
こんにちわ、クセノツヨイ映像制作会社トビガスマルの廣瀬です。
長野県上田市の山肌にひっそり佇む無言館(戦没画学生慰霊美術館)を訪ねました。国道 18 号を外れ、つづら折りの坂道を 15 分─武骨なコンクリートと浅間石の建物に足を踏み入れた途端、ひんやりした静寂が肌にまとわりつきます。
館内には戦没画学生が遺した未完の絵と絵筆・パレットが整然と並び、「描くこと=生きること」という息遣いが今も脈打っていました。
本記事では、無言館のアクセス・営業時間・チケット情報、第一展示館や傷ついた画布のドームの見どころを現地レポート形式でお届けします。さらに、映像制作者として持ち帰った3つの気づきと、周辺の上田観光モデルコースもご紹介。写真の代わりに言葉で立ち上げる“未完の物語”に、どうぞ耳を澄ませてください。
目次
無言館とは?――戦没画学生たちが遺した“未完のアトリエ”
1997 年開館の無言館は、第二次大戦で命を落とした画学生・美術教師 200 名以上の遺作と遺品を収蔵する私設美術館です。標高 650 m の丘に建つ質素な空間は、まるで時間ごと封じ込めたアトリエ。今回ここを訪ねたのは戦後 80 年特集で取材した現代美術家小野和則さんの詩の真意を確かめるためでした。
死んでも
死んでも
死にきれない生きても
生きても
生ききれないそう言う
すべてを
私は思う
小野さんは「節目ではなく失われた命に祈りを捧げるとともに、荒廃の中から未来を切り開いた世代の営みに敬意を寄せる。その繰り返しこそが、記憶をつなぐ営みになる」と語ります。その言葉を噛みしめるうち、無言館が浮かびました。館内は撮影禁止──私はカメラをバッグにしまい、静寂と向き合うことで詩の行間に宿る祈りを探る旅を始めました。
“無言”が語りかけるもの
第一展示館には塗り残しのキャンバス、乾きかけの油彩、兵役前夜に描かれた自画像。隣には絵筆・パレット・日記帳が寄り添い、「描くこと=生きること」だった若者たちの時間が今も続くかのよう。耳を澄ますと、詩の一節が別のメディアとなって立ち上がる──そんな体験でした。
次章ではアクセス・営業時間・チケット情報を現地メモとともに整理します。写真は外観のみですが、言葉と数字で“未完のアトリエ”への道案内をお届けします。
【アクセス・営業時間・チケット】無言館への道案内ガイド
車・電車・バスでの行き方
| 交通手段 | ルート概要 | 所要時間 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 車 | 上信越道〈上田菅平 I.C.〉→国道18号を長野方面へ約10km 山口交差点を右折し県道65号へ。案内板を左折後、山道を約4km |
約25 分(I.C.から) | 館前に無料駐車場30台。冬期はスタッドレス必須 |
| 電車+バス | JR北陸新幹線〈上田駅〉下車 → 上田バス「中仙道線」 〈無言館入口〉下車→徒歩15 分(上り坂) |
バス約25 分 +徒歩15 分 |
土日祝は1時間に1本程度。帰路の時刻を要確認 |
| タクシー | 上田駅温泉口タクシー乗り場 → 無言館 | 約20 分 | 片道3,500〜4,000円目安。バス待ちを短縮したいとき便利 |
営業時間・休館日・チケット料金 (2025年9月時点)
- 開館時間:9:00〜17:00(最終入館 16:30)
- 休館日:毎週火曜日(祝日の場合は翌日休)・年末年始
※展示替え期間の臨時休館あり。公式サイトで要確認 - 入館料:大人 1,000 円/高校・大学生 800 円/中学生以下 500 円
- 割引情報:上田電鉄〈別所温泉駅〉で配布の観光クーポン提示で 100 円引き
- 撮影規定:館内全面撮影禁止(外観・庭は静止画のみ可)
旅のヒント
上田駅からのバスは「塩田町」行きと「中仙道線」の2系統がありますが、無言館最寄りは後者です。東京発の午前中便であれば、新幹線〈かがやき号〉 → 上田駅 10:00 着 → 10:20 発バス → 11:00 無言館着 がスムーズ。午後はバス本数が減るので復路の最終(16:20頃)を逃さないよう注意してください。
なお、冬季(12〜2月)は坂道に積雪・凍結が残るためスタッドレス+チェーン推奨です。館内は暖房がありますが展示室はやや冷えるので、厚手の上着をお忘れなく。
無言館内の見どころ5選――“未完のエネルギー”に触れる場所
無言館は二つの展示館と回廊、中庭だけの小さな美術館ですが、滞在2時間でも足りないほど密度の高い体験が詰まっています。撮影禁止のため写真は載せられませんが、ここでは映像屋の視点で「絶対に見逃せない5ポイント」を言葉でスケッチしました。
第一展示館:遺作が並ぶ“静止した時間”
- 油彩の筆跡が止まった位置—未乾燥の絵の具の盛り上がりから、筆を置いた「その瞬間」が読み取れる。
- 等身大の自画像—兵役前夜に描かれた1枚。背景を塗り残したまま出征した経緯が、キャプションで補足されている。
- パレットと旅券—絵具が固まったパレットと軍用旅券が同じケース内に展示され、“創作⇄出征”の急転を物語る。
傷ついた画布のドーム:修復と展示のあいだで
2008 年に増設された第二展示館。半円ドーム内部に“傷ついた画布”が吊るされ、壁面には修復工程の写真が時系列で並びます。
視覚だけでなく嗅覚—溶剤と古い麻布の匂い—が体験の一部になる珍しい空間で、「保存しながら見せる」という矛盾をどう乗り越えるかがテーマ。
祈りの部屋:絵筆と手紙が語る“個”の物語
第一展示館奥にある半地下の小部屋。家族宛のはがき、学友の寄せ書き、兵役直前に綴られた「最後のスケッチ」など文字資料が中心。耳を澄ませると来館者の足音すら吸い込む静寂で、“生ききれない”という小野和則さんの詩句が心の中で反響します。
回廊のガラス窓:未完のキャンバスと浅間山
第一展示館とドームを結ぶ回廊の途中、幅1 m ほどのガラス窓から浅間山の稜線が切り取られます。未完の絵筆と雄大な自然がワンカットに収まる、文字どおりの“絵画的フレーム”。夕方は斜光がキャンバスに当たり、筆跡の凹凸が浮かび上がる瞬間が必見。
中庭の「無言の鐘」:静寂を打ち破る1打
退出前に立ち寄れる中庭には、来館者が1人1打だけ突ける鐘が置かれています。金属音が館内に低く響き、静寂に小さな波紋をつくる儀式のよう。映像屋としては「無音の中に置かれた最小の音」がどれだけ強いメディアかを痛感しました。
トビガス流 “鑑賞ワンポイント”:展示キャプションを読む前に作品と5秒だけ対峙→その後キャプション確認→もう一度作品を観る、の“W ルック”方式が感情の揺れを最大化してくれます。
次章では、小野和則さんの詩と無言館をつなぐ3つの気づきを映像制作の観点から掘り下げます。
トビガスマルが感じた3つの学びと映像制作へのヒント
小野和則さんの詩と無言館の静寂を行き来しながら、私たちが持ち帰ったのは祈りと継承を映像でどう扱うかという問いでした。以下の3つは、次回の現場で即アクションに落とし込めるヒントでもあります。
未完の物語を“今”に継ぐ──記録の意味
無言館にある絵の多くは「未完」。しかし未完だからこそ観る側が続きを想像し、物語が更新されると気づきました。映像制作でも「完成させ過ぎない」余白が、時代を超えて観客を招き入れる装置になる。戦後80年の節目は“区切る”のではなく“つなぐ”編集点。未完の筆跡を未来のクリエイターへ手渡す感覚で、素材の保存フォーマットとメタデータを整備することを強く意識しました。
静寂は最強のメディア──音のないフレーム
館内撮影禁止の静けさは、逆説的に「聴かせる」力を持っていました。無音は観客自身の呼吸、衣擦れ、心音を浮き立たせ、体内から物語を再生させます。次回のドキュメンタリーでは、意図的にナレーションもBGMも入れない 30 秒の“無音パート”を差し込む構成を採用予定。
Point:無音部分は-35 dBFS 付近の環境ノイズだけ残し、観る側の「内側の音」を呼び覚ます。
保存と発信は同時進行──未来を切り開く営み
傷ついた画布のドームで見た「展示しながら修復する」姿勢は、映像アーカイブにも適用できます。撮って終わりではなく、公開フォーマットの刷新と劣化対策を平行させることで、作品は“現在進行形”のまま未来へ滑走します。具体的には、撮影素材をProRes RAW+HDRで残しつつ、低容量 H.265/AV1へ同時エンコード。クラウド側でチェックサム定期検証を実装し、次世代視聴環境へシームレスに更新できる設計を進めています。
小野さんの言葉「失われた命に祈りを捧げ、荒廃の中から未来を切り開いた営みに敬意を寄せる」──その“営み”は、映像を残す私たち自身の仕事でもあると確信しました。次章では、この理念を旅の延長線に置く上田観光モデルコースと、無言館との合わせ技で深まる学びをご案内します。
無言館周辺観光スポット&モデルコース|祈りと継承をたどる上田半日旅
無言館で“未完のアトリエ”に触れたら、上田市内の「祈り」「復興」「未来」を感じられる場所をセットで巡ると学びが立体的に広がります。ここでは所要4〜5時間で回れる半日モデルコースを提案します。
別所温泉|北向観音と外湯めぐり(車で20分)
- 北向観音—善光寺と向かい合わせに建立された“現世利益”の祈りの場。戦没画学生の冥福を願いながら、「いまを生きる自分」の健康も祈念できます。
- 外湯「石湯」—源泉 42℃、入浴料 200 円。静寂のあとに身体を解きほぐすのに最適。
上田城跡公園|真田石と復興のシンボル(車で30分/バス40分)
- 戦国時代に二度落城せず「不落城」と呼ばれた真田石に触れると、“荒廃の中から未来を切り開く営み”を体感。
- 公園内の櫓門資料館では、城復興プロセスの展示があり、無言館の修復活動とリンク。
上田映えカフェ「monami coffee」|未来を語る余白(城跡から徒歩5分)
- 地元焙煎のシングルオリジンが 500 円。Wi-Fi&USB 電源完備で、無言館の感想を“今”のうちにメモするのに便利。
- 店舗壁面には上田市の若手アーティスト作品が月替わりで展示──“未完→未来”を象徴する場。
モデルタイムテーブル(東京発日帰り)
| 時刻 | 行程 |
|---|---|
| 08:24 | 東京駅発 かがやき503号 → 上田駅 09:29 着 |
| 09:50 | 上田駅発 バス〈中仙道線〉→ 無言館入口 |
| 10:30-12:00 | 無言館 鑑賞 |
| 12:30-14:00 | 別所温泉 北向観音+外湯 |
| 14:30-15:30 | 上田城跡公園・櫓門資料館 |
| 15:40-16:20 | monami coffee でメモ&休憩 |
| 16:43 | 上田駅発 あさま628号 → 東京駅 18:08 着 |
ポイント:無言館で受け取った“祈りと継承”を、北向観音の現世利益、上田城の復興史、若手アートの現在進行形へとバトンリレーすると、小野和則さんの詩が「過去→今→未来」を貫く一本の線として腑に落ちます。
次章では旅の締めくくりとして、よくある質問(FAQ)をまとめ、撮影可否や所要時間など実務的な疑問をクリアにします。
よくある質問(FAQ)――撮影可否・所要時間・混雑回避
Q1. 無言館は館内で写真や動画を撮影できますか?
A. できません。作品と静寂を守るため館内は撮影全面禁止です。外観・中庭のみ静止画撮影が可能ですが、三脚・ドローンは不可です。
Q2. 所要時間はどのくらい見ておけば良いですか?
A. 第一展示館・傷ついた画布のドーム・中庭をじっくり鑑賞すると約90分〜120分。キャプションを読み込むスタイルなら 2 時間を目安にしてください。
Q3. 混雑を避けるおすすめの時間帯は?
A. 一般団体が少ない平日 10:00〜11:30 が比較的空いています。土日祝は 14 時以降にバスが減るため、午前中の到着が安心です。
Q4. 冬に行く際の注意点は?
A. 館前の坂道が凍結するのでスタッドレス+チェーン推奨。館内は暖房が効いていますが展示室はやや低温です。厚手の上着をご持参ください。
Q5. 周辺に食事できる場所はありますか?
A. 最寄りは別所温泉(車 10 分)か上田駅周辺。館付近に飲食店はないため昼食は別所温泉街で外湯めぐりとセットにするとスムーズです。
まとめ|無言館で“語らぬ声”に耳を澄ませる旅へ
戦没画学生の未完の筆跡と、現代美術家・小野和則さんの詩——
「失われた命に祈りを捧げ、荒廃の中から未来を切り開いた世代の営みに敬意を寄せる。」
この言葉を胸に無言館の静寂へ身を置くと、“継承は節目ではなく日々の営み”だと実感します。撮影禁止という制約はむしろ、レンズではなく五感と想像力で物語を受け取り、未来へ手渡す行為を促してくれました。
- 祈り──無言館の静寂に身を委ね、未完のエネルギーに心をひらく
- 継承──別所温泉・上田城跡で「復興」と「現在」を重ね合わせる
- 未来──若手アートや映像保存の実践で“次の語り手”へバトンを渡す
旅はここで終わりではありません。この記事があなた自身の“未完の物語”に小さな火を灯し、日常の中で祈りと敬意を紡ぐきっかけになれば幸いです。
もし無言館を訪ねたら、ぜひ #無言館の静寂 で感想を共有してください。
私たちトビガスマルも、次の映像プロジェクトで“未完を未来へつなぐ営み”を形にしていきます。

2025.02.07
あなたは「太陽光発電なんて雪国では無理だろう」とあきらめていませんか? そんな悩みを解決するために生まれたのが、Reeele(リール)株式会社様のソーラーカーポート「YUKIJI」。両面式パネルによる雪溶かし機能や、一枚一枚のパネルを最大効率で稼働させる独自の仕組みで、雪下ろし不要...


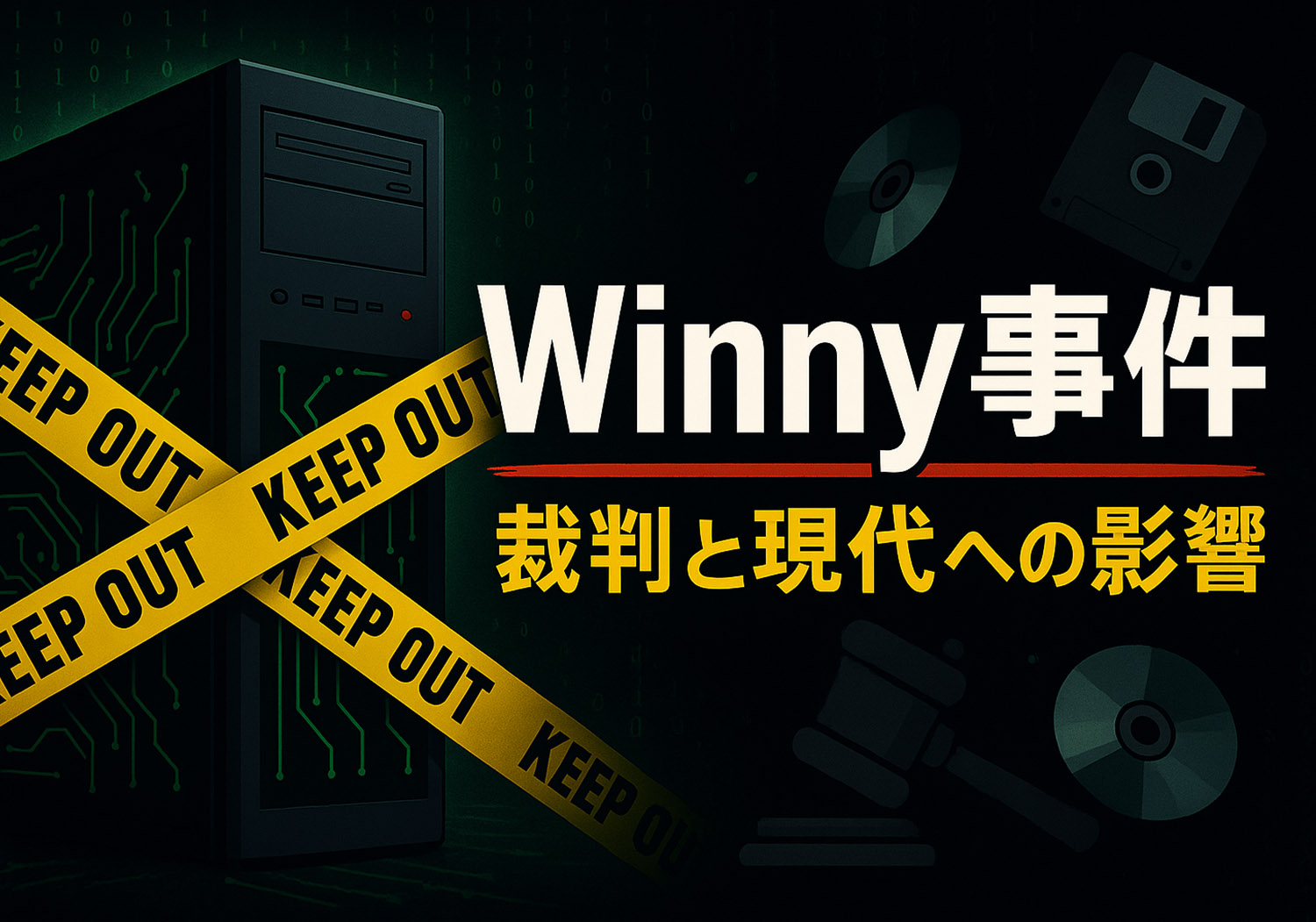
コメント