
こんにちわ、合同会社トビガスマル代表の廣瀬です。
近年、人手不足が深刻化する中、各業界でクリエイターという職種に熱い視線が注がれています。
デザイン・映像・SNS・ライティングなど、あらゆる業種が“表現力”を求めている今、
クリエイターはただの制作担当ではなく、価値創出の中心人物になりつつあります。
そして、こんな印象を持たれている方も多いのではないでしょうか?
「クリエイターって、メンタル強いよね」
確かに、納期、クオリティ、他人からの評価──
シビアな現場を乗り越えてきた人が多く、メンタル面での“タフさ”が求められる仕事でもあります。
でもその一方で、
強さの裏には“見えない疲労”や“燃え尽き”も潜んでいるのが、クリエイティブの現場。
この記事では、クリエイターにとってのメンタルヘルスがなぜ重要かを掘り下げ、
創造力を守り、育てていくための考え方・実践法・サポート手段をまとめてご紹介します。
「作品をつくる力」と同じくらい、「自分を守る力」も、大切にしていきませんか?
![]()
目次
本記事の根拠と参考資料(最新版)
- バーンアウト(燃え尽き)はICD-11で「職業上の現象」と定義(医学的診断名ではない)。
- 睡眠は成人で「個人差を踏まえつつ6時間以上を目安」に休養感の確保を重視。
- 運動は不安・抑うつなど横断的に症状軽減に寄与することを示す包括レビューが蓄積。
- マインドフルネスは創造性(特に収束的思考)の向上に有効というメタ解析。
出典:WHO(ICD-11のバーンアウト定義)、厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」、運動の効果に関する包括レビュー、創造性×マインドフルネスのメタ解析。
クリエイターのメンタルヘルスが重要な理由
クリエイターという仕事は、自由で創造的な一方で、目に見えにくいストレスや孤独と常に隣り合わせです。
クライアントの期待、自分の理想、終わらない修正依頼、評価されない不安── 「好きでやっているから」「慣れているから」と片付けがちな負荷は、積み重なると想像以上に心をすり減らします。
ここでは、クリエイターとメンタルがどう関わっているのか、3つの視点で掘り下げてみましょう。
創造性とメンタルの密接な関係
創造性は、論理だけでは生まれません。 むしろ感情や感性が大きく関わるため、メンタルが不安定なときほど、アイデアが湧かなくなることも。
逆に、
- 心に余裕があると発想が広がる
- 安心できる環境だと試行錯誤がしやすい
- 自己肯定感があると“攻めた表現”もできる
メンタルの状態は、そのままアウトプットに反映されるのが、クリエイティブ職の特徴です。
プレッシャーとストレスの影響
納期・修正・クライアントとのやりとり。 どんなに経験を積んでも、「納品するまで終わらない不安」はついて回ります。
特にフリーランスや小規模チームでは、
- 「売上を気にしながら創作する」
- 「ひとりで全部背負っている」
という環境がストレスを慢性化させやすく、知らないうちに消耗していくケースも。
適切な休息や発散がなければ、燃え尽き(バーンアウト)や慢性的な無気力感につながる危険性もあります。
自己肯定感の維持
クリエイターの多くは、「自分の表現=自分そのもの」という感覚を強く持っています。
だからこそ、
- 作品が否定されると、自分も否定された気になる
- フォロワー数や再生数に振り回される
- 他人と比べて「自分はダメだ」と感じてしまう
このように、自己肯定感が揺らぎやすい職種だからこそ、“自分を認め直す習慣”が重要になります。
具体的なメンタルヘルス対策
「メンタルが大事なのはわかるけど、何をすればいいのか分からない」 そう感じているクリエイターの方は多いはず。
ここでは、実際にすぐ取り入れられるシンプルな対策を3つご紹介します。
どれも「習慣化しやすい」ことを重視しています。まずはひとつ、今日からでも始めてみましょう。
休息とリフレッシュ
「集中が続かない」「ミスが増えた」「やる気が出ない」 それは、“頑張りすぎ”のサインかもしれません。
ポイントは、
- 物理的に離れる: デスクから立ち上がって散歩するだけでもOK
- 五感を刺激する: 香り・音楽・景色を変えてリセット
- “何もしない”時間をつくる: 予定を詰めすぎない
休むことも仕事のうちと割り切って、意識的に“止まる”時間をとりましょう。
運動習慣の導入
運動は脳内のセロトニンやドーパミンを活性化させ、気分を安定させてくれる効果があります。
といっても、いきなりジムに通う必要はありません。
- 朝のストレッチ5分
- 階段を使う・一駅歩く
- 15分の軽い散歩で“画面脳”をリセット
クリエイターはどうしても座りっぱなし&視線が固定されがち。
体を動かすことが、発想の切り替えや気分転換にもつながります。
瞑想とマインドフルネス
情報過多のこの時代、「脳が休まる時間」が圧倒的に足りていません。
そこで注目されているのが、呼吸と意識に集中する“マインドフルネス瞑想”です。
やり方は簡単:
- 椅子に座って、目を閉じる
- 呼吸にだけ意識を向ける(1日3分〜でもOK)
「今ここ」に意識を戻すことで、思考の渦や感情のノイズから少し離れることができます。
無料アプリ「Headspace」や「Inscape」なども活用できます。
実務ですぐ使える:1日10分セルフケア
- 2分:呼吸リセット(4秒吸う→6秒吐く×10)※マインドフルネスの簡易形。
- 5分:歩く/伸ばす(屋外に出て視界を遠くへ)※運動は気分安定に有効。
- 3分:今日の“やったこと”3行メモ(達成感の可視化で自己効力感UP)。
※運動・マインドフルネスの効果は上掲のエビデンスを参照。
クリエイターが利用できるサポート
「ひとりで抱えない」ことは、メンタルヘルス対策の大前提です。
クリエイターはフリーランスで孤独になりやすく、会社に属していても「共感してくれる人が少ない」と感じることもあります。
ここでは、プロとして活動するクリエイターが、必要に応じて使える支援・相談の選択肢を紹介します。
コミュニティへの参加
気持ちが沈んだとき、「分かってくれる誰かがいる」という感覚は非常に大きな支えになります。
おすすめの方法:
- オンラインのクリエイター交流コミュニティに参加する(Slack/Discordなど)
- 地域のコワーキングスペースや異業種交流会で顔を出す
- X(旧Twitter)で同業フォロー&ゆるく交流
「成果」ではなく「共感」を求められる場をひとつでも持っておくと、気持ちがずっと楽になります。
カウンセリングサービスの利用
「なんか最近つらい」「理由は分からないけど疲れてる」
そんなときは、専門家に話すという選択肢も大切です。
利用しやすいサービス:
- cotree(コトリー): オンラインカウンセリング。顔出し不要・匿名可
- BetterHelp(英語対応): 海外サービス。グローバルな相談環境を求める人向け
- 企業勤めの方は、社内のEAP(従業員支援プログラム)も確認してみましょう
心のメンテナンスは、“元気なうちに”こそしておくのがベストです。
公的な相談窓口(困ったら、今すぐ)
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556(各都道府県の窓口へ接続)
- #いのちSOS:0120-061-338(24時間365日/フリーダイヤル)
- 日本いのちの電話 公式サイト:最新の受付時間・番号を確認のうえ利用
※緊急時は119または最寄りの救急へ。自傷他害のおそれがある場合は独りで抱えないでください。
相談窓口の活用
「いきなりカウンセリングはハードルが高い…」という方は、公的な相談窓口の利用も検討してみましょう。
おすすめの窓口:
- こころの健康相談統一ダイヤル: ☎0570-064-556(各都道府県の精神保健福祉センターにつながります)
- 日本いのちの電話: 0570-783-556
- 労働者健康安全機構・メンタルヘルス支援センター(産業医相談なども可能)
悩みを“言語化”すること自体が回復の第一歩になることもあります。
睡眠:創作の“燃料”を切らさない
- 目安は6時間以上+休養感(個人差あり)。休日の“寝だめ”で体内時計を崩し過ぎない。
- 就寝90分前の強光・カフェインを控える/就床時刻を一定に。
- 昼に10–20分の仮眠(夕方以降は避ける)で集中回復。
出典:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」。
メンタルヘルスを維持するための習慣
心の不調は、急にやってくるものではなく、少しずつ蓄積されていくものです。
だからこそ、日々の習慣の中に「自分の心を整える時間」や「気づける仕組み」を組み込むことが、一番の予防策になります。
ここでは、クリエイターが毎日取り入れやすいメンタル維持のための3つの習慣を紹介します。
目標設定と達成感
モチベーションが落ちているときほど、「今日何をやったか分からない…」と感じがちです。
そこでおすすめなのが、“小さな目標を立てて、ちゃんと終わらせる”こと。
たとえば、
- 「今日は3案だけ出す」
- 「メール返信は午前中に片付ける」
- 「サムネを2パターン作る」
小さくても“やったぞ”という達成感は、脳に「自分はできる」という感覚を積み重ねてくれます。
自己評価の適正化
クリエイターあるあるとして、「自分にだけめちゃくちゃ厳しい」という傾向があります。
でも、作品や発言がすべて自分の人格とイコールではありません。
「いい時もあるし、ダメな時もある」
「誰かに合わなくても、誰かには響いている」
そんなふうに、“自分を外から見る視点”を持てると、メンタルはグッと楽になります。
感謝の気持ちを持つ
意外に効くのが、「ありがとう」を意識して増やすこと。
たとえば、
- 作品にリアクションくれた人に「ありがとう」
- 編集を手伝ってくれた仲間に「ありがとう」
- 「今日も机があって、Wi-Fiがつながってる」ことに気づいて「ありがとう」
感謝の視点は、自己否定や不安のループから抜け出すスイッチにもなります。
ちょっとした習慣が、長い目で見れば大きな支えになる。 だからこそ、“続けられる小さなケア”が最強なのです。
まとめ
クリエイターという仕事は、自由で、表現豊かで、やりがいがある一方で、自分の内面と向き合い続ける繊細な職業でもあります。
「好きなことを仕事にしているから大丈夫」
「みんなも頑張ってるから、自分も…」
そう思って頑張り続けた結果、知らず知らずのうちに心がすり減ってしまう── そんなことが、業界の中でも静かに広がっています。
記事の振り返りポイント
- 創造性とメンタルは直結している
- “強そうに見える”人ほど、実は我慢しているかもしれない
- 対策は「大げさなこと」ではなく、「日常に小さく組み込む」こと
- 相談できる場所・人・習慣を持っておくことが、最大の安心材料

トビガスマルでも、映像制作・執筆・企画・編集など、創造に関わるすべての仕事を「人」で回しています。
だからこそ、パフォーマンスを出し続けるには、まず“心の余白”を守る仕組みが必要だと、日々感じています。
作品は、心の鏡。
だからこそ、クリエイターであるあなた自身のメンタルも、何より大切にしてほしいと思います。
よくある質問(クリエイターのメンタル)
Q.「燃え尽き」と病気の違いは?
A. 燃え尽き(バーンアウト)はWHOのICD-11で“職業上の現象”として定義。医学的診断名ではなく、慢性的な職場ストレスに起因する症候群です。辛さが続くときは専門家に相談を。
Q. まず何から始めればいい?
A. 10分セルフケア(呼吸2分・歩く/伸ばす5分・記録3分)→睡眠の見直し→信頼できる人/公的窓口への相談の順で。
Q. 相談先はどこ?
A. 厚労省のこころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)、#いのちSOS(0120-061-338 24h)、日本いのちの電話公式サイトで最新の受付情報を確認。

2025.05.18
共感力とは?その重要性を再確認 共感力の定義とビジネスにおける役割 共感力は、ざっくり言うと「相手の気持ちや考えを汲み取る力」のこと。 映像制作でもクライアントさんの「こんな雰囲気を作りたい」という想いをちゃんと理解しないと、良い映像が作れません。 ビジネスの場面でも...

2025.03.03
圧倒的な転送速度と驚くほど安定した持続性能に加え、現場視点の細かな使い勝手が際立つ本製品は、映像制作のワークフローを一新する可能性を秘めています。今回は実際の使用感も交えながら「PG10 Pro」の魅力を徹底解説します。 映像制作の現場にSSDが必要な理由 近年、4Kや8Kといっ...
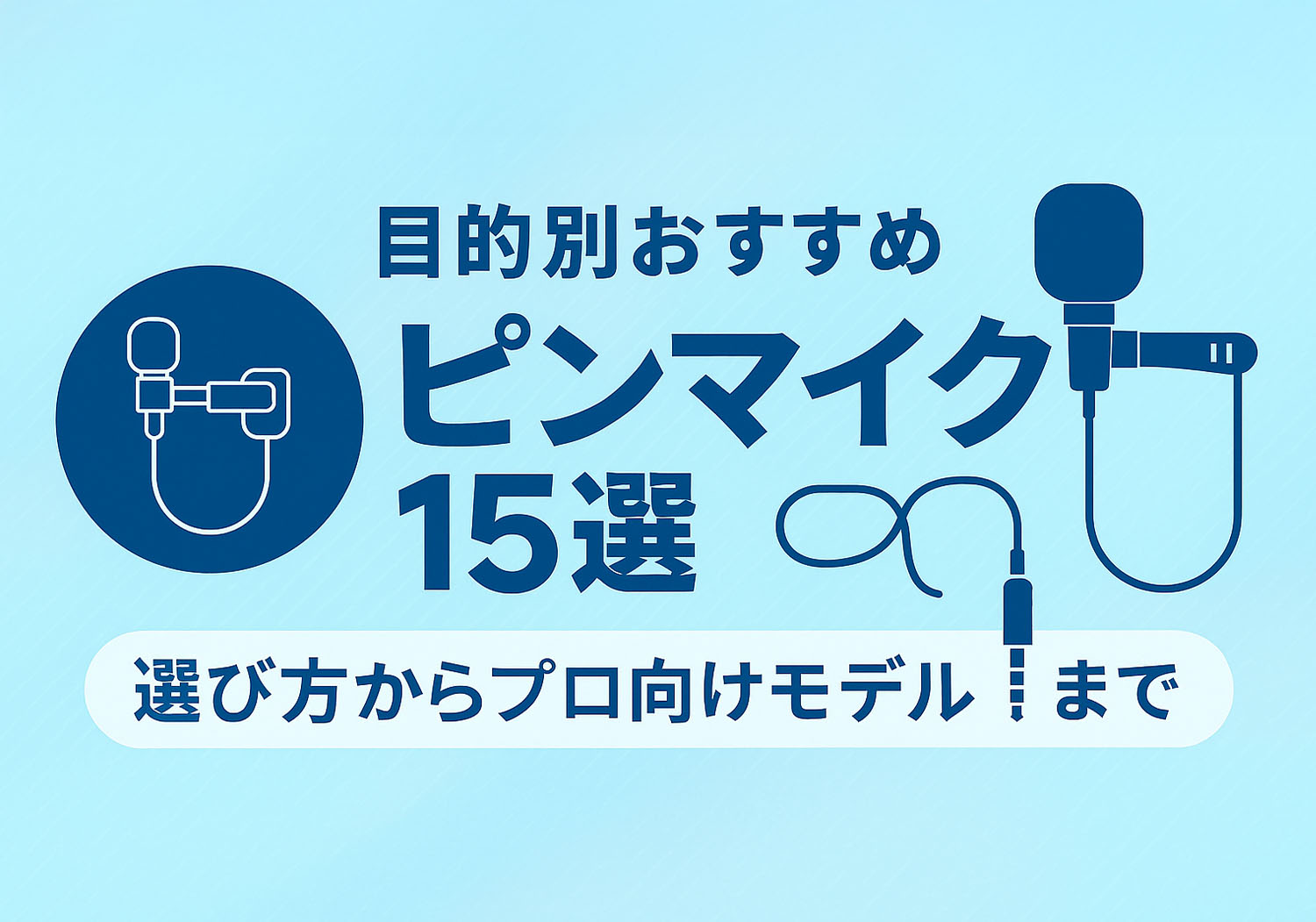
2025.05.25
せっかく映像がうまく撮れていても、音が悪いと、全体の印象がガクッと下がる。 そんな経験、私たちの現場でも何度もしてきました。 そこで役に立つのが、小さくても信頼できる相棒「ピンマイク(ラベリアマイク)」です。 胸元などに装着して使えるピンマイクは、声をダイレクトに拾い、雑音を抑え、...


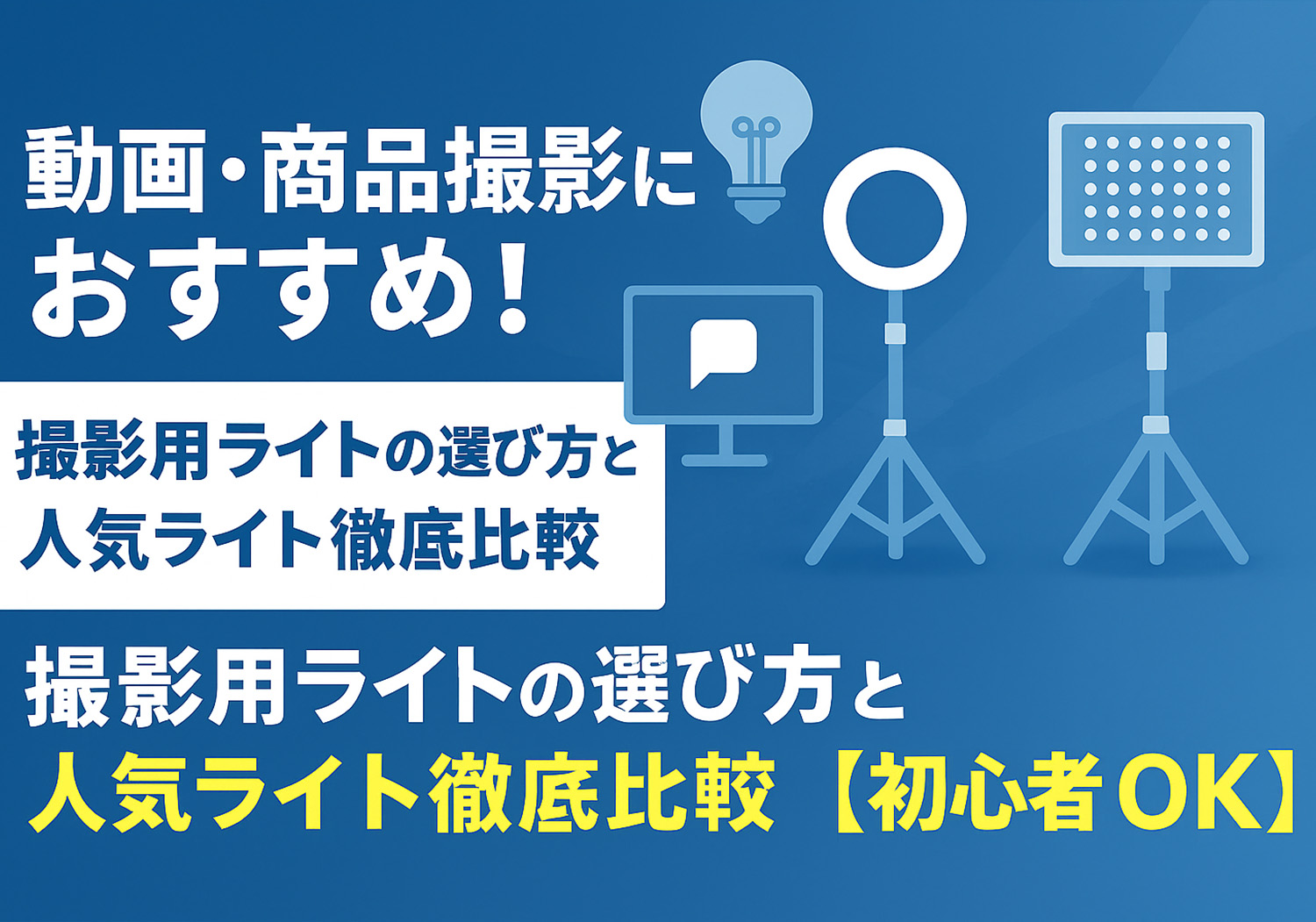
コメント