
こんにちわ、クセノツヨイ映像制作会社トビガスマル代表社員の廣瀬です。
「Adobe Creative Cloud は 個人版(Individuals)で十分? それとも 法人版(Teams/Enterprise)が正解?」
――答えは、使うアプリ数よりも、ライセンス管理・資産の所有・セキュリティで決まります。
本記事では 個人版 vs 法人版の違いを料金・機能・管理・コンプライアンスの4軸で徹底比較し、Admin Console・SSO・席の再割当・アセット保護といった“現場で効く”ポイントを、導入フローとチェックリストつきでわかりやすく解説します。
こんな人に:
・フリーランス/個人事業主でコスト最適化したい
・数名〜数十名のチームで退職・外注入替に強い運用を作りたい
・情報システム・広報・制作部門でライセンス統制とコンプラを両立したい
読み終わる頃には、あなたの組織にとっての最適プランが即断できるはず。では、基本の違いから見ていきましょう。
※価格・仕様は変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

2025.06.22
本記事では、学割付きパッケージを提供する代表的な 3 校 アドバンスクールオンライン・たのまな・デジハリ ONLINE を 価格・講座内容・サポート体制の3視点で徹底比較。 「買うならどこが自分に合う?」「動画講座の質は?」「質問サポートの違いは?」 ──そんな疑問を、早見表...
目次
Adobe Creative Cloud 個人版 vs 法人版:基本機能とライセンスの違い
違いの本質はアプリ数ではなく、資産の所有権/コラボの設計/管理とセキュリティ。下の早見で土台をそろえましょう。
| 観点 | 個人版(Individuals) | 法人版(Teams/Enterprise) |
|---|---|---|
| アプリ | 単体 or All Apps(中身は同等) | 同等のアプリ+チーム運用前提の周辺機能 |
| ストレージ | 個人アカウント保有 | 1TB/ユーザーのプール型、会社所有ライブラリ、クラウドドキュメント180日履歴 |
| 資産の扱い | 原則ユーザーに帰属 | 退職者からのアセット回収(Asset Reclamation)可 |
| 管理 | 各自が購入・管理 | Admin Consoleで一元管理(席の追加・回収、請求、配布) |
| 認証 | Adobe ID | Enterprise/Federated ID(SSO)対応 |
| サポート | 通常サポート | 24/7テクサポ・専門家1:1セッション(プランにより) |
| 端末 | 同一ユーザーで同時サインイン2台/同時使用は1台まで(共通仕様) | |
上記のプール型1TB、会社所有ライブラリ、180日履歴、資産回収、Admin Console、24/7サポートは公式が明記。端末の同時利用制限も共通ポリシーです。
個人版と法人版の料金プラン比較
個人版は「単体アプリ/All Apps」の月額、法人版は席(シート)単位で契約し増席・再割当が容易。為替・キャンペーンで変動するため、最新料金は公式の料金ページを参照してください。
利用可能なアプリケーションと機能の違い
- アプリ自体は同等。ただしTeams/Enterpriseはプール型1TB、会社所有ライブラリ、クラウドドキュメント180日履歴、アセット回収で継続案件・人員入替に強い。
- Stock をチーム契約にするとライセンスをプールでき、個人版のような“各自課金バラけ”を防げます。
ライセンス管理とアカウント管理の違い
- Admin Consoleでユーザー/席/請求を一元管理、配布ツールでIT展開も簡素化
- Enterprise/Federated ID+SSOで組織のID基盤(Azure AD/Okta等)と連携。既存Adobe IDは組織IDへ移行手順あり。
- 端末ポリシーは共通:2台までサインイン/同時利用1台。運用ルールとして明文化を。
クイック結論▶
人が入れ替わるチーム・外注混在なら法人版(資産保護/SSO/再割当)。
固定メンバーの個人事業なら個人版(低コスト・シンプル)。
企業がAdobe CC 法人版を選ぶべき理由:メリットとデメリット
チームコラボレーションの促進と効率化
制作現場の最大の敵は、「最新版どれ問題」。
法人版なら、会社所有のライブラリ(カラー/フォント/ロゴ/テンプレ)とレビュー共有がワークフローに組み込まれ、誰が何をどこまで進めたかが一目で揃います。
- 共有ライブラリ:ブランド要素を一元配布→案件ごとの齟齬を削減
- Share for Review:ブラウザで差分指示→往復の書き出しを最小化
- 役割ベース運用:デザイナー/外注/発注側で権限を分離
現場Tip▶ ライブラリ名の頭に [Brand] [Campaign] を付けて階層整理。検索ヒット率が上がります。
セキュリティとデータ管理の強化
退職・外注終了は“情報流出の山場”。法人版はアカウントを組織IDで発行し、離任時のアセット回収とアクセス遮断を管理画面から即実行できます。SSO(社内ID連携)を使えばパスワード管理の属人化も解消。
- 組織所有のクラウド資産:人の出入りがあってもデータは会社に留まる
- アクセス制御:共有リンクやライブラリの公開範囲をポリシー化
- 監査性:変更履歴・共有履歴を運用ログで把握しやすい
管理機能の充実とコンプライアンスの遵守
Admin Consoleでライセンス割当/回収、請求一本化、ユーザー権限の一括変更が可能。
法務・情シスの観点でも、契約・権限・資産を“会社単位”で管理できるのが最大の利点です。
- 席(シート)単位で増減が柔軟:繁忙期だけ増やすなどの運用が現実的
- 請求の集約:部門ごとのバラ購入を防ぎ、コスト把握が容易
- ポリシー運用:データ持ち出し・共有範囲に社内ルールを適用しやすい
メリット/デメリット早見表
| メリット(Teams/Enterprise) | デメリット(留意点) |
|---|---|
| 資産が会社所有、離任時の回収が容易 | 個人版より月額単価が高めになりがち |
| Admin Consoleで席の再割当・一括管理 | 初期設定(SSO/権限設計)にIT工数が必要 |
| 共有ライブラリ&レビューで統一品質を担保 | 外注が個人版のみの場合、権限設計に工夫が要る |
| 監査性・セキュリティ要件を満たしやすい | 運用ルール(命名・保管先)をドキュメント化しないと逆効果 |
導入の目安(迷ったら)
年内に人の入替が複数回/外注と社内の混成チーム/ブランド資産の共有が多い
→ 法人版で早めに基盤を固めると後が楽です。
次章では、個人版がフィットするケースを整理します。フリーランス/小規模チームの“身軽さの強み”も見逃せません。
個人版の利用が適しているケース:フリーランスや小規模事業者
個人版(Individuals)の強みは 低コスト・導入の速さ・シンプル運用。
1人〜数名での制作や、外注中心のプロジェクトでは“軽さ”こそが生産性になります。
コストを抑えたい個人クリエイター
- 単体アプリで最小構成:Photoshop や Premiere だけなど必要分だけで開始。
- 解約・再契約が柔軟:案件の増減に合わせて月単位で見直しやすい。
- 2台までサインイン可:自宅PC+モバイルワーク用といった二拠点運用に対応(同時使用は1台)。
節約Tip▶ まずは単体アプリで開始 → 同時に2本以上使い始めたら All Apps に切替えると無駄が出にくいです。
機能制限が気にならない小規模プロジェクト
- 共有は軽量でOK:リンク共有・クラウドドキュメントの履歴で十分に回る規模。
- ブランド統一要件が緩い:色・フォント・テンプレの厳格な一元管理までは不要。
- 外注は各自の環境:外部パートナーが自分のアカウントで完結できる体制。
運用Tip▶ クライアント納品物はプロジェクト用の共有フォルダに集約(Drive/Dropbox等)。個人アカウントにだけ残さない仕組みを。
将来的なスケールアップの可能性
- まずは個人版で検証:ワークフローが固まるまで軽く走る。
- 人が増えたら切替:退職・出入り・ブランド統一が課題化した時点で法人版へ。
- 移行を想定した設計:命名規則/ライブラリ構成/保管先を最初からチーム運用前提で作ると移行が楽。
ミニ診断:以下に当てはまれば“いまは個人版”でOK
・運用メンバーが固定(出入りが少ない)/ ・共有はリンク中心で十分 /
・ブランド資産の厳格管理は不要 / ・請求は個人名義で問題なし
次章では、法人版導入のステップ(プラン選定 → 席の割当 → 運用設計)を、チェックリストつきで解説します。
Adobe CC 法人版導入のステップ:プラン選択から運用まで
導入は①要件定義 → ②プラン選択 → ③管理設計 → ④配布 → ⑤運用定着の5段で考えると迷いません。
ここでは、失敗しやすい“人の出入り”と“資産の所在”にフォーカスして手順化します。
自社のニーズに合ったプランを選ぶ
まずは現状を30分で棚卸し。
- 人数と出入り:正社員/契約/外注の人数、年間の入退場見込み
- 利用アプリ:Photoshop・Illustrator・Premiere・After Effects…“常用3本以上”ならコンプリート(All Apps)を検討
- 共同作業の度合い:ブランド要素(ロゴ・フォント・カラー)の共有頻度、レビューの往復量
- 管理要件:SSO必須か/資産を会社所有にしたいか/監査・ログの必要性
次にプランの目安。
- Teams(単体):特定職種だけに1〜2本配る。コスト最小。
- Teams(All Apps):制作職が複数アプリを横断。席(シート)を弾力配分。
- Enterprise:SSO・厳格な資産管理・監査が必要。人の出入りが多い組織向け。
見積りのコツ
・最初は必要席+10〜15%の余剰でスタート(繁忙期の臨時配布に備える)
・映像部門は After Effects/Media Encoder 分も忘れず積算
ライセンスの割り当てとユーザー管理
Admin Console 設計を最初に固めると後が楽です。
- 管理ロールを分担:
・システム管理(ID・SSO)/ 製作運用(ライブラリ・テンプレ)/ 請求管理(席と支払い) - グループ設計:部門×権限でグルーピング(例:
Design-AllApps、Video-AllApps、External-Single) - 配布ルール:
・社員=会社メールの組織ID/ 外注=有期の組織ID(終了日メモ必須)
・初回はテンプレ+ブランドライブラリを自動配布
オンボーディング手順(テンプレ)
- ユーザー作成 → 席割当(アプリ/ストレージ枠)
- プロジェクト用クラウドフォルダと共有ライブラリに参加させる
- 命名規則・保存先・レビュー手順を記した1枚マニュアルを送付
オフボーディング手順(テンプレ)
- 最終稼働日の前日までに席の回収予約(停止日時を決める)
- クラウドドキュメント/ライブラリの所有者を管理者へ変更
- 共有リンクを棚卸し→必要分だけ再発行(アクセス遮断)
移行時の“地雷”チェック
・個人Adobe IDに作品が残っていないか(必ず組織IDへ移管)
・Brandライブラリの“オーナー不在”状態を作らない(常に管理者を共同所有者へ)
・外注の一時IDは終了日と責任者を台帳管理
導入後の運用とサポート
“入れて終わり”にしないための定着運用を最初に決めます。
- 月次点検:アクティブ席/未使用席/共有リンク/ライブラリの整頓状況をチェック
- ナレッジ循環:テンプレ(PSD/AI/AE)・プリセット・MOGRT をライブラリ化して再利用
- レビュー整流化:Share for Review やコメントの返信期限・責任者を明確に
- 教育:四半期に1回、“保存先・命名・書き出しプリセット”だけは全社で再確認
- サポート窓口:一次受付(制作班)→ 二次(管理者)→ 三次(ベンダー)のエスカレーション表を用意
命名規則(例)
フォルダ:/Brand/2025_CampaignA/Assets/
ライブラリ:[Brand] Logo & Color/[Brand] Motion Presets
ファイル:BR_campA_KV_v03_20250814.psd(プロジェクト_用途_v番号_日付)
ここまで整えば、あとは年1回の棚卸し(席・外注・ライブラリ)で健全運用が続きます。
次章では、記事全体の要点をまとめ、“あなたはどちら?”をすぐ判断できるチェックを提示します。
まとめ:最適なAdobe Creative Cloudプランを選び、創造性を最大限に引き出そう
最終判断のカギは、資産の所有権・人の出入り・セキュリティ/監査要件の3点です。
アプリの数よりも、ワークフローに合う運用基盤を選ぶことが成果に直結します。
企業規模や利用目的に合わせて最適なプランを選択
クイック判定(30秒)
1) メンバーの入替や外注の出入りが多い? → 法人版(Teams / Enterprise)
2) ブランド資産を会社に帰属させたい? → 法人版
3) SSO・監査ログなどの要件がある? → Enterprise
4) 固定少人数・請求は個人で完結? → 個人版
- 個人版:低コスト/導入が速い/2台サインインで二拠点作業に好適。
- Teams:席(シート)単位の配布・回収/会社所有ライブラリで品質の統一。
- Enterprise:SSO・厳格な資産管理・監査性まで含めた全社運用に最適。
無料体験版を活用して機能を試す
判断を早めるには、短期トライアル+本番想定の小さな検証が近道です。
- 代表アプリを2本(例:Photoshop+Premiere)に絞って体験。
- 実案件データで「作成→共有→レビュー→書き出し」まで一連の流れを再現。
- チーム運用を想定し、共有ライブラリでフォント/カラー/ロゴを配布してみる。
- 法人検討中なら、管理画面のデモ(席の割当・回収/権限)を運用担当と確認。
検証ポイント▶ 共有の速さ/レビュー往復回数/保存先の統一度/離任時にデータを会社へ残せるか。
アドビ認定プロフェッショナルによるサポート
導入と定着を加速したい場合は、Adobe認定プロフェッショナル/認定パートナーのスポット支援が有効です。
- 対象領域:テンプレ設計(PSD/AI/AE)/ライブラリ運用/レビュー手順の標準化/色管理。
- 選定基準:認定バッジの有無/最新バージョン対応実績/NDA対応/教育資料の提供可否。
- 依頼の要点:現状の課題(共有・保存・命名)を1枚のフロー図にして渡すと改善が速い。
最後にもう一度:人が動くなら法人版、固定少人数なら個人版。
迷ったら“小さく試して、早く決める”。これが創造性を失速させない最短コースです。

2025.06.22
本記事では、学割付きパッケージを提供する代表的な 3 校 アドバンスクールオンライン・たのまな・デジハリ ONLINE を 価格・講座内容・サポート体制の3視点で徹底比較。 「買うならどこが自分に合う?」「動画講座の質は?」「質問サポートの違いは?」 ──そんな疑問を、早見表...

2025.06.21
・自宅の照明環境で本当にキレイに撮れるか ・編集PCが4Kデータに耐えられるか ・ライブ配信で30分たっても熱停止しないか ――購入前の“不安要素”を全部チェックしてから、本当に必要な機材だけを賢く買えます。 本記事では〈レンタルで試す→納得して買う〉をキー...


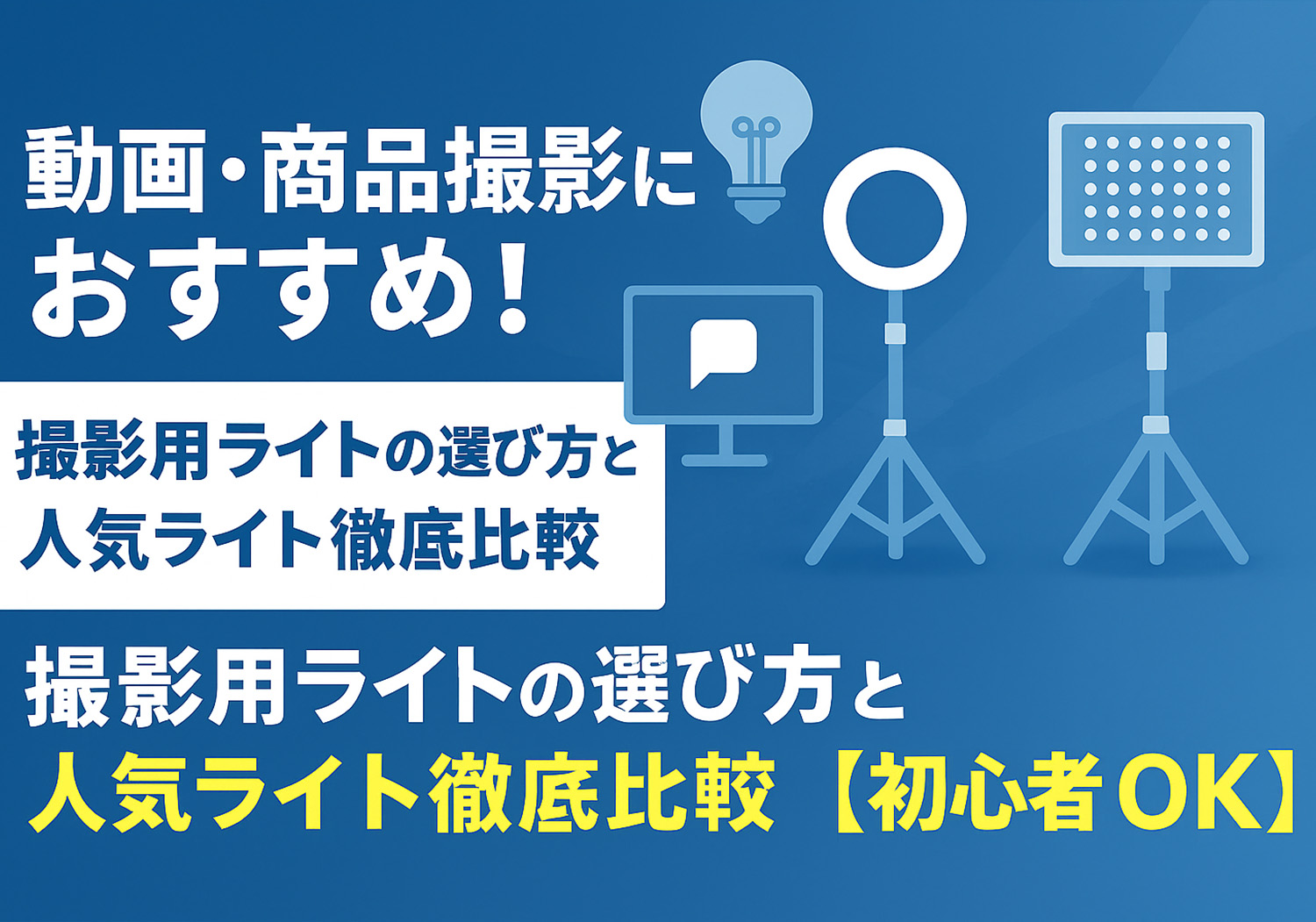
コメント