
こんにちわ、合同会社トビガスマル代表の廣瀬です。
私たちは日々、映像制作の現場で「光の力」を活かした撮影に取り組んでいますが、初心者の方からよくいただくのが「どんなライトを買えばいいの?」というご相談です。
実は、照明ひとつで動画や商品の見え方は劇的に変わります。暗くて地味だった映像も、適切なライトを使うだけでプロっぽい仕上がりに。
今回は、これから動画撮影やネットショップ用の商品撮影を始めたい方に向けて、撮影用ライトの基礎知識と選び方、そして2025年現在人気の機種まで、最新情報を交えて徹底解説します!
テクニックも交えつつ、わかりやすく紹介していきますので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

2025.06.22
本記事では、学割付きパッケージを提供する代表的な 3 校 アドバンスクールオンライン・たのまな・デジハリ ONLINE を 価格・講座内容・サポート体制の3視点で徹底比較。 「買うならどこが自分に合う?」「動画講座の質は?」「質問サポートの違いは?」 ──そんな疑問を、早見表...
目次
撮影用ライトの種類と特徴
撮影で使われるライトにはいくつかの種類があります。それぞれ形や光の性質が異なり、用途に合わせて選ぶことで映像や写真の仕上がりがグッと良くなります。ここでは代表的な3タイプをご紹介します。
定常光ライト(ビデオライト)
定常光ライトとは、スイッチを入れた瞬間から常に一定の光を発する照明のことです。カメラのフラッシュとは異なり、動画撮影や商品撮影など、リアルタイムで光の当たり方を確認したい場面に最適です。
2025年現在、主流はLEDタイプで、特にCOB(チップオンボード)型の大光量LEDが普及し、小型でもスタジオ並みの明るさを得られるようになりました。明るさや色温度(光の色味)を細かく調整できるモデルが増えており、初心者にも扱いやすいです。
撮影現場では「キーライト(主光源)」としてよく使われ、GodoxやNeewer、YONGNUO、Ulanziなど多数メーカーからラインナップが出ています。ファンノイズを抑えた静音モデルや、Vマウントバッテリー対応など携帯性に優れた製品も要注目です。
リングライト
その名の通り、リング状にLEDが並んだ照明で、真ん中にカメラやスマホをセットして撮影できるようになっています。顔に均等に光が当たるため、美肌効果があり、メイク動画やライブ配信、ポートレート撮影にぴったりです。
背景に影が出にくく、キャッチライト(目の中に写る光)も丸く自然になるため、人物撮影に最適。卓上タイプから大きめのスタンドタイプまでバリエーションも豊富で、設置が簡単なのも魅力です。
最近はNeewer製の18インチLEDリングライトや、Ulanziなどの新興メーカー製品も高演色のLEDを採用し、さらにクオリティが上がっています。
ソフトボックス
スタジオ撮影などでよく使われるのがソフトボックス型ライトです。内部のライトの前にディフューザー(白い布)を装着することで、柔らかく拡散した光を作り出します。
商品撮影や人物撮影などで「自然な陰影」や「なめらかな肌質感」を出したいときに重宝されます。しっかりした印象の写真・映像を撮りたい方は導入を検討すると良いでしょう。
近年はワンタッチで組み立て可能な折りたたみ式や、空気で膨らませるインフレータブル型など、携帯性に優れたモデルも登場しています。
撮影用ライトの選び方:6つの重要ポイント
ライト選びに失敗すると、せっかくの撮影が「暗い」「色味が変」「ノイズが出る」など、がっかりな結果に…。ここでは、プロの現場でも重視されている6つのチェックポイントを紹介します。初心者の方でも、これさえ押さえておけば間違いありません!
1. 光源の種類:LEDを選ぶ
現在、撮影用ライトの主流はLEDライト。白熱灯や蛍光灯に比べて圧倒的に省エネ・長寿命・低発熱です。最近は大光量のCOB型や、RGB対応モデルも増えているので、用途に合わせて選択すると良いでしょう。
屋外や出張撮影が多い方はバッテリー駆動対応かも要チェック。例えばUlanziのVL-200Biなどは200W級でもVマウントバッテリーで運用可能です。
2. 明るさ(照度)
ライトの明るさは「ルーメン(lm)」や「ルクス(lux)」で表されます。用途によって必要な光量は異なりますが、1m距離で1,000~2,000lux以上あれば汎用性は高め。
ソフトボックスをつけると光量が落ちるので、ある程度パワーに余裕があるライトを選ぶのがおすすめ。調光機能(1~100%)があれば、シーンに合わせた細かい設定が可能です。
3. 色温度と演色性
撮影ライトの色味は「色温度(ケルビン/K)」で表され、3,200K(電球色)~5,500K(自然光)前後で調整可能なバイカラー型が一般的。
また、CRI(演色評価指数)が90以上、できれば95以上だと、被写体本来の色をより正確に再現できます。人物や商品を撮るなら重視したいポイントです。
4. 電源の種類
AC電源式とバッテリー式の2タイプがあり、スタジオ常設ならコンセント給電でOK。ロケやイベントで使うならバッテリー運用が便利です。
VマウントやNP-Fバッテリー、USB-Cなど、メーカーによって対応がさまざまなので、撮影スタイルに合うか確認しましょう。
5. 静音性
動画撮影では、ライトのファン音が「ブーン」と録音されてしまうケースがあります。特にインタビューや商品説明では注意が必要。
ファンレスや、ファン音が極力抑えられた静音モデルを選ぶと安心です。大光量モデルではファンが必須な場合が多いので、レビューをチェックしておきましょう。
6. 価格とサポート
最後は予算です。近年は安価なモデルでも性能が上がっているので、NeewerやYONGNUO、Ulanziなどのエントリーブランドはコスパ◎。
一方で大型・高出力機種はそれなりの価格になります。万一の不具合に対応してもらえるか、保証やアフターサービス面も選ぶポイントです。
おすすめの撮影用ライト:人気メーカー別
ここからは、初心者〜中級者にも人気のある実力派メーカー3社に加え、ワンランク上のブランドまで幅広くご紹介します。いずれもAmazonや楽天などで入手しやすく、コスパと機能性のバランスが取れたブランドです。
Neewer(ニューワー)
撮影用ライトといえば、まず名前が挙がるのがNeewer(ニューワー)。中国発のブランドですが、品質の高さと手頃な価格帯で、世界中のクリエイターに支持されています。
特徴:
- LEDパネル、リングライト、ソフトボックス、COB型まで幅広く展開
- 明るさ・色温度ともに調整できるバイカラー設計が多い
- 三脚やキャリーバッグ付きのセット商品が充実
代表モデル:
「Neewer 660 LEDビデオライト」や「RL-18 リングライトキット」は定番。
最新のCOBライト「CB200B/CB300B」は高演色・大光量ながらコスパが良いと話題です。
Ulanzi(ウランジ)
Ulanzi(ウランジ)はミニマルで機能的なガジェットを得意とするメーカー。特にYouTuberやVlogger、ガジェット好きな映像制作者にファンが多いブランドです。
特徴:
- ポケットサイズの高輝度LEDやRGBライトなど個性的な製品が多数
- 磁石・シューアダプターなど、固定しやすい設計
- バッテリー内蔵・USB-C充電タイプが多く、屋外でも使いやすい
代表モデル:
「VL49」は小型で持ち運びやすく、価格も数千円でコスパ良し。
「VL-200Bi」は200W出力・Vマウントバッテリー対応の本格ライトで、ロケ撮影や商品撮影にも対応できると注目を集めています。
YONGNUO(ヨンヌオ)
YONGNUO(ヨンヌオ)は中華系フラッシュ・LEDメーカーとして長年の実績があるブランド。カメラ用ストロボで有名ですが、LEDライトの分野でも高機能な製品を多数展開しています。
特徴:
- 色温度や明るさの細かい調整が可能(バイカラー/RGB対応)
- アプリ操作ができるモデルもあり、リモート撮影に便利
- COBタイプからパネル型、スティック型までバリエーション豊富
代表モデル:
「YN600 LEDビデオライト」は安定の定番。
「YNLUX 300RGB」は300WのRGB COBライトでCRI96以上と高演色。
「YN360IV」スティック型はRGBフルカラー+白色LEDで多彩な演出が楽しめます。
Aputure(アプチャー) / Amaran(アマラン)
よりハイエンド〜中上級向けの機材も視野に入れるなら、Aputure(アプチャー)と、そのサブブランドであるAmaran(アマラン)も押さえておきたいところ。映画やCM撮影の現場でもよく見かける本格派ブランドです。
特徴:
- Aputureはシネマ向け高出力ライトが中心で、演色性や耐久性、機能性もトップクラス
- AmaranはAputureの手頃なラインで、100〜200WクラスのCOBライトを中心に展開
- 専用アプリやアクセサリー展開も充実しており、照明コントロールがしやすい
代表モデル:
Aputureの「LSシリーズ」は映画向けのハイエンド機材。
「Amaran 100X/200X」はバイカラー対応で、プロ品質ながら比較的手頃。
最新の「Amaran 150C」「Amaran 300C」はRGBWW対応で、多彩なカラー演出が可能です。
価格帯はやや高めですが、「妥協せず長く使いたい」「本格的な映像制作を目指したい」という中級〜上級者には非常におすすめのブランドです。
撮影用ライトの使い方:実践テクニック
ライトは「買って終わり」ではありません。どう使うかで撮影のクオリティは大きく変わります。 ここでは、映像制作の現場でも使われている照明テクニックを、初心者にもわかりやすくご紹介します。
3点照明(スリー・ポイント・ライティング)
撮影現場で最も基本となるのが3点照明。人物や商品を立体的に見せるための構成です。
- キーライト:主光源。正面や斜めから、対象に一番強く当てる光。
- フィルライト:補助光。影を和らげるために反対側から当てる弱めの光。
- バックライト(リムライト):被写体の後ろから当てて輪郭を際立たせる光。
この3つをバランスよく配置することで、プロっぽい立体感が生まれます。最初はキーライト+フィルライトの2灯でもOKです。
バウンス(反射光)
「光が強すぎる」「影がきつい」…そんな時は、光を壁や白いレフ板に反射させる“バウンス”がおすすめです。
ライトを直接被写体に当てず、壁や天井に向けて光を拡散させることで、やわらかく自然な光が得られます。特に人物や料理撮影では、肌や素材の質感がぐっと良くなるでしょう。
色温度調整で「雰囲気」をつくる
色温度(ケルビン/K)を調整できるライトを使えば、シーンに合わせた雰囲気作りが可能です。
- 白くクリーンに撮りたい → 5,500K前後の昼白色
- 温かみのある雰囲気 → 3,200K前後の電球色
さらに近年はRGBライトも充実しているので、カラー演出で個性的な映像表現が可能。撮影テーマに合わせて、ぜひ試してみてください。
まとめ:最適な撮影用ライトでクオリティアップ
撮影用ライトは、動画や商品写真の印象を左右する“影の主役”です。カメラやレンズと同じくらい、いやそれ以上に「光」は撮影クオリティに直結します。
2025年現在はLED技術の進化によって、明るさ・演色性・静音性などが大きく向上し、バッテリー駆動やアプリ制御、RGB対応といった機能も充実しています。今回ご紹介したように、「種類」「明るさ」「色温度」「静音性」などのポイントを押さえたうえで最適な機材を選び、効果的な配置・バウンス・色温度の活用などのテクニックを取り入れるだけで、映像や写真のクオリティは見違えるほど変わります。
「ちょっと暗いな」「何か安っぽいな」と感じたら、まずはライトを変えてみるのがおすすめ。ほんの少しの投資と工夫で、グッとプロっぽい見映えが手に入るはずです。
ぜひ、自分に合った1台を見つけて、撮影をもっと楽しく、もっと美しくしていきましょう!

2025.06.22
本記事では、学割付きパッケージを提供する代表的な 3 校 アドバンスクールオンライン・たのまな・デジハリ ONLINE を 価格・講座内容・サポート体制の3視点で徹底比較。 「買うならどこが自分に合う?」「動画講座の質は?」「質問サポートの違いは?」 ──そんな疑問を、早見表...

2025.03.30
この記事では、初心者の方が自宅でナレーション録音を始めるためのマイク選びについて、プロの収録現場を見てきた私の視点から、できるだけわかりやすく、親しみやすくまとめてみました。 「できればプロっぽい音質で録りたい!」「でもあまり予算はかけられない…」そんな方に向けて、種類別のおすすめマイクを...
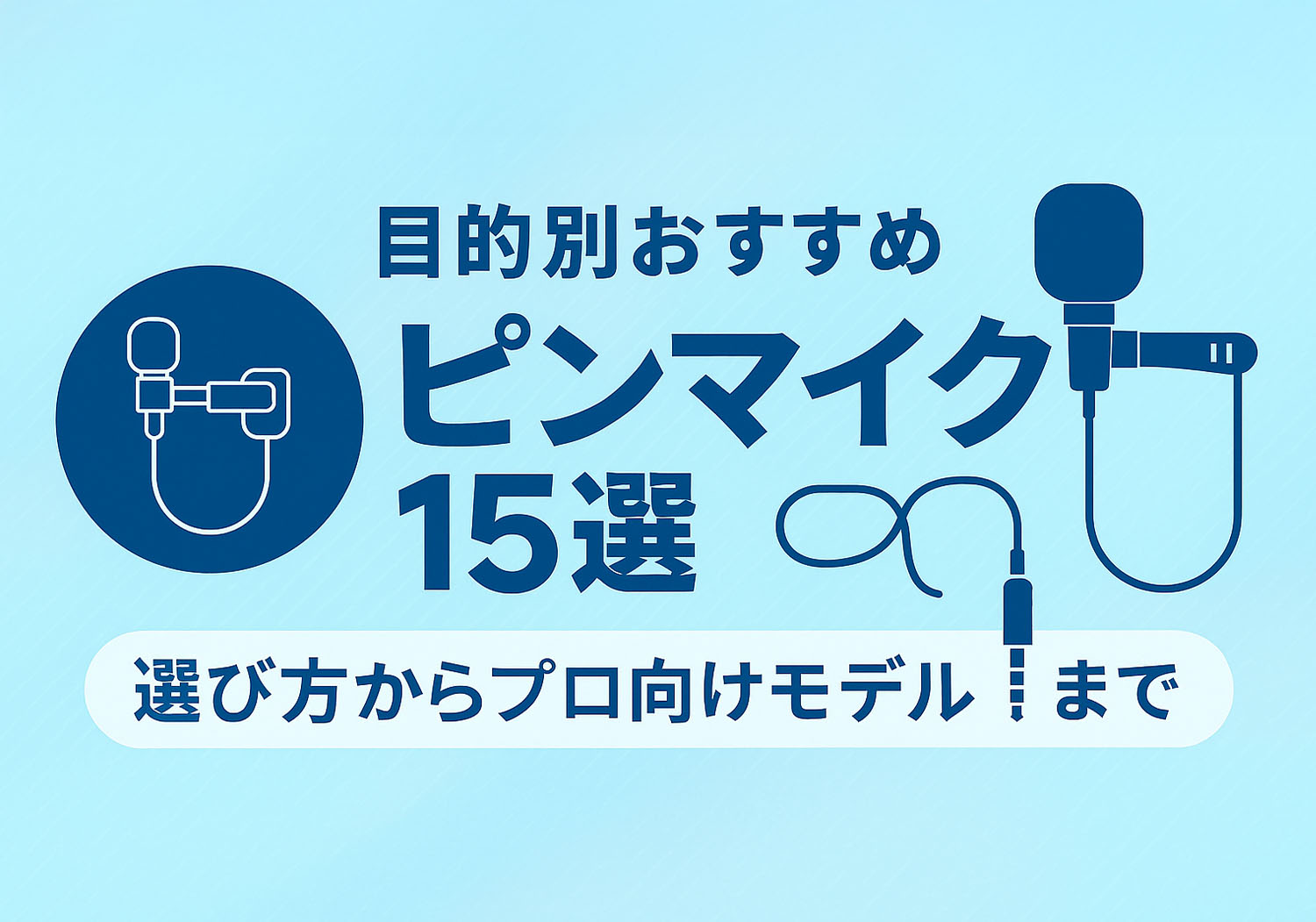
2025.05.25
せっかく映像がうまく撮れていても、音が悪いと、全体の印象がガクッと下がる。 そんな経験、私たちの現場でも何度もしてきました。 そこで役に立つのが、小さくても信頼できる相棒「ピンマイク(ラベリアマイク)」です。 胸元などに装着して使えるピンマイクは、声をダイレクトに拾い、雑音を抑え、...

2025.02.07
HOLLYLAND LARK M2Sとは? まず、HOLLYLANDといえば 映像・音響機器のプロフェッショナルブランド であり、特にワイヤレスシステムに強みを持っています。 トビガスマルでは、映像制作・ライブ配信の現場で HOLLYLAND製品 を積極的に導入しています。 ...

2025.03.03
圧倒的な転送速度と驚くほど安定した持続性能に加え、現場視点の細かな使い勝手が際立つ本製品は、映像制作のワークフローを一新する可能性を秘めています。今回は実際の使用感も交えながら「PG10 Pro」の魅力を徹底解説します。 映像制作の現場にSSDが必要な理由 近年、4Kや8Kといっ...



コメント