
こんにちは、合同会社トビガスマル代表社員の廣瀬です。近年注目を集めている「TikTokライブコマース」は、スマホひとつで手軽にライブ配信しながら商品を販売できる新しい手法です。視聴者とリアルタイムで交流しつつ購買意欲を高められるため、大企業のみならず中小企業にとっても大きなチャンスといえます。
しかし、「具体的にどう始めればいいの?」「事前準備やデメリットは?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、TikTokライブコマースの基本からメリット・デメリット、さらに成功のコツや事例まで徹底解説します。
目次
TikTokライブコマースとは?
ライブコマースの基本
ライブコマースとは、ライブ配信を通じて消費者とコミュニケーションを取りながら商品を販売する新しいオンライン販売手法です。リアルタイムで商品の紹介やデモンストレーションを行い、視聴者からの反応や質問にその場で答えることで、まるで実店舗で接客しているかのような臨場感ある体験を提供できます。
視聴者は商品について不安や疑問があれば即座に質問でき、納得してから購入に進めるため、「見てすぐ買える」スムーズな購買体験が可能です。
文字や写真だけでは伝わりにくい商品の質感や使用感、作り手の想いもライブ動画ならリアルタイムに伝えやすく、単に商品を売るだけでなく体験そのものを提供できる点が大きな特徴です。
TikTokが注目される理由
数あるプラットフォームの中でも、なぜTikTokがライブコマースで注目を集めているのでしょうか。その理由の一つは、利用者層と拡散力にあります。TikTokは日本国内でも若年層を中心に圧倒的なユーザー数を誇り、人気インフルエンサーも多く活躍しています。彼らの影響力を活用したライブ配信は視聴者からの信頼を得やすく、商品の購入につながりやすいと言われます。また、TikTokのアルゴリズムによる拡散力は非常に高く、リアルタイムのライブ配信が話題になれば一気に多くの潜在顧客にリーチできる点も魅力です。
さらに技術面でもTikTokはライブコマース対応の進化が期待されています。「カード機能」と呼ばれる、ライブ配信中に直接商品購入ページへのリンクを表示できる機能を2025年に実装するとの噂があり、実現すればライブ配信から離脱せずにその場で商品の購入手続きが可能になります。加えて、「TikTok Shop(小黄車)」というライブ配信中に直接商品を購入できる新機能も日本で導入される可能性が報じられており、中国では既にこの機能でライブコマースが大成功を収めています。こうした機能が搭載されれば、ライブ視聴から購入までの導線が短縮されユーザー体験が飛躍的に向上し、企業側としても高いコンバージョン(購買転換率)を期待できます。
そして参入のハードルの低さも見逃せません。ライブコマースはスマホ一つとネット環境さえあれば始められるため初期投資が比較的少なく、中小企業や個人ブランドでも参入しやすい土壌があります。実店舗を構えるほどの資金が無くても、TikTok上であれば手軽に自社商品のPR・販売が可能です。以上のように、「若者に人気のプラットフォームであること」「新機能による購買体験の最適化」「低コストで始められる」といった点からTikTokはライブコマースの舞台として大きな注目を集めています。
SharingLiveの活用
ライブコマースを自社で始めるにあたり、「何から手を付ければ良いか分からない」「配信のノウハウがない」と不安に感じる中小企業の方も多いでしょう。
そこで心強い味方となるのが、ライブコマース支援サービスの「SharingLive(シェアリングライブ)」です。SharingLiveは株式会社クリップスが提供するライブコマースに特化したプラットフォームで、スマホアプリ(iOS/Android)として利用できます。ライブコマース専門のサービスであるため、ライバー(配信者)のキャスティングから企画立案、撮影、配信運営、さらには配信後のデータ分析や改善提案に至るまでトータルでサポートしてくれるのが強みです。自社にノウハウがなくても、SharingLiveを活用すればプロの手でライブコマースの仕組みを導入でき、初めての企業でも安心してライブ販売に挑戦できます。
またSharingLiveではライバーの育成事業も行っており、エンターテインメント性の高い配信ができる人材を発掘・育成しています。そのため「商品の魅力をどう映像で伝えるか」「視聴者を飽きさせないトーク術」など、ライブ配信の質そのものを高める支援が受けられる点もメリットです。実際、SharingLiveは2024年12月にTikTok LIVEの公式提携エージェンシーにも参画しており、TikTok上でライブコマース事業を展開したい企業に向けたサポート体制も強化されています。以上のようにSharingLiveを上手く活用すれば、企画から配信運営までワンストップで支援を受けられるため、中小企業でも効率よくライブコマースを導入できるでしょう。
TikTokライブコマースのメリットとデメリット
メリット:手軽さと高エンゲージメント
1. 手軽に始められる:
TikTokライブコマース最大の利点は、その手軽さです。特別な機材や大掛かりな準備がなくても、スマートフォン一台で誰でも簡単にライブ配信を始められます。InstagramやYouTubeといった他SNSのライブ配信と同様、プラットフォーム上の機能を無料で使って気軽に配信を始められるため、コストをかけずに新しい販売チャネルを開拓できるのは中小企業にとって大きな魅力です。既存のTikTokアカウントさえあればすぐにライブ配信を試せるので、新商品のプロモーションや在庫一掃セールなども思い立った時にスピーディーに実行できます。
2. 顧客とのエンゲージメントが高い:
ライブ配信では視聴者とのリアルタイムなコミュニケーションが可能なため、文字や画像中心のEC販売に比べ圧倒的にエンゲージメントが高まります。視聴者はチャット機能でコメントや質問を投げかけ、それに配信者(企業側)がその場で回答したりデモを見せたりできるので、双方向のやりとりを通じて信頼関係を構築しやすいのです。
視聴者の疑問点をすぐ解消できるため購買への心理的ハードルも下がります。加えて「○○さんがハートを送りました」「残り○点です!」といったライブならではの演出や緊張感が購買意欲を刺激し、視聴者参加型のショッピング体験によって商品への共感や欲しい気持ちを高める効果があります。結果として、ライブ配信を通じた商品の購入率は従来のECより高くなる傾向も報告されています。
3. プラットフォーム連携と拡張性:
TikTokは他のECプラットフォームとの連携にも積極的です。特にShopify(ショッピファイ)との公式連携は、中小企業にとって大きな追い風でしょう。Shopifyは世界中で利用されているECサイト構築プラットフォームですが、TikTokと連携することでShopify上の商品カタログを活用した動画広告を簡単に作成できたり、TikTok経由の販売データをShopify側で一元管理できたりします。具体的には、Shopifyの管理画面内にTikTok連携用のアプリを導入し、商品情報を同期させることで、TikTok動画内に「購入する」ボタンを表示したり、広告キャンペーンを実施したりすることが可能です。このような連携機能を使えば、ライブ配信中に紹介した商品について視聴者が購入ボタンをクリックすると、自社のShopifyストアでスムーズに決済・注文できるため、ライブコマースの成果を自社EC売上に直結させやすくなります。
デメリット:炎上リスクと機能面の制約
もちろんメリットばかりではなく、注意すべきデメリットやリスクも存在します。
1. 炎上リスク・配信管理の難しさ:
TikTokは拡散力が高い反面、不適切な発言やトラブルが起きた際に一気に批判が広まりやすい側面もあります。ライブは生放送ゆえに配信者の言動やハプニングを後から編集で消すことができません。視聴者とのやり取りで予期せぬ質問やクレームが出てくる可能性もあります。対応を誤るとそのままコメント欄で炎上してしまい、ブランドイメージを損ねるリスクがあることは心得ておかなければなりません。特に若年層が多いTikTokでは、些細なことがきっかけでネガティブな反応が増幅されることもあるため、配信前にシナリオを用意する・ガイドラインを設ける・不適切なコメントは非表示にするなどの対策が必要です。また、配信者自身の教育も重要で、商品の知識はもちろん発言や振る舞いに十分注意を払うよう訓練しておくことが望ましいでしょう。
2. 機能上の制約:
現時点(2025年初頭)において、TikTokライブには他プラットフォームと比べていくつか機能的な制約があります。まずライブ配信のアーカイブ(録画保存)機能がないことです。InstagramやYouTubeではライブ後に動画を保存しておき、後から見逃し視聴できる場合がありますが、TikTokでは公式にはライブ配信を後から視聴する方法が提供されていません。そのためライブに参加できなかった潜在顧客にはリーチできず、せっかく時間をかけた配信も一度きりの機会になってしまいます。次にライブコマース専用の購入機能が未整備な点も挙げられます。TikTokには現状、配信中に直接決済まで完結する「ライブショッピング」機能が日本では実装されておらず、商品を販売するには外部のECサイトへ誘導する必要があります。視聴者は購入の際にライブ配信から離れて通販サイトに移動しなければならず、その間に配信内容を聞き逃したり視聴をやめてしまったりするリスクがあります。このように購入フローが分断されることによる離脱はライブコマース全般の課題です。
とはいえ、この購入導線の問題は前述のShopify連携や今後導入予定のTikTok Shopによって徐々に解消される見込みです。既に2021年からTikTokはShopifyとの提携を開始しており、日本でもShopify経由でTikTokに商品情報を連携したり広告出稿したりできる仕組みが整っています。さらに将来的にTikTokアプリ内でそのまま決済まで完了できるようになれば(TikTok Shopの本格導入)、ライブ配信から購入までシームレスにつながり、視聴者の利便性は飛躍的に向上するでしょう。中小企業にとっては現状でも「ライブ配信で商品に興味を持ってもらい、Shopify等の自社ECで購入してもらう」という流れで十分成果を上げることは可能です。今後の機能拡充にも期待しつつ、現時点ではこうした連携機能を上手に活用してデメリットを補完する戦略が重要です。
TikTokライブコマース成功のポイント
それでは、実際にTikTokライブコマースで成果を出すためには具体的にどのような点に気をつければ良いのでしょうか。ここでは配信内容の工夫、トレンド活用、継続的な発信とプロモーションの観点から成功の秘訣を解説します。
動画制作と配信内容の工夫
・押し売りではなくストーリー性を重視:
TikTokの主要ユーザーである10〜20代は、あからさまな「〇〇を買ってください!」という宣伝を嫌う傾向にあります。そのためライブ配信でも売り込み色の強いトークより、商品を実際に使った感想やエピソードを交えたストーリーテリングを意識しましょう。例えば「この商品を使ってみたら本当に驚きました!」「うちのスタッフも手放せない一品なんです」といった実体験に基づく話を盛り込むことで、視聴者の共感を得やすくなります。同じ目線・世代の配信者がリアルな感想を語ることで、「自分にも合いそうだ」と興味を引き、結果的に購買につながりやすくなるのです。
・デモンストレーションと見せ方の工夫:
ライブ配信では映像を駆使できる強みを最大限活かしましょう。商品を実際に使ってみせるデモンストレーションはもちろん、使い方のビフォーアフター比較、商品を様々な角度から映す、着用モデルの全身を見せてサイズ感を伝える、といった工夫が有効です。視聴者が「自分が使うイメージ」を持てるような見せ方を心がけてください。またTikTokならではの機能として、コメントでアンケートを取ったりエフェクトやBGMを活用したりすることでエンタメ性を高めるのも手です。例えば「どの色が好きですか?コメントで教えてください!」と呼びかけたり、商品の雰囲気に合った音楽をBGMに流したりすると、ライブ全体が盛り上がり視聴者の滞在時間も延びやすくなります(TikTokでは商用利用可能な音源が用意されているので安心です)。映像のクオリティ面では、照明やカメラアングルにも気を配り、明るく鮮明で見やすい画面を意識しましょう。スマホ用のリングライトやスタンドを用意するだけでも映り方が格段に良くなります。
トレンドハッシュタグの活用
TikTokにはトレンドページと呼ばれる、その時々で話題になっているハッシュタグや楽曲を一覧できる機能があります。
人気のトレンドハッシュタグは多くのユーザーが関心を寄せているテーマであり、これを上手に活用することで動画の閲覧数やフォロワー数を飛躍的に伸ばせる可能性があります。ライブコマースにおいても、配信タイトルや事前告知の投稿にトレンドハッシュタグを取り入れることで新規視聴者の目に留まりやすくなるでしょう。たとえば、季節のイベント(#ハロウィン, #クリスマス など)や話題の現象(#○○チャレンジ など)に関連付けて商品を紹介できるなら、そうしたタグを付けて露出を増やす戦略が考えられます。
ただし注意点として、商品の内容と無関係なハッシュタグを無理に付けるのは逆効果です。人気だからといって関係のないタグを付ければ、一時的に人目には触れても視聴者を騙すことになりブランドの印象を悪化させてしまいます。あくまで自社商品の特性やターゲットにマッチし、視聴者にも有益となるタグを選ぶようにしましょう。例えばアパレル商品であればファッショントレンドのハッシュタグ、食品であればレシピ系ハッシュタグ、といった具合です。また、TikTok上で自社独自のハッシュタグキャンペーンを展開するのも有効です。視聴者にハッシュタグ投稿を呼びかけてUGC(ユーザー生成コンテンツ)を促進すれば、ライブ配信後も継続的に話題を喚起することができます。
継続的な配信と効果的なプロモーション
・定期配信でファンを増やす:
ライブコマース成功のカギは継続力にあります。一度配信しただけで終わりではなく、週○回など定期的にライブ配信を行いましょう。フォロワーを増やすには、長期的にコンスタントに情報発信を続けることが重要です。
人々の記憶には「たまに現れるアカウント」より「継続的によく見るアカウント」の方が残りやすいものです。決まった曜日や時間に配信を行えば視聴者も予定を立てやすく、「次回はいつやるのかな」と待っていてくれる常連ファンが育ちます。例えば「毎週水曜夜8時はライブコマースDAY」のように習慣化できれば理想的です。継続する中で、「どんな内容なら反応が良いか」「視聴者層はどんな属性か」などのデータも蓄積されていきます。配信回数が増えるほど傾向分析が可能になり、次第に自社にとって最適なライブコンテンツの形が見えてくるでしょう。最初は色々な企画に挑戦し、回ごとの反応を比較しながら試行錯誤する姿勢も大切です。
・事前告知と集客施策:
配信を定期化するだけでなく、一回一回のライブをしっかり盛り上げるために事前のプロモーションにも力を入れましょう。TikTok上ではライブ配信予定を告知する機能(※現在はプロフィールや投稿動画での告知が中心)があるので、新しい投稿動画で「◯月◯日△時からライブ開催!○○を初公開します」と案内したり、ストーリーズ(TikTokではストーリー機能)でリマインドするのも有効です。既存フォロワー以外にもリーチするには、TwitterやInstagramなど他のSNSで告知したり、自社のウェブサイトやメルマガで案内したりするとよいでしょう。「ライブ配信中だけ使える割引クーポン配布」や「視聴者限定プレゼント企画」を用意しておくと告知内容にインパクトが出て、参加を促しやすくなります。実際、大手企業ではライブ視聴者だけに特典クーポンを発行して購買意欲を高めた例もあります。
・インフルエンサーとのコラボ:
自社だけで集客が難しい場合や、新規フォロワー獲得を加速させたい場合は、TikToker(ティックトッカー)と呼ばれる人気クリエイターに協力を依頼する方法も検討しましょう。
TikTokで活躍するインフルエンサーに商品PRを依頼する企業は増えており、100万フォロワー超のTikTokerがプロモーションに起用されるケースもあります。自社商品と親和性の高いジャンルで影響力を持つTikTokerがいれば、ライブ配信にゲスト出演してもらったり、商品紹介動画を投稿してもらうことで一気に認知拡大が見込めます。例えばコスメならメイク系クリエイター、食品なら料理系TikTokerといった具合に、ターゲット層にリーチできる人物を選ぶことがポイントです。依頼する際は直接交渉も可能ですが、著名なTikTokerであれば事務所を通すとスムーズでしょう。コラボ配信ではそのインフルエンサーのファンも視聴者として流入してくれるため、自社アカウントのフォロワー獲得にもつながります。 以上のようなポイントを押さえ、「継続×工夫×プロモーション」をバランス良く実践していくことで、TikTokライブコマースの成功率はぐっと高まります。最初から完璧を目指す必要はありません。小さく始めてPDCAを回しながら改善を重ね、自社ならではのライブコマーススタイルを築いていきましょう。
企業事例:TikTok活用事例
ここでは、ライブコマースに取り組み成果を上げている企業の事例をいくつかご紹介します。大企業の例ではありますが、中小企業にも参考になる工夫が多く含まれています。それぞれのケースから、自社で活かせるポイントを探ってみましょう。
Mark Styler(アパレルEC)
ファッションブランドのEC運営で知られるMark Styler(マーークスタイラー)は、自社ECサイト上でライブコマースを実施しています。同社のライブ配信の特徴は、出演モデルの身長を冒頭で紹介している点です。視聴者はモデルの身長情報を基に、画面に映る服のサイズ感を自分の場合に当てはめて想像しやすく、「自分が着るとどんな丈感だろう?」といった疑問がすぐ解消されます。また配信中はショップ店員が商品を着用しながら説明し、コメント欄で視聴者からの「○○cmだとMサイズで大丈夫?」といった質問にも気軽に答えてくれます。店舗で店員と会話しているような感覚が得られるため、視聴者にとって安心感があり購買意欲を後押ししています。ライブ配信を通じてお気に入りのスタッフができたお客様も多く、スタッフ個人のファン化にもつながっています。このようにサイズ感の共有やスタッフとの交流といった工夫は、中小のアパレル企業でも取り入れやすいポイントです。自社スタッフをモデルに起用し、お客様とコミュニケーションを図りながら商品の魅力を伝えることで、EC上でもリアル店舗さながらの接客効果が期待できます。
資生堂(コスメ)
大手化粧品メーカーの資生堂もライブコマースの成功事例として知られています。同社はコロナ禍で対面販売が難しい状況下、ライブ配信を活用して非接触での商品提案に取り組みました。資生堂のライブ配信では美容の専門家(ビューティーコンサルタント)が出演し、スキンケアやメイクの方法をレクチャーしながら自社コスメを紹介しています。視聴者から「肌荒れが気になる」「自分に合う色はどれ?」といった悩み相談のコメントが寄せられると、その場で専門家が回答し、最適な商品のアドバイスを行いました。プロならではの知識提供に視聴者は惹き込まれ、リアルタイムで悩みを解決してもらえる体験に満足度も高く、配信は好評を博しました。またライブ視聴者限定でサンプルプレゼントや割引クーポンを提供するなど特典を用意し、購買への後押しも行っています。この事例から学べるのは、専門知識や付加価値情報の提供です。中小企業でも、自社商品に関連する分野で豊富な知識を持つスタッフや講師を起用すれば、視聴者に「ためになる話」を届けつつ商品PRができます。例えば食品メーカーなら栄養士、DIYグッズなら職人さん、といったように、その道のプロ視点で商品を語ってもらうことで信頼感を醸成し、商品への関心を高めることができるでしょう。
ワッツ(100円ショップ)
100円均一ショップを全国展開するワッツは、実店舗とライブコマースを上手く連動させた取り組みで注目されました。オンラインショップで人気の商品やSDGs(持続可能な開発目標)関連の商品をピックアップしてライブ配信し、画面上に「店舗在庫検索」のボタン(アイコン)を表示したのです。視聴者はライブで気になった商品があればそのボタンをタップすることで、自分の近くの店舗で在庫があるかすぐに調べることができ、気に入ったらそのまま最寄り店舗で購入できるよう導線を工夫しました。通販だけでなく店舗への送客まで考慮したこの仕掛けはユニークで、「近所の店舗にあるなら買いに行こうかな」と視聴者に思わせる効果を生んでいます。また配信中は視聴者からのコメントに店員が返信したり、「いいね」連打にリアクションしたりと双方向のコミュニケーションも積極的に行い、オンライン上でも顧客との距離を縮めています。この事例からは、ライブコマースをオンライン完結にせずオフラインとも連携させる戦略が学べます。中小の小売店でも、自社EC在庫だけでなく店舗在庫を案内したり、「明日から店舗セールをやります」とライブで告知したりすることで、ネットと実店舗の相乗効果を狙うことができます。地域密着型のお店ほど、ライブ配信を新たな地元顧客づくりの場として活用する価値は大きいでしょう。
コジマ(ペットショップ)
ペット用品店のコジマ(※家電量販のコジマではなくペットショップ運営企業)は、商品そのものだけでなく関連するサービスの訴求にもライブコマースを役立てています。コジマでは看板施策としてプロのドッグトレーナーによる「しつけ教室」を店舗で開催していますが、これをオンラインに拡張し、ペットのしつけ方やお悩み相談をテーマにしたライブ配信を実施しました。配信ではカリスマドッグトレーナーが出演し、噛み癖や無駄吠えなど視聴者のペットの悩みに答えながら、しつけのコツをライブで実演してみせました。視聴者から寄せられるコメント質問にも丁寧に返答しつつ、適宜おすすめのしつけ用グッズ(おやつ、ケージ、しつけ本など)も紹介。専門家のアドバイスと商品提案が違和感なく融合した内容となりました。さらに配信画面上からコジマの「しつけ教室」予約ページに直接アクセスできる仕組みも用意し、ライブ視聴者がそのまま店舗サービスの予約申し込みまで完了できるようにしました。この結果、ライブ配信は商品の売上貢献だけでなく実店舗でのサービス集客にもつながっています。中小企業でも、自社商品に関連するノウハウやサービスがあれば、それを絡めたライブ配信は有効な戦略です。例えばスポーツ用品店ならトレーニング指導のライブ、楽器店なら音楽レッスン配信、といったように「教える×商品紹介」の形式にすれば視聴者の学びと購買ニーズを同時に満たすことができます。コジマの例は、ライブコマースの枠を超えて包括的な顧客体験の提供**につなげた好例と言えるでしょう。
まとめ:TikTokライブコマースの可能性
いかがでしたでしょうか。TikTokライブコマースの基本からメリット・デメリット、成功のポイントや企業事例まで一通り解説しました。中小企業の経営者の皆様にとっても、TikTokライブコマースは決してハードルが高いものではなく、むしろビジネス拡大の新たなチャンスとなり得ることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
初期費用が少なく参入しやすいライブコマースは、中小企業にこそ相性の良い販売チャネルです。実際、従来の広告手法に比べてライブコマースは直接購買につながりやすく、広告費あたりの効果(ROI)が高まる可能性があるとも言われています。うまく軌道に乗せれば、少ない予算で効率よく売上アップやファン獲得を実現できるでしょう。 現在日本ではライブコマース市場は発展途上ですが、海外(特に中国)では既にECの主流になりつつあり、日本でもこれから大きく普及することが見込まれます。2025年にはTikTok上でショッピング機能が本格化するとの見通しもあり、市場が一気に拡大する可能性があります。ライブコマースは決して一時的なブームではなく、ECの未来を担う存在になりつつあります。今後、消費者の購買行動がライブコマース前提にシフトしていくことも十分考えられます。
だからこそ、ぜひ早い段階でこの波に乗ってみてください。最初は視聴者が数人でも気にする必要はありません。継続し工夫を凝らすことで必ず手応えが出てきますし、小さな成功体験の積み重ねがやがて大きな成果につながります。必要であればSharingLiveのような専門サービスの力も借りつつ、自社に合った形でTikTokライブコマースを取り入れてみましょう。ライブ配信を通じてお客様と直接つながれる喜びは、きっと従来の販促では得られなかった新しい発見をもたらしてくれるはずです。リアルとネットの境界を超えたエンゲージメントで、中小企業ならではのファンづくり・ブランドづくりを実現し、ぜひ御社のビジネスを次のステージへと押し上げてください。ライブコマースの可能性は無限大です。恐れず挑戦し、その恩恵を存分に享受していきましょう。

2025.02.26
カテゴリー1|YouTubeチャンネル運用・集客の基本 YouTubeマーケティングに特化した基礎知識や、チャンネルの作り方・初期設定、効果的に集客するための基本戦略などを扱う記事。これからYouTubeを活用したい方、基礎から学びたい方向け。 【初心者向け】YouTubeのチャンネ...
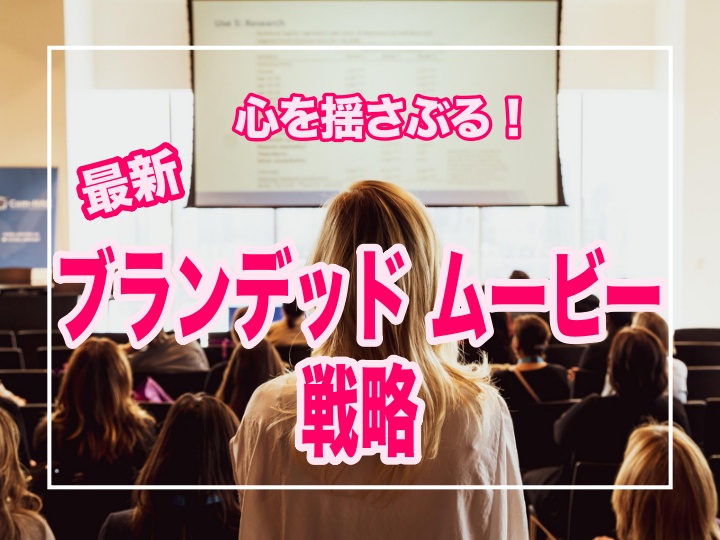
2025.02.26
本記事では、ブランデッドムービーの定義や特徴、動画広告との違い、制作のメリット・デメリット、そして成功事例や効果測定の方法、今後の展望までを詳しく解説します。企業のマーケティング担当者やブランド戦略担当者の皆様が、自社のブランディングに最適な映像戦略を見出す一助となれば幸いです。 ブラ...


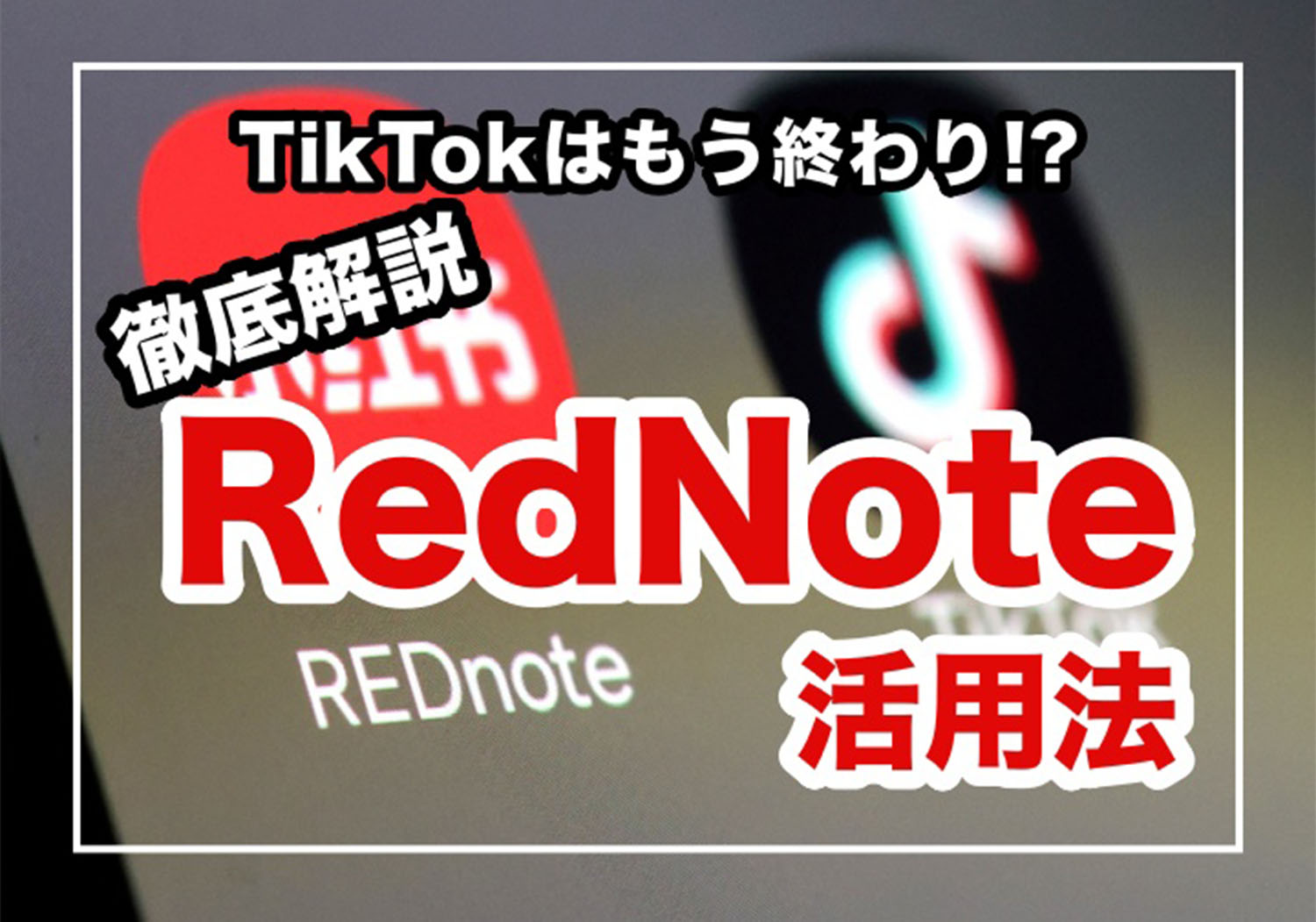
コメント