
こんにちは、クセのつよい映像制作会社「トビガスマル」代表の廣瀬です。
企業の広報や採用、ブランディングにおいて、
「とりあえず動画を作りたい」「SNSで発信したい」という相談を受けることがよくあります。
ですが、制作の現場で私がまずお聞きするのは、
『なぜ、その動画を作るのか?』という一点です。
動画編集や映像制作は、ただ“かっこいい映像”を作る作業ではありません。
目的を間違えると、どれだけクオリティが高くても届かない。
逆に、目的が明確なら、スマホで撮った映像でも心を動かすことができます。
本記事では、企業・広報担当者が動画を作る前に整理すべき
7つの目的と、成果につながる動画設計の考え方を、
現場目線でわかりやすく解説します。
「動画を作ること」よりも、「なぜ作るのか」を明確にする。
それが、映像を“コスト”ではなく“資産”に変える第一歩です。
目次
なぜ今、企業に動画が求められているのか
文字より「体験」を伝える時代へ
かつては、企業が伝えたいことを“言葉”や“写真”で発信していました。
しかし今の時代、ユーザーが求めているのは「情報」よりも“体験”です。
動画は、音・表情・空気感を含めて“企業の人格”を伝えることができるメディア。
静止画では伝わらないリアルな雰囲気や人の温度を、数秒で届けることができます。
SNSや採用サイトを見ていても、「この会社、なんか信頼できる」と感じるのは、
テキストではなく映像で見たときではないでしょうか。
SNS・採用・展示会——どこでも“動画が顔”になる
今、あらゆる企業が「動画で語る時代」を迎えています。
Webサイト、SNS、採用イベント、展示会ブース。
どのタッチポイントでも、最初に目に入るのは動画です。
動画は第一印象をつくるメディア。
つまり、“企業の名刺”でもあり、“営業担当”でもあるということです。
特にBtoB業界では、営業担当が訪問する前に動画で企業を知ってもらうケースが急増中。
その数十秒の映像が「信頼できる会社かどうか」を左右します。
動画は「伝える」ではなく「感じてもらう」ツール
テキストや資料では伝わらなかったものが、動画では一瞬で伝わる。
それは、映像が「情報」ではなく“感情”を動かすメディアだからです。
たとえば、工場の音、社員の笑顔、代表の語り。
それらが組み合わさることで、“会社の温度”や“価値観”が自然に伝わります。
企業のブランディングや採用活動で「共感を生む」ことが重要視される今、
動画はその中心にある表現手段と言えます。
動画は“企業の印象をデザインする”時代へ
動画制作は、単なる宣伝ではなく企業の印象設計です。
どんなトーンで話すか、どんな表情で登場するか、どんなBGMで流すか。
そのすべてが、企業の「人となり」を形づくります。
だからこそ、今の時代において動画は「作ること」ではなく、“どう伝えるか”を設計する戦略メディアなのです。
動画を作る前に整理すべき7つの目的
動画制作の打ち合わせで「どんな映像を作りたいですか?」と伺うと、
「会社紹介」「採用動画」「サービス紹介」などの回答がよく返ってきます。
ですが、本当に大切なのは“形式”ではなく目的です。
なぜその映像を作るのか?誰に何を伝えたいのか?
ここを明確にしておかないと、せっかくの動画も届かない映像になってしまいます。
以下の7つの目的を整理することで、「目的から逆算した動画設計」が可能になります。
① 企業ブランドを伝える
もっとも基本となるのがブランド認知のための動画です。
企業の理念、文化、社会への姿勢など、文字では伝わりづらい価値観を映像で表現します。
特に、「どんな人が働いている会社なのか」を映像で見せることで、
視聴者は企業を“人として”理解します。
ブランディング動画は、商品ではなく信頼を売るための映像です。
② 採用・リクルート活動を強化する
採用動画は近年、企業広報で最もニーズの高いジャンルです。
文字だけの求人票では伝わらない「職場の空気」「社員のリアル」を伝えることで、
応募者の共感とエンゲージメントを高めます。
“働く人の表情”を見せることが、何よりの採用力。
動画は「この会社で働きたい」と思わせる最強のPRツールです。
③ 商品・サービスをわかりやすく説明する
どんなに優れたサービスでも、説明が難しいと伝わりません。
動画なら、動きや図解・ナレーションを交えて直感的に理解させることができます。
特にBtoB企業の製品紹介では、「30秒で理解できる」ことが重要。
動画は営業ツールとしても効果を発揮し、展示会やWebサイトでの接点強化に役立ちます。
④ 顧客の信頼を獲得する(実績・インタビュー動画)
顧客の声や導入事例を動画で紹介することで、信頼と実績を可視化できます。
テキストの事例紹介よりも、実際の声や表情を通じてリアリティを伝えられるのが強みです。
「どんなお客様がどんな理由で選んでくれたのか」。
そのリアルな声は、次の顧客を動かす“最強の営業資料”になります。
⑤ 社内文化や想いを共有する(インナーブランディング)
社内向けの動画も重要です。
社員総会、周年イベント、経営理念ムービーなど、
映像を使うことで「会社の想い」をより深く共有できます。
組織づくりの根底にあるのは、“想いの共有”。
動画は、言葉以上に共感を生む社内コミュニケーションツールです。
⑥ 広報・プレスリリースの補完として使う
企業ニュースや新製品発表などの際、動画を添えることで報道価値が高まります。
プレスリリースだけでなく、映像素材を配信することで
“報道されやすい企業”をつくることができます。
特に自治体・公共団体では、映像発信が「透明性」と「信頼性」を高める役割を果たします。
⑦ SNS・AI時代の「拡散力」を活かす
AIが進化し、SNSが主戦場になった今、動画は“拡散する言葉”を持っています。
企業が自ら語るだけでなく、社員・顧客・ファンが動画で語る時代。
短尺動画(ショート動画)やAI自動編集ツールを活用することで、
スピード感と表現力を両立した発信が可能です。
動画を“継続的に出す仕組み”を整えることで、ブランドの鮮度を保てます。
目的が定まれば、映像の形は自然に決まる
動画を作るときは、「何を作るか」ではなく「なぜ作るか」。
目的を明確にすることで、最適な長さ・構成・演出が見えてきます。
動画制作はゴールではなく、“目的を叶える手段”。
この7つの目的を整理しておけば、次の動画は確実にブレない軸を持てます。
“目的が明確な動画”は成果が違う
なんとなく作った動画は、誰にも届かない
動画制作で最も多い失敗が、「とりあえず動画を作る」というパターンです。
目的が曖昧なまま制作を進めると、映像自体は綺麗でも「誰に」「何を」「なぜ伝えるのか」がぼやけ、視聴者の記憶に残りません。
広報動画なのか、採用動画なのか、営業用なのか。
意図を明確にしないまま作ると、社内でも評価軸がブレてしまうのです。
結果として「再生数はあるけど成果がない」「良い動画だけど使われない」といった現象が起こります。
“目的がある動画”は視聴者の行動を変える
一方、目的が明確な動画は、短くても強い。
たとえば採用目的なら「この会社で働いてみたい」と思わせる。
営業目的なら「問い合わせしたい」と思わせる。
つまり、視聴者の行動をデザインしているのです。
動画の本質は、情報を流すことではなく、“次の一歩”を生むこと。
目的が明確であれば、動画は「広報資料」ではなく「行動のきっかけ」に変わります。
再生回数よりも“目的到達率”を見よう
動画の成果を測るとき、多くの企業が「再生数」や「視聴維持率」に注目します。
しかし本当に見るべきは、目的をどれだけ達成できたか。
たとえば、採用動画なら「応募者数」や「説明会参加率」。
ブランディング動画なら「問い合わせの質」や「認知拡大」。
明確な目的があれば、KPI(成果指標)も正しく設定できます。
数字を追う前に、まず“動画のゴール”を決める。
そこが整えば、効果測定もブレません。
目的を決めると、制作コストも最適化できる
不思議なことに、目的が明確な動画ほど、無駄なコストがかかりません。
なぜなら「やらなくていい演出」がはっきりするからです。
「伝えたいのは理念か、製品か、人か?」
この優先順位が決まるだけで、撮影シーン・編集構成・ナレーションの使い方まで整理されます。
結果として、“短く・安く・効果的”な動画が生まれます。
目的が決まれば、すべての判断が速くなる
動画制作は、目的を決めることで加速します。
どんな映像を作るか、どの尺で構成するか、どんなBGMを選ぶか——。
そのすべての判断基準は「目的」です。
目的が曖昧な動画は、編集も評価も曖昧。
逆に目的が明確なら、全員が同じゴールを見て動ける。
それが、結果的に成果を生む“チームとしての動画制作”につながります。
動画制作の目的を決める3ステップ
「動画を作る目的を整理する」と言われても、最初は難しく感じるかもしれません。
でも大丈夫です。
実は、明確な目的は3つの質問に答えるだけで導き出せます。
この3ステップを押さえておけば、社内の企画会議でも「方向性がズレない」映像を企画できるようになります。
① 誰に届けたいのか(ターゲットを定義する)
まずは、“誰に見せたい動画なのか”を明確にしましょう。
学生・顧客・取引先・社員——誰を想定するかによって、構成も演出も180度変わります。
たとえば、採用動画なら「学生が共感できるリアルさ」を重視。
BtoB商材なら「決裁者が信頼を感じる丁寧さ」を重視。
ターゲットを決めると、語り口・BGM・カットテンポなど、すべての要素が明確になります。
動画制作は、まず「誰に届けるのか」から始まります。
② 何を感じてほしいのか(感情を設計する)
次に考えるのは、見た人の感情設計です。
動画を見たあとに、視聴者にどう感じてほしいかを言語化しましょう。
「信頼できそう」「楽しそう」「挑戦してみたい」「感動した」——。
映像は情報ではなく感情を動かすメディアなので、狙う感情を明確にすることが成功の鍵です。
ここを曖昧にすると、動画のトーンが定まらず、
“何を伝えたいか分からない映像”になってしまいます。
③ 見たあとどうしてほしいのか(行動を設計する)
最後に、動画のゴール=行動を定義します。
見たあとに、視聴者に何をしてほしいのか? これが明確になると、構成の流れが一気に整います。
たとえば…
- 採用動画 → 説明会・応募ページに誘導する
- 商品紹介動画 → 資料請求や問い合わせを促す
- ブランド動画 → サイト滞在時間を伸ばし、印象を定着させる
つまり、「動画の終着点」を最初に決めるのが成功のコツです。
視聴者が“見たあとにどう動くか”を想像できれば、動画のストーリーは自ずと決まります。
3つの軸で目的を可視化すれば迷わない
ターゲット(誰に)・感情(どう感じてほしいか)・行動(何をしてほしいか)。
この3つを明確にするだけで、動画制作の方向性は迷わなくなります。
この考え方は、私たちトビガスマルでも常に意識している基本です。
目的を“感情と行動”の両面から設計することで、“伝わる映像”が生まれるのです。
AI時代でも“目的設計”が最重要な理由
AIは“映像”を作れるが、“意図”は作れない
AI編集ツールが進化し、映像制作はかつてないほど手軽になりました。
カット編集・色補正・自動テロップ——。
以前は数時間かかっていた作業が、今では数分で完了します。
しかし、AIが作るのはあくまで「形としての映像」です。
“なぜこの映像を作るのか”という意図や目的は、人間にしか設計できません。
同じ素材をAIが編集しても、目的が違えば伝わり方はまったく変わります。
だからこそ、AI時代ほど「目的設計」が重要になるのです。
AIが苦手なのは“感情の温度”
AIは、トランジションやBGMを選ぶことは得意です。
ですが、「この表情に0.5秒だけ間を持たせると“誠実さ”が伝わる」といった
“温度の編集”は、まだ人間の領域です。
動画は感情のメディア。
だからこそ、AIがいくら正確でも、心を動かす映像にはならないことがあります。
目的と感情を理解して“間”を作れるのは、人の感性だけ。
AIツールは“手段”、設計は人の仕事
AIはとても頼もしいアシスタントです。
ですが、AIを“監督”にしてしまうと、映像は一瞬で無個性になります。
目的が明確なら、AIをどう活かすかの判断も変わります。
たとえば…
- ブランド動画 → AIで効率化しつつ、ナレーションと演出は人が調整
- 採用動画 → AIでカット整理し、人間が感情の流れを設計
つまり、AIを動かすのは「意図」。
AIが編集を代行しても、“映像の意味”を決めるのは人間です。
AI編集時代の“人間クリエイター”の価値
AIが普及すると、「誰でも動画を作れる」時代になります。
だからこそ、人間クリエイターの価値は“目的を翻訳する力”に移っていきます。
企業が伝えたい想いを、映像の形に翻訳する。
この役割は、AIには担えません。
映像制作とは、ただ編集するのではなく、“意図を見える形にする仕事”なのです。
AI時代は「誰が作るか」より「なぜ作るか」
AIで動画を作るスピードは上がりました。
しかし、速く作れることと、伝わることは別問題です。
これからの時代は、「誰が作るか」よりも「なぜ作るか」。
目的を設計できる人が、動画コミュニケーションの中心に立ちます。
AIを使うかどうかよりも、“何を伝えるために使うか”。
そこにこそ、企業の映像戦略の未来があります。
まとめ|動画の目的は「伝える相手の行動を変えること」
動画制作の目的は、再生回数を増やすことでも、映像を綺麗に見せることでもありません。
本質はただひとつ。
「伝える相手の行動を変えること」です。
採用動画なら「応募したくなる」、
ブランド動画なら「共感してファンになる」、
商品紹介動画なら「購入や問い合わせをしたくなる」。
動画の真価は、“見たあとの変化”にあります。
つまり、映像は情報ではなく体験。
どんなに短くても、見る人の心に“何かが残る”動画が強い。
そのためには、最初に目的を明確にし、そこから逆算して構成・撮影・編集を設計することが欠かせません。
動画制作は「広報戦略」ではなく「企業戦略」
動画は今や広報の領域を超え、経営コミュニケーションの中核になっています。
企業理念の共有、採用、社内文化の醸成、顧客との信頼構築。
動画を通じて、企業がどう見られるかが決まる時代です。
だからこそ、「動画を作るかどうか」ではなく、
「何を伝え、どう動かしたいのか」を決めることがスタートラインです。
“映像の意図”が企業を動かす
トビガスマルの現場でも、最初の打ち合わせで必ず確認するのは、
「この映像で、誰の心をどう動かしたいですか?」という質問です。
目的が明確な動画は、チームの意思がひとつになります。
制作スタッフ・広報担当・経営陣——みんなが同じゴールを見て動ける。
その状態こそが、最も効果的な動画プロジェクトの形です。
映像の“意図”が整えば、結果は自然についてきます。
最後に:動画は「企業の想いを可視化する」メディア
AIが進化し、情報があふれる今こそ、“想いのある映像”が必要です。
動画は単なる宣伝ツールではなく、企業が社会に語りかける言葉。
目的を明確にし、心の通った映像を作る。
それが、これからの時代における最強のブランディング戦略です。
そして——。
動画を制する者は、伝達を制す。
そのための「目的設計」こそ、映像制作の原点なのです。

2025.10.28
構図とは、被写体の配置・カメラの高さ・背景とのバランス。 ほんの数センチ、レンズの角度を変えるだけで、 「誠実そう」「話を聞きたくなる」「画面に安心感がある」といった印象が生まれます。 逆に、構図を間違えるとどんなに良い内容でも 「暗い」「威圧的」「距離を感じる」と思われてし...


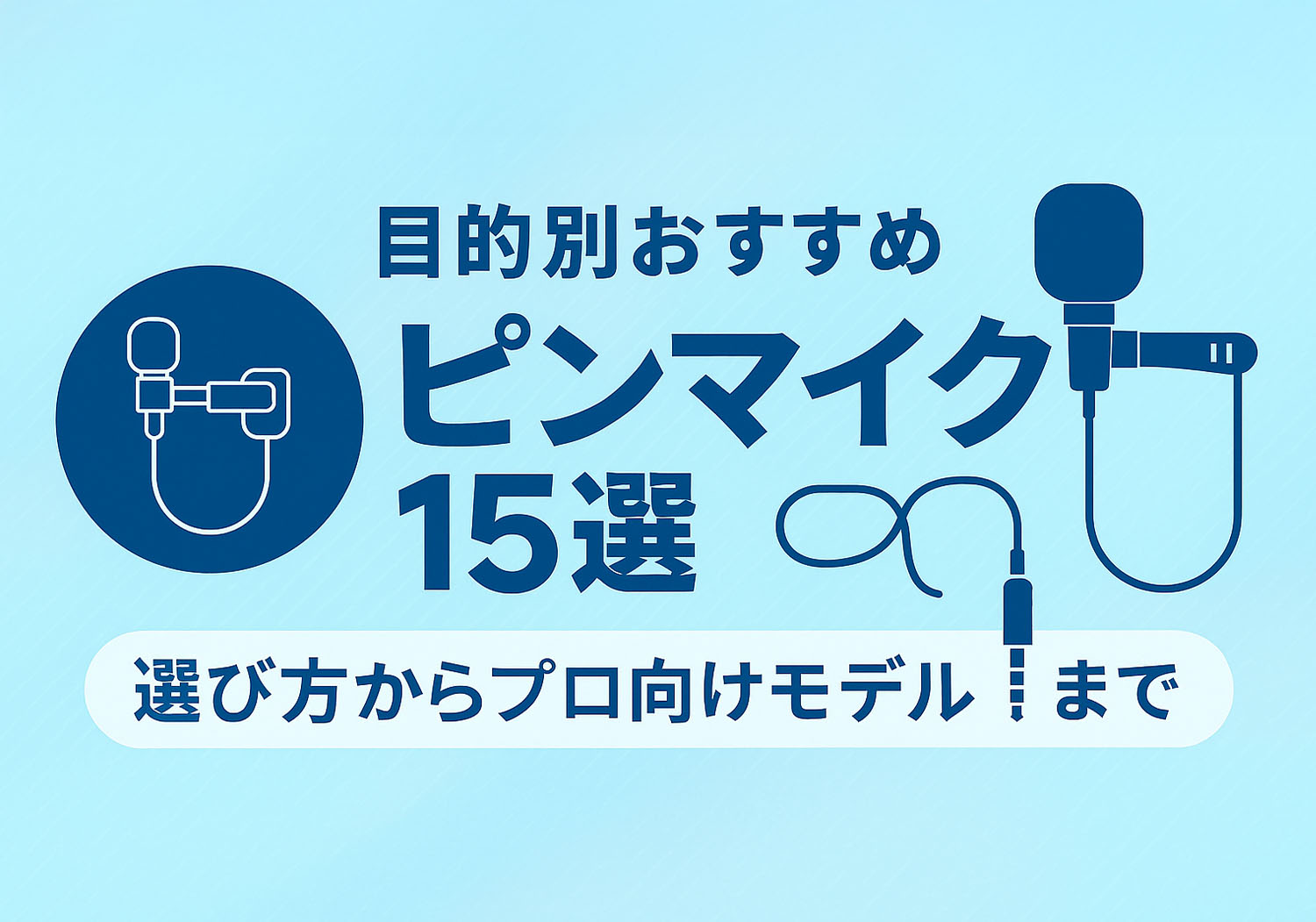
コメント