
こんにちは、クセのつよい映像制作会社「トビガスマル」代表の廣瀬です。
企業や団体のインタビュー動画を撮っていると、
「どうして同じカメラでも、プロが撮ると“信頼感”があるんだろう?」と聞かれることがよくあります。
答えはシンプルです。“構図”が違うんです。
構図とは、被写体の配置・カメラの高さ・背景とのバランス。
ほんの数センチ、レンズの角度を変えるだけで、
「誠実そう」「話を聞きたくなる」「画面に安心感がある」といった印象が生まれます。
逆に、構図を間違えるとどんなに良い内容でも
「暗い」「威圧的」「距離を感じる」と思われてしまう。
つまり、構図は“印象をコントロールする技術”なんです。
この記事では、
– インタビュー動画で覚えておきたい構図の基本
– 被写体・背景・カメラ位置のバランスの取り方
– プロが現場で使う構図づくりのコツ
– そしてAI時代の“自動構図補正”の使いこなし方
を、現場目線でやさしく解説します。
これを読めば、あなたのインタビュー動画が
「なんか信頼できる」「ちゃんとしてる」と言われるようになります。
今日から“構図の目”を持った撮影者になりましょう。

2025.08.08
この記事では、ネットでさっと買える厳選写真集をレベル別(初心者→中級→上級)に紹介しつつ、ページをめくりながら使える観察チェックリストと、1冊を“3周で血肉化”する読み方もセットで解説します。 「今すぐ上達のスイッチを入れたい」人は、まずは最初の1冊をポチって今週末に10分の“構図...
目次
なぜ構図がインタビュー動画の印象を左右するのか
視聴者の“第一印象”は3秒で決まる
動画を再生してから最初の3秒で、視聴者は「信頼できる」「見づらい」「雰囲気がいい」といった印象を無意識に判断します。
これは心理学的にも「初頭効果」と呼ばれ、最初に与えた印象がその後の評価に強く影響することがわかっています。
インタビュー動画では、話す内容よりも先に、“見た目の印象”が信頼性を左右します。
カメラの高さ、レンズの角度、被写体の位置、背景の整理。
たったそれだけで、動画全体のクオリティが一段上がります。
構図が伝える心理的メッセージ
構図には、視聴者に与える無言のメッセージがあります。
例えば、カメラが少し見上げる位置にあると「威厳」や「自信」が伝わり、
逆に見下ろす構図では「親しみ」「柔らかさ」を感じさせます。
また、被写体を中央に配置するセンター構図はフォーマルで安定感があり、
三分割構図では会話の余白や自然さを演出できます。
つまり、構図は単なる“画面のバランス”ではなく、人の感情をデザインする手段なんです。
構図が整うと、言葉の信頼度が上がる
プロの現場では、「構図を整える=話の説得力を上げる」と言われます。
構図が乱れていると、無意識に視聴者の注意が散り、内容に集中できません。
しかし、構図が安定している映像では、視線の誘導がスムーズになり、
話す人の言葉が自然と心に届きやすくなります。
たとえば、被写体の目線をカメラより少し上に置くだけで、
「自信」「落ち着き」「誠実さ」が生まれます。
つまり構図とは、見せたい印象を“操作できる”技術なのです。
プロの現場が“構図”に時間をかける理由
撮影現場では「1分話してもらうより、カメラ位置を1センチ動かす方が効果的」と言われることがあります。
構図が整うと、ライティング・表情・声のトーンまでも自然に噛み合う。
それほど“映像の土台”として構図は重要です。
逆に言えば、構図をおろそかにすると、どんなに照明や機材が高性能でも、仕上がりに「違和感」が残ります。
だからこそ、プロはまずカメラの位置と角度に全神経を注ぐのです。
構図は“信頼をつくる見えない演出”
インタビュー動画における構図は、見た目を整えるためのものではなく、信頼感を演出する技術です。
「この人の話をもっと聞きたい」と思わせるのは、被写体の言葉ではなく、映像の安定感。
つまり構図とは、“聞き手の心理”をデザインするツール。
次に紹介する「基本の構図パターン」を押さえれば、
誰でも“プロっぽい映像”を作れるようになります。
基本の構図3パターンを押さえよう
構図の基本を押さえるだけで、インタビュー動画の“信頼感”と“見やすさ”は劇的に変わります。
ここでは、プロの現場でも定番の3つの構図パターンを紹介します。
① センター構図:フォーマルで安定感のある印象
センター構図とは、被写体を画面の中央に配置する最もシンプルな構図です。
ニュース番組や公式メッセージ動画などでよく使われ、
誠実・信頼・公的といった印象を与えます。
ポイントは、カメラを被写体の目線と同じ高さに設定すること。
少しでも上から撮ると“弱々しく”、下から撮ると“威圧的”に見えてしまうため、
正面からしっかり目線を合わせることが大切です。
背景はなるべくシンプルに。ロゴや壁面、布バックなど、情報量を抑えることで、
視聴者の意識を「言葉」に集中させられます。
② 三分割構図:自然で親しみのある印象
三分割構図は、画面を縦横3分割した線の交点に被写体を配置する手法です。
ニュースよりも会話的で、企業紹介・YouTube・社内インタビューに最適。
カメラを少し斜め45度に振り、視線の先に空間(余白)を作るのがポイント。
この「話している方向に空間を残す」ことで、自然な会話の流れを感じさせられます。
背景に観葉植物やオフィスの壁などを入れると、
「その人らしさ」や「現場感」が出て、映像に温度が生まれます。
ただし、奥行きをつけすぎるとピントが甘くなるので注意しましょう。
③ ナナメ構図:ドキュメンタリー感と臨場感を演出
ナナメ構図は、被写体を中央ではなく少し斜めから捉える方法です。
カメラ位置を被写体の右または左にずらし、対角線上に背景を抜くことで、
“リアルな現場感”や“ドキュメンタリー的空気感”を出せます。
トーク番組やメイキング映像、社員インタビューなどにぴったり。
特に「複数のカメラ」を使う場合、1台をナナメ構図で撮ると映像に変化が生まれ、編集時の切り替えがスムーズになります。
注意点は、被写体がフレームの端に寄りすぎないこと。
頭上に少し余白を取り、肩先が画面外に切れないよう調整することで、
バランスの良い構図になります。
構図の使い分けで“印象操作”ができる
センター構図=信頼、三分割構図=親しみ、ナナメ構図=臨場感。
たったこれだけで、インタビュー動画の世界観は大きく変わります。
映像のテーマや伝えたいメッセージに合わせて、構図を“意図的に選ぶ”ことが、
プロの現場では欠かせません。
構図はカメラ位置ではなく「演出の一部」なのです。
被写体・背景・カメラ位置の黄金バランス
「構図が整っている」とは、単にフレームの中が綺麗ということではありません。
大切なのは、被写体・背景・カメラ位置の3つが絶妙に噛み合っていること。
この3点のバランスが取れると、“見やすく、安心感のある映像”になります。
逆にどれか1つでもズレると、
・被写体が暗く見える
・背景がうるさい
・カメラが不安定に感じる
といった印象が生まれ、全体の完成度を下げてしまいます。
では、それぞれのポイントを見ていきましょう。
① 目線の高さとカメラ位置を合わせる
インタビュー動画の基本中の基本は、カメラの高さ=被写体の目線の高さに合わせること。
目線が下すぎると「威圧的」、上すぎると「弱々しい」印象になります。
理想的なのは、被写体の目線がフレーム上1/3の位置にくる構図。
これは“黄金比構図”とも呼ばれ、視聴者が最も自然に感じるバランスです。
また、目線がカメラの真ん中より少し右(または左)に寄ることで、
会話の流れや方向性が感じられ、より自然な印象を与えます。
② 背景の奥行きで「立体感」を作る
背景をどう見せるかで、映像の印象は大きく変わります。
壁に近すぎると平面的で窮屈に見えるため、
被写体と背景の距離を1.5〜2メートルほど離すのが理想です。
そのうえで、明るい背景の中に“暗い被写体”を置かないよう注意。
背景が明るすぎるとカメラの露出が引っ張られ、顔が暗く写ります。
可能であれば、背景の明るさは被写体より1段階落とすと立体感が出ます。
植物・窓・社名サインなどをボケ味で入れると、
“雰囲気のある背景”を演出できます。
③ 余白(ネガティブスペース)をデザインする
構図を整えるうえで重要なのが、余白の使い方です。
被写体の周りに空間を残すことで、
画面に呼吸感とプロっぽさが生まれます。
特に、インタビューの話す方向側に余白を作ると、視聴者の意識が自然と相手に流れます。
逆に、話す方向が詰まっていると圧迫感を感じてしまいます。
また、フレーム上部に少しだけ“頭上の空間”を残すのもポイント。
「頭が切れて見える」だけで一気に素人っぽく見えてしまうため、
撮影時には1〜2cmの余裕を意識しましょう。
④ 三脚とレンズ選びで安定感を出す
いくら構図が良くても、カメラがブレていたらすべて台無しです。
三脚を使い、カメラを固定+水平に保つことが大前提。
水平が取れていない映像は、視聴者の無意識に「違和感」や「不安定さ」を与えます。
また、インタビューでは焦点距離50〜85mm前後のレンズが最適。
被写体を自然に切り取りつつ、背景のボケで奥行きを演出できます。
手持ちで撮る場合は、カメラを胸の高さに固定し、呼吸に合わせてゆっくり動かすと安定感が出ます。
構図は「三角形の関係」を整えること
被写体、背景、カメラ位置。
この3つを三角形のようにイメージして配置することで、
映像は自然にバランスが取れます。
構図の美しさは、「配置の整い」と「距離感の心地よさ」。
撮影前に数秒だけ“被写体・背景・カメラ”の位置関係を確認するだけで、
動画の完成度が見違えるほど変わります。
現場で役立つ!構図づくりの実践テクニック
構図の理論を理解したら、次は実際の撮影現場でどう応用するかです。
ここでは、プロの映像制作現場でも使われる「構図調整のコツ」を紹介します。
ちょっとした工夫で、インタビュー動画のクオリティは驚くほど変わります。
① 三脚と照明で「構図の安定」をつくる
構図を安定させる第一歩は、カメラを固定すること。
三脚の脚をしっかり開き、水平を保つだけで画の落ち着きが変わります。
照明も構図の一部です。
被写体の顔の左上45度からライトを当てると、自然な陰影が生まれ、立体感のある構図になります。
ライトの位置が低いと「怖い印象」、正面すぎると「のっぺり」とした印象になるため、
構図とライティングはセットで考えることが重要です。
② 複数カメラで構図バリエーションを作る
インタビュー動画でよく使われる手法が、マルチカメラ構成です。
1台をメイン(センター構図)、もう1台をサブ(ナナメ構図)で配置すれば、
カット切り替え時にリズムと深みが出ます。
このとき、サブカメラはメインから30〜45度ほどの角度で設置するのが理想。
距離を変えすぎると編集で違和感が出るので、
被写体との距離はおおよそ同じに保ちましょう。
サブカメラには少し長めのレンズ(85mm前後)を使うと、
柔らかいボケ感が出て、画面がプロっぽくまとまります。
③ カメラ揺れを防ぐ“呼吸テク”
意外と盲点なのが撮影者の呼吸です。
特に手持ち撮影では、呼吸とともにカメラが上下して構図がブレます。
コツは、「息を止めずにリズムを一定に保つ」こと。
呼吸を意識的にゆっくりにすることで、手の動きも安定し、構図のズレを防げます。
どうしてもブレる場合は、一脚やスタビライザーを併用しましょう。
重量のある機材ほど安定するので、軽量カメラを使う場合は逆にブレ対策を強化するのがポイントです。
④ 現場チェックリストで“ズレ防止”
撮影前に毎回、以下のチェックを行うだけで構図トラブルを防げます。
- 被写体の目線はカメラの1/3ラインにあるか?
- 頭上・左右に余白が均等にあるか?
- 背景が傾いていないか(水平確認)?
- 明るさ・色味が左右でズレていないか?
これらは、現場でプロも実際に口に出して確認しています。
慣れてくると、構図が“整っている映像”を感覚で判断できるようになります。
⑤ 撮影中は「話し手」ではなく「画面」を見る
インタビュー中、つい話の内容に意識が向いてしまいますが、撮影者は画面監督です。
話を聞くよりも、「画面の中で何が起きているか」を見てください。
被写体が体を前に傾けた瞬間や、頭を動かしたタイミングで、
“構図のズレ”が一気に生まれることがあります。
その都度、ズームや三脚の微調整でフレームを再構築する。
これが、プロが「安定した映像」を維持できる理由です。
構図づくりは“秒単位の調整力”
インタビュー動画の構図は、一度決めたら終わりではありません。
撮影中も常に「今、映像として美しいか?」を確認し続けることが重要です。
カメラを構えながら、被写体・背景・光を意識する。
その瞬間ごとの“バランス感覚”こそが、プロとアマを分ける決定的な差になります。
AI時代の構図最適化:自動構図補正をどう使う?
近年、動画編集ソフトにはAIによる自動構図補正やリフレーム機能が続々と搭載されています。
Final Cut ProやDaVinci Resolve、Premiere Pro、そしてスマホアプリでも、
被写体を自動追尾して“最適な構図”をキープしてくれる機能があります。
便利ですよね。
でも、AIの構図はあくまで“数学的な最適化”。
「美しさ」や「感情の距離感」までは、まだAIには読み取れません。
① 自動構図補正のメリット
AIによる構図補正が得意なのは、安定感の確保と被写体追尾です。
被写体が動くインタビューや、カメラが固定できないロケ環境では大活躍。
たとえば、DaVinci Resolveの「Smart Reframe」やFinal Cutの「自動トリミング」機能では、
被写体を検出して中央に収めることで、構図のズレを瞬時に補正してくれます。
これは、“最低限の見やすさ”を確保する強力な保険になります。
② AI構図の“限界”を理解する
AIはフレーム内の被写体を“数値的に中心”に置こうとします。
つまり、人の会話の流れや表情の変化を読まずに、
ただ“顔を真ん中”に配置してしまうことが多いのです。
その結果、「話している方向の余白が消える」「目線が不自然」といった現象が起こります。
AIが構図を直しても「なんか変だな」と感じるのは、
人間が“会話の空気”を読み取る生き物だからです。
つまり、AI構図補正は万能ではなく、“安全運転”のためのツールとして使うのが正解です。
③ AIと人間の“役割分担”が最強
AIが得意なのは「ズレを防ぐ」こと。
人間(撮影者)が得意なのは「雰囲気を作る」こと。
この二つを組み合わせれば、“正確かつ感情的な構図”を作れます。
たとえば、撮影後にAIリフレームでトリミングを補正しつつ、
自分の手で“少し右にズラす”ことで、会話方向に余白をつくる。
このようにAIと人間の判断をミックスするのが、現場で最も現実的な方法です。
「AIに任せきり」は早いけど浅い。
「人の手だけ」は深いけど時間がかかる。
理想は、AIに土台を作らせて、人間が“温度”を足すことです。
④ AI構図機能を活用できるおすすめツール
ここで、現場でもよく使われるAI構図ツールを紹介します。
- Final Cut Pro:自動クロップ/リフレーム機能(被写体追従が自然)
- DaVinci Resolve:Smart Reframe(SNS比率変換にも最適)
- Adobe Premiere Pro:Auto Reframe Sequence(YouTube Shorts・Reels対応)
- CapCut/Runway:AIトラッキングによる構図補正
これらを使うと、編集後の「構図崩れ」や「SNS比率変換時の切れ」を防げます。
特にSNS向け動画では、AI構図補正は“必須の仕上げ工程”になりつつあります。
⑤ AI時代でも残る“人間のセンス”
AIがどれだけ進化しても、最後に映像の印象を決めるのは人間の感覚です。
被写体との距離、空気感、会場の温度、光の揺らぎ。
これらを感じ取って構図を整えるのは、まだAIにはできません。
トビガスマルの現場でも、AI補正は使います。
でも最終的には、「見る人の心地よさ」を基準に構図を整える。
AIが出した正解に、“人間の違和感センサー”を重ねる。
それが、AI時代の映像クリエイターに求められる新しい感性です。
AI構図は“補助輪”、感情は人間の仕事
AIが構図を整えてくれる時代だからこそ、人間のセンスが光る。
AIに任せて“綺麗”な映像を作るのは簡単ですが、
人間にしか作れない“伝わる構図”には、感情・余白・間があります。
AIを使いこなすとは、AIに勝つことではなく、AIを味方にして作品を深くすること。
これが、これからの映像制作における“構図の新常識”です。
よくある質問(FAQ)
Q. インタビュー動画の構図で、初心者が最初に意識すべきポイントは?
A. まずは「目線の高さ」と「背景の整理」を意識しましょう。
カメラを被写体の目線と同じ高さに合わせ、背景をシンプルに整えるだけで、
画面の印象が一気にプロっぽくなります。
複雑な照明や高価な機材より、構図の基本バランスが何より大事です。
Q. 背景がごちゃついて見えるときはどうすればいい?
A. 背景を完全に隠すより、「ぼかす」か「整える」のが効果的です。
被写体を背景から1.5mほど離して撮ると、
自然なボケが生まれ、奥行きが感じられます。
また、余計な物を片づけるより、背景に“意味のある小物”を1つ置くだけで印象が変わります。
Q. スマホでも構図を工夫できますか?
A. はい、可能です。
スマホカメラでも「三分割構図」を意識するだけで、映像のクオリティが格段に上がります。
撮影設定でグリッド線をONにし、被写体を線の交点に合わせると、自然でバランスの取れた構図が作れます。
また、スマホは軽いので手ブレしやすいため、三脚やスタビライザーの使用をおすすめします。
Q. 1台のカメラだけで“プロっぽい構図”に見せるコツは?
A. 1カメ構成なら、「構図を動かさずに、被写体を動かす」のがコツです。
話す人の姿勢や向きを少し変えるだけでも、画の印象が大きく変わります。
カメラを動かしすぎず、被写体の動きで変化を出すのがポイントです。
Q. AIの自動構図補正を使えば、人間の感覚はもう不要?
A. いいえ、AIはあくまで“補助輪”です。
AI構図は被写体を正確に中心へ置いてくれますが、
人の感情や“空気の距離”までは判断できません。
最終的に信頼感を生むのは、人間のセンスと微調整。
AIを使いながらも「見る人にとって心地よい構図」を意識することが大切です。
Q. 広告・企業PR向けのインタビュー構図で気をつけることは?
A. 「企業の印象を左右する映像」として考えることです。
信頼感を出したい場合はセンター構図+低コントラスト背景、
親しみやすさを出したい場合は三分割構図+ナチュラルな光がおすすめ。
構図のトーンがブランドの雰囲気に直結します。
Q. どんなレンズがインタビュー構図に合いますか?
A. 定番は50mm〜85mmの中望遠レンズです。
人物の歪みが少なく、背景ボケが柔らかいのが特徴。
撮影距離を2m程度にとり、顔・肩・背景のバランスを整えると、自然で落ち着いた印象になります。
まとめ|構図を制する者がインタビューを制す
インタビュー動画で最も大切なのは、機材でも編集技術でもありません。
それは「構図」=“画面の中の空気づくり”です。
被写体の位置、カメラの高さ、背景との距離。
この3つが整うだけで、映像は驚くほど変わります。
逆に、どんなに高価なカメラを使っても、構図が崩れていれば信頼感のない映像になってしまうのです。
構図を整えるということは、被写体を尊重すること。
話す人を気持ちよく見せる構図には、撮影者の優しさと観察力が宿ります。
それが、視聴者の「この人、信頼できる」という感情につながるのです。
今回紹介したポイントを思い出してください。
- センター構図で“誠実さ”を演出
- 三分割構図で“会話の自然さ”を引き出す
- ナナメ構図で“リアルな臨場感”を出す
- 背景とカメラ位置で“奥行きと余白”を整える
- AI構図補正を“味方”にして人間のセンスで仕上げる
構図とは、映像における「語らない言葉」。
被写体が語る前に、すでに構図がストーリーを伝えています。
明日からの撮影で、ほんの少しカメラを動かしてみてください。
目線を1センチ上げる、背景を1歩下げる、光を半段落とす。
その小さな調整が、映像の印象を劇的に変えます。
そしていつか、“構図を考えなくても自然に整う”瞬間が来ます。
それは、あなたの中に“映像の目”が育った証です。
構図を制する者は、インタビューを制す。
今日から、カメラの向こうに“伝わる映像”を作りましょう。

2025.08.08
この記事では、ネットでさっと買える厳選写真集をレベル別(初心者→中級→上級)に紹介しつつ、ページをめくりながら使える観察チェックリストと、1冊を“3周で血肉化”する読み方もセットで解説します。 「今すぐ上達のスイッチを入れたい」人は、まずは最初の1冊をポチって今週末に10分の“構図...


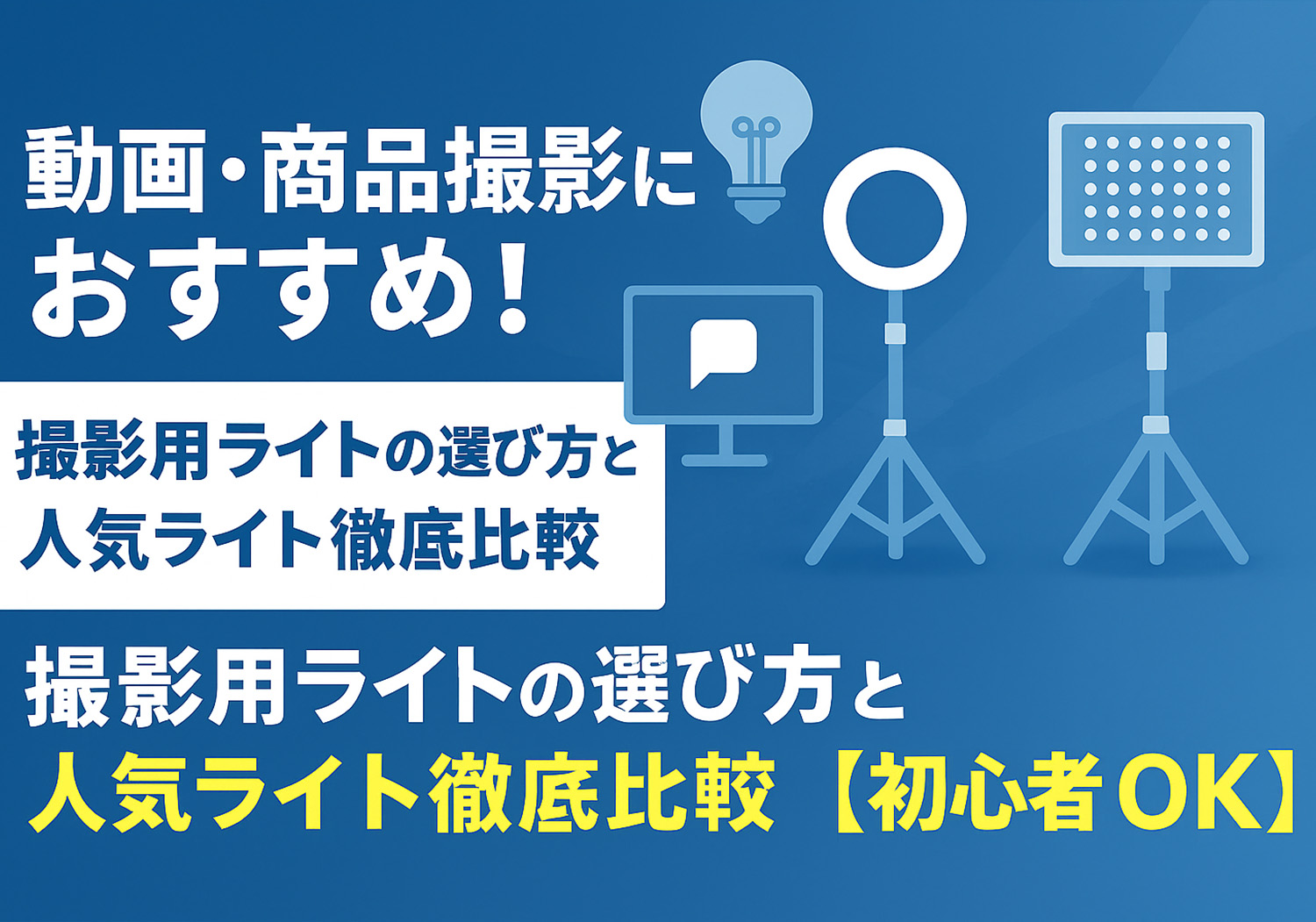
コメント