
こんにちは、合同会社トビガスマルの廣瀬です。日本の撮影環境は湿気と温度差が大敵。レンズのカビや鏡筒内のくもり、ボディの接点腐食は、撮影の仕上がりだけでなく修理コストにも直結します。でも安心してください。正しい保管ルールと簡単なメンテ手順を押さえれば、愛機はぐんと長持ちします。
本記事は初心者向けに、現場目線で「今日からやるべき最小手順」を整理しました。
なぜ保管が重要か(天敵とメリット/デメリット)→ 基本の保管方法(清掃・乾燥・置き場所・レンズ/バッテリーの扱い)→ おすすめ保管グッズ(防湿庫/ドライボックス/乾燥剤)→ メーカー別の注意(ニコン/キヤノン/FUJIFILM X-T50)の順に、迷わず実践できるようガイドします。
「撮影から帰ったら5分でできる習慣」まで具体的に落とし込みます。まずは、カメラを守る保管の基礎から一緒に整えていきましょう。
目次
なぜカメラの保管方法が重要なのか?
カメラとレンズの天敵:湿気・ホコリ・衝撃
- 湿気(最凶):レンズ内のカビ・くもりの主因。
目安は相対湿度40〜50%。60%超はカビ繁殖ゾーンです。 - ホコリ:センサー汚れやAF/ズーム機構の不調の原因。
マウント・スイッチ部・接点から侵入するため、防塵環境+保管前の簡易清掃が有効。 - 温度差(結露):冷房車内→蒸し暑い屋外などで一気に結露。
帰宅/外出時はバッグに入れたまま30分ほど慣らすと安全。 - 衝撃・振動:落下や圧迫でレンズの片ボケ/ズレ、IBISユニットや接点の不具合を招きます。
保管時は倒れない向き・安定した棚で。
保管環境を整えることのメリット
- 画質が安定:フレア・ゴースト・片ボケ・センサー斑点の発生を抑制。
- 故障・メンテ費を削減:カビ取り・分解清掃・ユニット交換の頻度を下げる。
- 撮影準備が速い:防湿庫やドライボックスに“定位置化”すると、出発前チェックが最短に。
- 資産価値の維持:状態良好=下取り・売却時に高値がつきやすい。
- トラブルの予防医学:不調の早期発見(異音・リングの重さ・接点不良)につながる。
保管を怠った場合のデメリット
- レンズカビの定着:コーティング侵食で完全修復不可になるケースも。
- センサーゴミの常駐:F8以上で黒点が目立ち、撮影後の現像に手間が増加。
- 接点腐食・誤作動:レンズ認識エラー、AF不安定、手ぶれ補正の異音など。
- 結露による基板・機構不良:繰り返すと錆・断線のリスク増。
- 余計なコスト・機会損失:修理代+撮影機会の逸失=ダブル損。
結論:カメラは“保管で寿命が決まる”道具です。
次章から、今日からできる基本手順(清掃→乾燥→低湿度で保管→レンズ/バッテリーの扱い)を具体的に解説します。
基本的なカメラの保管方法
保管前のメンテナンス:清掃と乾燥
- 電源OFF→レンズを外す(長期保管時)。ボディにはボディキャップ、レンズにはリアキャップを装着。
- ドライ清掃:ブロアー→柔らかいブラシ→マイクロファイバーの順で外装・マウント周り・スイッチ部を清掃。
レンズ面はブロアー→レンズクリーナーごく少量→拭き上げ(円を描かず中心から放射状に)。 - 雨天・海辺後:塩分・水滴を残さない。固く絞ったウェットクロス→乾いたクロスで仕上げ。端子・ホットシューは乾いた綿棒で。
- 乾燥:撮影バッグから出し、風通しの良い室内で1〜2時間陰干し。
湿ったストラップやバッグ内部も開いて乾かす(カビの温床になりやすい)。 - 乾燥剤の再生:色付きシリカゲルは色が変わったら取扱説明に従って再生(目安:100℃前後の低温オーブンで1〜2時間)。
※金属袋・指標タイプは電子レンジ不可のものが多いので必ず表示を確認。
保管場所の選び方:低湿度の環境
- 湿度の目安:相対湿度40〜50%(許容35〜55%)。
60%超はカビ繁殖ゾーン/30%未満が続くとグリスやゴムが乾きやすい。 - 温度の目安:15〜25℃で安定。急激な温度差(結露)を避ける。
- 置き場所:直射日光・窓際・外壁直下・床直置きは避け、通気性のある棚の中段へ。
長期は防湿庫やドライボックス+湿度計でコントロール(詳細は後章)。 - バッグに入れっぱなし禁止:密閉・残湿でカビやすい。帰宅後は収納から出して乾かすを習慣に。
- 湿度計を常備:アナログでもOK。40〜50%に収まっているか毎回チェック。
保管時の注意点:レンズとバッテリー
- レンズ:長期はボディから外し、前後キャップ+フード逆付けで保護。
収納は縦置きが基本(重ね置き・圧迫はNG)。ズームは最短側に戻しておくと機構に優しい。 - ボディ:キャップ装着・外装を軽く拭いて収納。
ミラーレスはセンサー面を上にしない(落ちたホコリが載りにくい向きで)。 - バッテリー:本体から外して保管。40〜60%残量で涼しく乾燥した場所に。
月1で残量点検(20%以下になったら追充電)。端子はショート防止キャップか袋に。
長期は耐火ポーチ保管が安心。 - メモリーカード:データを2重バックアップ後、ケースに入れて保管。
撮影前にカード内をカメラでフォーマット(PC削除のみはトラブルの元)。 - 月イチ可動:長期保管中も月1回、リング・スイッチを軽く動かすとグリス偏りや接点酸化の予防に。
5分ルーティン(帰宅後):
①拭く(ブロアー→クロス)→ ②乾かす(陰干し1〜2h)→ ③収納(防湿庫/ドライボックス)→ ④湿度計チェック(40〜50%)
季節・環境別の保管対策(梅雨/冬の結露/海沿い)
梅雨〜夏:高湿期のポイント
- 相対湿度は40〜50%キープ。ドライボックスは乾燥剤を多め+週1チェック
- 撮影帰りはバッグから出して陰干し1〜2h→収納。バッグ入れっぱなしはNG
冬:結露を起こさない移動
- 屋外→暖房室内/車内→屋外はバッグに入れたまま30分順応
- 防湿庫に戻す前に表面の水分を完全乾燥(水滴残りはカビの温床)
海沿い・山間部:塩分・霧対策
- 海風・潮だまり後は拭き取り→陰干し→収納の3ステップを徹底
- 霧の多い地域は防湿庫常用+月1で乾燥剤点検
結露対策ハンドブック(屋外⇄室内/車内保管)
移動時の“慣らし”時間
温度差が大きいときは、ケースやバッグのまま20〜30分置いて温湿度を馴染ませるのが安全。
車内保管の注意
- 夏場の車内は高温多湿+温度急変で最悪。短時間でも持ち出しが基本
- やむを得ない場合は日陰+保冷剤を直接触れさせない断熱パックで一時退避
防湿庫へ戻す前のチェック
- 水滴ゼロ/表面ドライを確認→ブロアー→クロス→収納
- レンズ交換は乾いた部屋で。湿った玄関や浴室前は避ける
おすすめの保管グッズ
防湿庫:長期保管に最適な環境
最も確実に湿度管理ができるのが電動防湿庫。内部の湿度を自動でコントロールでき、相対湿度40〜50%に安定させやすいのが利点です。
- 容量選び:「今の機材量 × 1.5〜2倍」が目安(将来のレンズ追加や書類・アクセ収納に余裕)。
- 設定の基本:湿度は40〜50%。30%以下が長期間続くとグリスやゴムの乾きが進むため避ける。
- 棚の使い方:重いレンズは下段の奥、ボディは手前の中段で取り出しやすく。ラベルで定位置化。
- 設置場所:直射日光・窓際・外壁直下を避け、水平な床に。振動や熱源の近くはNG。
- メンテ:月1でパッキン・棚板の拭き掃除/半年に一度、湿度計の校正(別計器と照合)。
簡易ドライボックス:手軽に湿度対策
防湿庫がない場合は密閉コンテナ+乾燥剤+湿度計で代用。コストを抑えつつ、十分な効果が得られます。
- 容器:パッキン付きの密閉ボックス(ロック機構あり)を選ぶ。サイズは機材量+20〜30%の余裕。
- 湿度管理:色付きシリカゲルを底面に敷き、小型の湿度計を中に入れる。目標は40〜50%。
- レイアウト:レンズは縦置き、ボディはキャップ装着。乾燥剤は直置き接触を避け、薄いトレーに。
- 運用:雨天ロケの後は、収納前に陰干し1〜2時間。週1で湿度をチェック。
乾燥剤:シリカゲルと防カビ剤
- シリカゲル(推奨):コバルトフリーの色付きタイプが扱いやすい。色が変わったら再生(取説に従い、目安100〜120℃で1〜2時間の乾燥)。
※電子レンジ不可の表示がある製品はレンジ使用NG。 - モレキュラーシーブ(ゼオライト):高湿環境でも吸湿力が落ちにくい高性能乾燥剤。梅雨〜夏場の補強に。
- 防カビ剤:カメラ/精密機器用と明記された低揮発タイプを選ぶ。
漂白系・強い溶剤臭のものはコーティングやゴムに悪影響の恐れがあるため避ける。 - 湿度計:ボックス内に1個。できれば別系統(アナログ+デジタル)の二本立てで相互チェック。
- 交換・管理:乾燥剤には導入日をメモ。梅雨入り・秋雨・冬の結露期など季節の変わり目は点検頻度を上げる。
どれを選ぶ?(結論):
据え置きで台数がある→防湿庫/コスト重視・持ち出し多め→ドライボックス+シリカゲル+湿度計。どちらでも40〜50%維持が最優先です。
ニコン・キヤノン製品の保管について
ニコン製品の保管方法
- ボディ(Z/一眼レフ):電源OFF→数秒待って内部ユニット(手ぶれ補正/シャッター)が完全停止してからレンズ着脱。
保管はボディキャップ装着・外装を拭き上げ、相対湿度40〜50%環境へ。 - レンズ(Z/NIKKOR F):長期はボディから外し、前後キャップ+フード逆付け。
重量級(望遠・大三元)は縦置きでマウント負荷を回避。ズームは最短側に戻しておくと機構に優しい。 - VRスイッチ:保管時はOFF側で問題なし(実運用時の初期値が明確)。電源OFF直後は数秒待ってから移動・収納するとユニットへの衝撃リスクを下げられます。
- FTZ使用時:アダプターは別保管(キャップ装着)。ボディ⇔レンズの間に挟んだままの長期放置は避ける。
- バッテリー(EN-EL系):本体から外し、40〜60%で涼しく乾燥した場所に。月1で残量点検し、20%以下なら追充電。端子はショート防止のキャップか袋へ。
キヤノン製品の保管方法
- ボディ(EOS R/一眼レフ):電源OFF→数秒待機→キャップ装着。センサー面に埃が落ちにくい向きで収納(横置き推奨)。
- レンズ(RF/EF):前後キャップ+フード逆付け。重量級(70-200/100-500など)は縦置き、重ね置き・圧迫はNG。
IS(手ぶれ補正)は保管時OFFでOK。移動時はIS停止音が消えてからしまうと安心。 - エクステンダー/マウントアダプター:個別保管が基本。接点は乾いた綿棒で軽く清掃→キャップ装着。
- バッテリー(LP-E6系など):本体から外し、40〜60%で保管。長期は耐火ポーチが安心。
ニッケル水素をストロボに使う場合は電池を抜いて保管(液漏れ・自己放電対策)。
FUJIFILM X-T50 の保管
- ボディ:電源OFF→数秒待機→ボディキャップ装着。相対湿度は40〜50%をキープ。
(※手ぶれ補正搭載機全般にいえることとして)電源OFF直後の移動・振動は避け、ユニット停止後に収納。 - レンズ(XF/XC):前後キャップ+フード逆付け。絞りリング付は誤操作防止にA位置で保管しておくと次回の初期設定が明確。
- 結露対策:冷房車内→屋外、冬の屋外→暖房室内ではバッグに入れたまま30分順応。急な温度差はくもり・カビの原因。
- バッテリー(純正):本体から外し、40〜60%で保管。月1で点検・追充電。端子は金属接触しないよう個別ケースへ。
共通のコツ:いずれのメーカーでも、湿度計常備・乾燥剤の管理(再生/交換)・月1の可動(リング/スイッチを軽く動かす)を習慣化。
長期保管ほど、相対湿度40〜50%と衝撃を与えない取り扱いが寿命を左右します。
トラブル時の対処:カビ・くもり・接点不良
自分でできる範囲
- 外装・前玉の軽微なくもり:ブロアー→クリーナーごく少量→中心から放射状に拭き上げ
- 接点不良:乾いた綿棒で金属接点を軽く清掃(薬剤は使わない)
専門修理に出すべき症状
- レンズ内部のカビ・曇り・バルサム切れの疑い
- AF異音/IBISやISの異音・振動、ズームの引っかかり
再発防止チェック
- 収納は相対湿度40〜50%を維持(湿度計常備)
- 帰宅後は拭く→乾かす→収納の5分ルーティンを徹底
まとめ:適切な保管でカメラを長持ちさせよう
今日からできること:保管方法の見直し
- 帰宅後5分ルーティン:拭く→乾かす(1〜2h)→収納→湿度チェック
- 収納先の基準:相対湿度40〜50%(防湿庫 or ドライボックス+湿度計)
- レンズの扱い:長期はボディから外し、前後キャップ+フード逆付け、縦置きで圧力回避
- バッテリー:本体から外し40〜60%残で保管/月1で残量点検
- バッグ入れっぱなし禁止:密閉・残湿はカビの温床。必ず外に出して乾燥
定期的なメンテナンスの重要性
- 月1:乾燥剤の状態確認・再生/湿度計の数値確認/リング・スイッチを軽く可動
- 季節の節目(梅雨・秋雨・冬の結露期):清掃強化と湿度管理の点検頻度アップ
- センサー&接点ケア:汚れ・接点酸化の兆候があれば早めにクリーニングへ
- ファームウェア:不具合修正・安定化のため定期的に更新をチェック
撮影を楽しむために:万全な準備を
- 前日チェック:バッテリー満充電/予備を用意/カードはカメラでフォーマット
- 当日持ち出し:レンズは必要本数のみ/ドライパック(シリカゲル小袋)をバッグに1つ
- 雨天・海辺帰りの初動:バッグから出し陰干し→防湿環境へ。ドライヤー直風や電子レンジは厳禁
- 習慣化:収納場所・湿度・道具の“定位置化”で、迷わない導線を作る
正しい保管は画質・信頼性・資産価値の三拍子を守ります。今日できる小さな一手から始めて、次の撮影を最高のコンディションで迎えましょう。

2025.06.22
本記事では、学割付きパッケージを提供する代表的な 3 校 アドバンスクールオンライン・たのまな・デジハリ ONLINE を 価格・講座内容・サポート体制の3視点で徹底比較。 「買うならどこが自分に合う?」「動画講座の質は?」「質問サポートの違いは?」 ──そんな疑問を、早見表...

2025.06.23
本ガイドでは、2025 年 6 月最新の 会員登録 30%OFF / アプリ・LINE 限定 5%OFF / 毎月16日 GOOPASS DAY ほか全 5 ルートのクーポンを完全網羅。 さらに Rentio・DMM と総額を比較し、 クーポン適用後の実質レンタル...


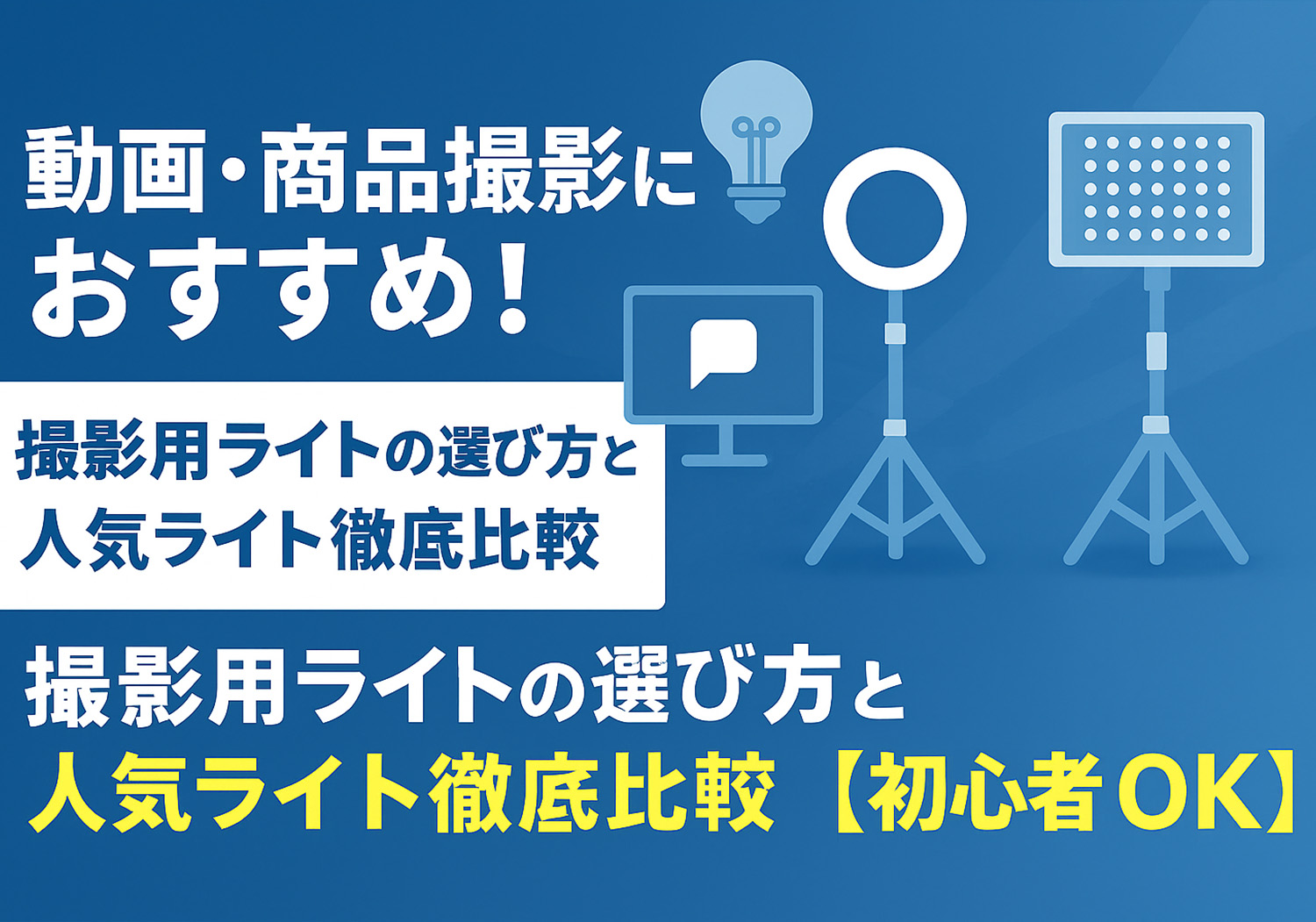
コメント