
こんにちわ、合同会社トビガスマル代表の廣瀬高之です。
「動画を使ったPRや販促を検討しているけれど、予算が心配…」そんな岡山の中小企業経営者の方へ朗報です。
いま国や自治体では、中小企業がデジタルマーケティングを導入・強化する際に活用できる多彩な補助金制度を用意しています。なかでも注目したいのが、販路拡大やブランド力向上に直結しやすい「動画制作費用」の補助。企業紹介や商品PR、採用活動など、多岐にわたる場面で活躍する動画を低コストで制作できるとあって、多くの企業が成果をあげています。
本記事では、具体的な補助金の種類や申請方法、成功事例まで徹底解説。補助金をフル活用して、動画を使った新たなビジネスチャンスを掴むためのヒントをお届けします。実際の申請や制作の流れも詳しくご紹介しますので、「初めて補助金を使うから不安…」という方もご安心ください。動画がもたらす可能性を、補助金を追い風に広げてみませんか?
目次
動画制作が企業成長に与える影響
デジタル時代において、動画コンテンツは企業のブランディングや販促、採用活動に欠かせない要素となっています。事実、マーケティング担当者の約95%が動画マーケティングを全体戦略の重要な部分と位置付けており、動画を活用しないことは貴重なエンゲージメント機会を逃すことにつながります。また、商品やサービスの購入決定には動画が大きな影響を与えており、2023年の調査では84%の人がブランドの動画をきっかけに購入に至ったと報告されています(出典元: 動画マーケティング調査を行う Wyzowl社 が公開した年次レポート「The State of Video Marketing」)このように動画には高い訴求力があり、テキストや画像では伝えきれない情報や企業の魅力を直感的に伝えることができます。
中小企業にとっても、動画を活用することは競合との差別化や顧客との信頼構築に極めて有効です。例えば、会社紹介動画で自社のストーリーや強みを表現すれば、ブランド認知度や親近感が高まり、新規顧客の獲得や優秀な人材の採用につながるでしょう。動画制作は決して大企業だけのものではなく、適切な投資対効果を見込めれば中小企業でも積極的に取り入れるべき施策なのです。
しかし、動画制作には一定の費用がかかるため、予算面で二の足を踏む経営者の方も多いでしょう。そこで注目したいのが「補助金」の活用です。国や自治体の補助金を上手に利用すれば、動画制作費用の一部を賄い、低コストで高品質な動画マーケティングを実現できます。
岡山で利用できる動画制作向け補助金の概要
岡山県内の中小企業が動画制作に活用できる主な補助金として、国の代表的な中小企業支援策である「小規模事業者持続化補助金」や「IT導入補助金」が挙げられます。また、岡山県や市町村が独自に提供する地域限定の補助金も存在します。以下、それぞれの概要を見ていきましょう。
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、中小企業庁と商工会議所(または商工会)が連携して実施する、全国対象の補助金制度です。小規模事業者(常時従業員数が商業・サービス業で5人以下、製造業等で20人以下など)が対象で、自社の経営計画に基づく販路開拓や生産性向上の取組みに対して経費の一部が補助されます。
この補助金では、広告宣伝や販売促進に関わる費用も広く認められており、動画制作費用も補助対象に含めることが可能です。たとえば会社紹介動画や商品PR動画の制作費は、「広報費」や「外注費」として計上できます。ただし、単に「動画を作りたい」という理由では採択は難しく、動画を活用してどのように売上拡大や顧客獲得につなげるかを具体的に計画し示す必要があります。
補助率・上限額
補助率は一般的に2/3(※赤字事業者の場合3/4)で、補助上限額は通常枠で50万円、条件次第では最大200万円まで引き上げられます。例えば50万円の動画制作費用なら、その2/3の約33万円が補助され、自己負担は約17万円で済む計算です(※採択枠や追加要件によって変動)。
対象経費の例
動画制作に直接関わる企画費・撮影費・編集費などが補助対象となり得ます(経費区分上は「委託費」や「広告費」等に分類)。さらに動画を活用するためのWebサイト掲載費用やSNS広告費といった関連経費も計画に組み込めば包括的に支援を受けられるでしょう。
申請のポイント
商工会議所や専門家の助言を受けながら事業計画書を作成することが推奨されています。公募は年に複数回(概ね3ヶ月毎)行われており、応募にあたっては事前に経営計画を練り上げ、補助事業の具体的な成果目標(売上○%増や新規顧客獲得数など)を明記しましょう。
IT導入補助金
「IT導入補助金」は、中小企業が業務効率化や売上向上につながるITツールを導入する際に、その費用の一部を支援する国の補助金制度です。主にソフトウェアやクラウドサービス、IT機器の導入が対象ですが、間接的に動画制作に活用できるケースもあります。
例えば、ECサイト構築やデジタルマーケティングツール導入の一環でプロモーション動画を制作・埋め込む場合や、動画コンテンツ配信プラットフォームを導入するといったケースでは、この補助金の活用が考えられます。ただし、IT導入補助金を利用するには事前に認定ITツールの中から導入ソリューションを選定し、登録されたIT導入支援事業者(ベンダー)を通じて申請する必要があります。純粋に動画制作サービスのみを依頼する場合は対象外となる可能性が高いため、動画制作を含むITパッケージ(例えば動画付きのWeb制作プラン等)で申請するのが現実的です。
補助率・上限額
通常枠では1/2補助、上限450万円までと定められています。例えば100万円のITツール導入費用(動画制作費含む)の場合、最大50万円が補助されます。また、小規模企業向けの「デジタル化基盤導入枠」では、費用50万円以下部分を3/4補助、50万円超~350万円部分を2/3補助する特例もあり、低予算のIT導入で手厚い支援を受けられます。
対象経費の例
動画関連では、営業支援ツール内で使用する動画コンテンツ制作費や、eラーニングシステムの動画教材制作費などが該当し得ます。要件として業務プロセスの改善や売上拡大に資するITツールの一部である必要があるため、単発のPR動画制作のみではなく、ITソリューションへの組み込みがポイントです。
申請のポイント
申請は全てオンラインで行い、事前にgBizIDプライムの取得が必要です。またIT導入支援事業者と協力して申請書を作成するため、早めに相談することが重要です。自社の課題を整理し、導入するITツールと動画の活用でどのように課題解決・業績向上を図るかを具体的に説明しましょう。
岡山県や市町村の独自補助金
国の補助金以外にも、岡山県および県内各市町村が独自に提供する補助金・助成金があります。これらは地域振興や地元企業支援を目的としており、動画制作を含む販路開拓や情報発信の取り組みが補助対象となるケースがあります。以下にいくつか例を挙げます。
岡山県の支援策
岡山県そのものが直接実施する補助事業としては、新市場開拓や展示会出展支援などがあります。例えば、県内企業が県外の展示会に出展したり新製品のプロモーションを行ったりする際に、経費の2/3・上限40万円まで補助する制度があり、この「プロモーション費用」には企業PR動画の作成費も含まれ得ます。自社HPでの動画公開やオンライン商談用動画資料の作成など、販路拡大につながる動画活用を計画に盛り込むと効果的でしょう。
市町村の補助金
岡山市や倉敷市をはじめ、県内各市町村でも中小企業支援の補助金を用意しています。例えば玉野市では「魅力ある職場環境づくり応援事業補助金」において、企業の情報発信支援として企業紹介動画の制作費を補助対象経費に認めており、補助率2/3で費用を支援しています。このような制度を活用すれば、自社の魅力を伝えるリクルート動画やPR動画を低コストで制作可能です。また津山市でも、販路開拓支援事業の一環で製品PRやデジタルマーケティング費用に対し2/3・最大40万円の助成を行っており、動画制作はその中の「プロモーション活動費」として補助対象になり得ます。
最新情報の入手法
自治体の補助金は募集時期や要件が年度ごとに変更されることがあります。岡山県や各市の公式Webサイト、商工会議所・商工会の案内、あるいは補助金情報サイト等で最新の公募情報をチェックしましょう。特に地域密着の補助金は公募期間が短かったり予算上限に達し次第締め切られたりするため、アンテナを高く張っておくことが大切です。
補助金を活用した動画制作の流れ
実際に補助金を活用して動画制作を行う場合、申請から制作・支払い、補助金受領まで一定のプロセスを踏む必要があります。ここでは一般的な流れを時系列で説明します。
①ニーズの整理と補助金の選定
まず自社でどのような動画を作りたいか、その目的(販促用・採用用・商品紹介等)と予算感を整理します。その上で、適用できそうな補助金を探します。岡山県内であれば前述のように「持続化補助金」「IT導入補助金」や自治体独自の補助金などが候補となります。必要に応じて商工会議所や専門コンサルタントに相談し、自社の計画に合った制度を選びましょう。
②動画制作会社への相談・見積取得
補助金申請には具体的な経費計画が欠かせません。そこで、早い段階で動画制作のプロ(制作会社)に相談し、企画内容と概算見積もりを作成してもらいます。当社にご依頼いただければ、補助金申請を見据えた最適なプラン提案とお見積もりの提供が可能です。プロの視点で効果的な動画企画を立てれば、申請書の内容も具体性が増し採択率向上につながります。
③申請書類の準備・提出
補助金の公募要領に従い、必要書類を作成します。主な書類は事業計画書(補助事業計画書)、補助対象経費の明細、見積書、会社の財務資料(決算書など)等です。事業計画書には、動画制作を通じて達成したい目標や具体的な活用方法、事業効果(売上増加見込みや集客数アップなど)を盛り込みます。書類作成時は誤字脱字や数字の整合性に注意し、要件を満たしていることを確認しましょう。準備が整ったら期限内に申請を提出します(電子申請の場合は事前の登録も忘れずに)。
④採択結果の通知・契約
提出後、審査を経て採択可否の結果通知があります。採択された場合、交付決定の手続きを経て正式に補助事業スタートとなります。ここで初めて動画制作会社との正式な契約・発注を行います(※多くの補助金では交付決定前の契約・支出は補助対象外となるため、結果が出るまで着手しないよう注意)。当社では採択後すみやかに制作工程に入れるよう準備しております。
⑤動画制作の実施
補助事業の期間内に動画制作を進めます。企画打ち合わせ、シナリオ作成、撮影・編集といった工程を経て、納品物(動画ファイル)が完成します。制作途中も補助事業の要件(例えばロゴ表示やクレジット表記等が指定されている場合)を満たすよう配慮しながら進めます。当社は岡山の企業様向けに多数の動画制作実績があり、貴社の魅力を最大限に引き出すコンテンツを制作いたします。
⑥実績報告と支払い
動画が完成したら、それを活用した販促活動(例:Webサイト掲載や動画広告実施)も行い、事業を完了させます。補助金事務局へ実績報告書を提出し、支出証拠(領収書や請求書)、制作物の提出や事業成果の報告を行います。動画制作会社への支払いは一旦全額を事業者が立替払いし、補助金は後日精算払いで支給されるケースが一般的です。つまり、まず制作費を全額支出し、その後報告が認められれば補助相当額が振り込まれる流れです。
⑦補助金の受領
実績報告が受理され問題なければ、数ヶ月後に指定口座へ補助金額が支払われます。これで補助事業は完了です。あとは完成した動画を継続的に活用し、効果検証を行いましょう。当社では納品後の運用に関するアドバイスや追加の動画活用施策のご提案も行っております。
以上が大まかな流れとなります。初めて補助金を使う場合は不明点も多いかと思いますが、当社では補助金活用型の動画制作について豊富な経験とノウハウがあります。申請サポートから動画制作、報告書用の資料提供まで一貫してお手伝い可能ですので、安心してご相談ください。
補助金活用事例
事例:岡山市の製造業A社の場合
岡山市で金属加工を手掛ける創業20年ほどの製造業A社では、優れた技術力がありながら知名度が低く、新規顧客開拓に課題を抱えていました。そこでA社は自社の強みを広く発信するため、企業PR動画の制作を検討。しかし予算面の不安があったため、地元商工会議所に相談し「小規模事業者持続化補助金」の活用を決めました。
A社は当社のサポートのもと補助金に申請し、50万円のPR動画制作プロジェクトを計画しました。補助金の通常枠採択により2/3の約33万円が支給されることになり、自己負担は約17万円で済みました。動画内容は、工場内で働く熟練スタッフの作業風景や社長のメッセージ、製品の品質検査プロセスなどを3分程度にまとめた本格的なものです。当社は企画段階から参画し、A社の強みである「高精度加工」と「迅速な納期対応」を分かりやすく伝える構成を提案。最新のドローン空撮やアニメーションも活用して映像に迫力と親しみやすさを両立させました。
完成した動画はA社の公式サイトやYouTubeチャンネルで公開されただけでなく、営業担当が商談前に取引先へ動画リンクを送付するなど多面的に活用されました。その結果、動画公開後3ヶ月で問い合わせ件数が前年同時期比で150%に増加し、新規取引先の開拓につながりました。さらに、この動画を見た地元大学生からインターン希望の連絡が入るなど採用面でも効果が現れました。A社の社長は「補助金のおかげで低リスクで挑戦できた。想像以上の反響があり、今後も動画を使った情報発信に力を入れたい」と大変満足されています。当社としても、補助金活用によって生まれた成功事例としてA社を継続的にサポートし、今後は製品ごとの紹介動画シリーズ展開も計画中です。
補助金申請のポイントと注意点
補助金を確実に活用するためには、申請時のポイントや注意事項を押さえておくことが重要です。以下に、よくある課題と対策をまとめました。
明確な目的設定
動画制作を通じて何を達成したいのか(売上○%増、問い合わせ件数○件増、採用○名など)を具体的に定め、それを申請書に反映しましょう。漠然とした目的では審査員に伝わらず、不採択のリスクが高まります。補助金の目的(販路開拓や生産性向上など)に合致した動画活用計画になっているかも再確認してください。
スケジュール管理
補助金の公募期間や締切を守るのは大前提ですが、制作スケジュールも逆算して計画する必要があります。採択後に短期間で動画を納品しなければならないケースも想定されるため、制作会社と日程を共有し無理のない計画を立てましょう。特に年度末が補助事業の実施期限となることが多いため、計画遅延には注意が必要です。
書類の正確さ
申請書類の不備は採択以前に失格となる恐れがあります。記入漏れ・誤記がないか、必要添付書類(見積書、決算書など)が揃っているか、提出前にチェックリストで確認しましょう。事業計画書では数字や根拠に一貫性を持たせ、根拠のない過大な売上予測は避けつつもポジティブな効果を示します。また、補助事業に係る経費積算根拠を明確に(○○費○円=○時間の撮影×単価など)記載すると信頼性が高まります。
採択率を理解する
補助金は応募すれば必ずもらえるものではありません。人気の制度では競争率も高く、例えばIT導入補助金の2022年度平均採択率は約66.4%と報告されています。小規模事業者持続化補助金でも回によっては半数程度しか採択されないこともあります。不採択の場合も念頭に置きつつ計画を練ることが大切です(不採択でも次回公募で内容をブラッシュアップして再挑戦することは可能です)。
事前着手の禁止
多くの補助金では交付決定前に事業着手(契約や支出)した経費は補助対象外です。つまり、結果が出る前に動画制作を始めてしまうと、その費用は補助金ではカバーされません。焦る気持ちを抑え、必ず採択・交付決定を待ってから発注・制作を開始しましょう。これはよくある失敗例なので注意が必要です。
実績報告と経費管理
採択後は計画通りに事業を実行するだけでなく、経費領収書や制作物の納品証拠をしっかり保管しましょう。補助事業完了後の実績報告では、当初計画とのズレや経費の過不足がないか精査されます。不適切な支出や計画未達(例:動画未完成や公開できなかった等)があると補助金が減額・返還となる場合もあります。経費項目の変更が必要になった場合は事前に事務局へ相談し承認を得るなど、ルールに従って進めてください。
専門家の活用
初めて申請する場合、行政書士や中小企業診断士等の専門家に書類作成を依頼したり、商工会議所の窓口支援を受けたりするのも有効です。客観的な視点で事業計画をブラッシュアップでき、採択率向上につながります。当社でも必要に応じて信頼できる補助金コンサルタントと連携し、お客様の申請をサポートいたします。
以上のポイントを押さえて準備すれば、補助金申請の成功率は格段に上がるでしょう。手間はかかりますが、その分リターンも大きいため、ぜひ慎重かつ積極的に取り組んでみてください。
動画制作の効果とROI(投資対効果)
補助金を活用することで、企業は低リスクで動画マーケティングに挑戦できるようになります。自己負担が軽減された分、動画から得られる成果が費用に見合うか(ROI:Return on Investmentの略、投資収益率)のハードルも下がり、チャレンジしやすくなるでしょう。
では、実際動画コンテンツにはどれほどの効果があるのでしょうか?複数の調査が示すところによれば、動画マーケティングのROIは非常に高い傾向にあります。ある調査ではマーケターの92%が「動画は自社にもたらすROIがプラスだ」と回答しており、多くの企業で動画投資が利益につながっている実態が伺えます。また前述のように、動画経由で商品購入や問い合わせに至るユーザーも非常に多く、適切に活用すれば売上増加や顧客獲得に直結する可能性が高いのです。
具体的な効果としては、以下のような例が報告・期待されています。
売上・集客の増加
商品紹介動画をサイトに掲載したところコンバージョン率が向上し売上が増加、あるいはSNSで配信したプロモーション動画が拡散され来店者数が増えた、といった事例が多くあります。動画は文字や画像よりも情報量が多く短時間で訴求できるため、興味喚起と購買促進に優れています。
ブランディング効果
企業の理念や世界観を表現したブランド動画は、視聴者の記憶に残りやすく企業イメージ向上に寄与します。例えば地元岡山の歴史や風景を織り交ぜた動画を制作すれば、地域密着の姿勢が伝わり親近感を醸成できます。こうしたブランディングは長期的なファン顧客の育成につながり、価格競争に陥らない強みとなります。
採用力の向上
リクルート動画を採用サイトに掲載すると、会社の雰囲気や社員の様子が伝わり応募者のミスマッチ減少や応募増加につながります。文字だけの求人票では伝えきれない魅力を動画で補完することで、優秀な人材確保に効果を発揮します。
情報伝達コストの削減
製品の使い方説明やサービスの導入事例などを動画にまとめておけば、営業担当が一から説明するより効率的に顧客へ情報提供できます。結果として営業工数の削減や問い合わせ対応コストの減少といった効果も期待できます。
このように、動画制作への投資は様々な角度からリターンを生み出し得ます。補助金を使えば初期費用負担が軽減されるため、ROIが一層向上しやすくなる点も見逃せません。極端な例を挙げれば、本来100万円の費用対効果(売上増など)が見込める動画プロジェクトに補助金で半額の50万円で取り組めた場合、ROIは実質2倍になる計算です。実際には効果測定が必要ですが、「費用対効果の高いマーケティング施策」として動画制作を導入できることは中小企業にとって大きなメリットでしょう。
もちろん、動画を作って終わりではなく、その後の活用戦略やPDCAも重要です。公開後の視聴データを分析し、必要に応じて動画内容や配信方法を改善することで、さらなるROI向上が期待できます。当社では動画納品後も効果検証や追加施策のご相談を承り、継続的なマーケティング支援を行っています。
まとめ:今すぐ補助金を活用して動画制作を始めるべき理由
最後に、本記事のポイントをまとめます。岡山の中小企業経営者の皆様は、今こそ補助金を活用して動画制作に踏み出す絶好の機会です。
デジタル時代において動画コンテンツは圧倒的な情報伝達力と影響力を持ち、販促・ブランディング・採用など企業成長のあらゆる局面で効果を発揮します。動画マーケティングを取り入れることで、競合との差別化や新たなビジネスチャンスの創出が期待できます。
国の「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」や岡山県・市町村独自の補助金によって、動画制作費の一部を公的に支援してもらえます。これにより初期コストのハードルが下がり、低リスク・高リターンで動画プロジェクトを実現できます。
補助金を賢く活用した企業では、実際に売上増・顧客増・採用成功などの成果が出ています。補助金活用で得た動画は、中長期的にも企業の資産となり、繰り返し活用することで継続的な集客・販促効果をもたらします。
申請から制作まで不安な点も多いかもしれませんが、当社のような動画制作のプロフェッショナルに相談いただければ、企画段階から丁寧にサポートいたします。補助金活用のノウハウも含めワンストップで対応しますので、煩雑な手続きも安心してお任せください。
まずはお気軽にご相談ください。
当社では岡山の企業様向けに、補助金を活用した動画制作プランのご提案や申請サポートを行っています。お問い合わせいただければ、御社の状況に合わせた最適なプランを無料相談にてご提案いたします。行動を起こすなら今です。この機会にぜひ、補助金を追い風に動画制作をスタートしましょう!

日本におけるYouTubeとFacebookの利用動向 今回は、総務省の最新データ(令和4年通信利用動向調査)を活用し、YouTube広告の優位性を示しつつ、両者の違いを分かりやすく解説します。 YouTubeとFacebookの利用率の違い 日本における主なSNSの利用率は次のと...


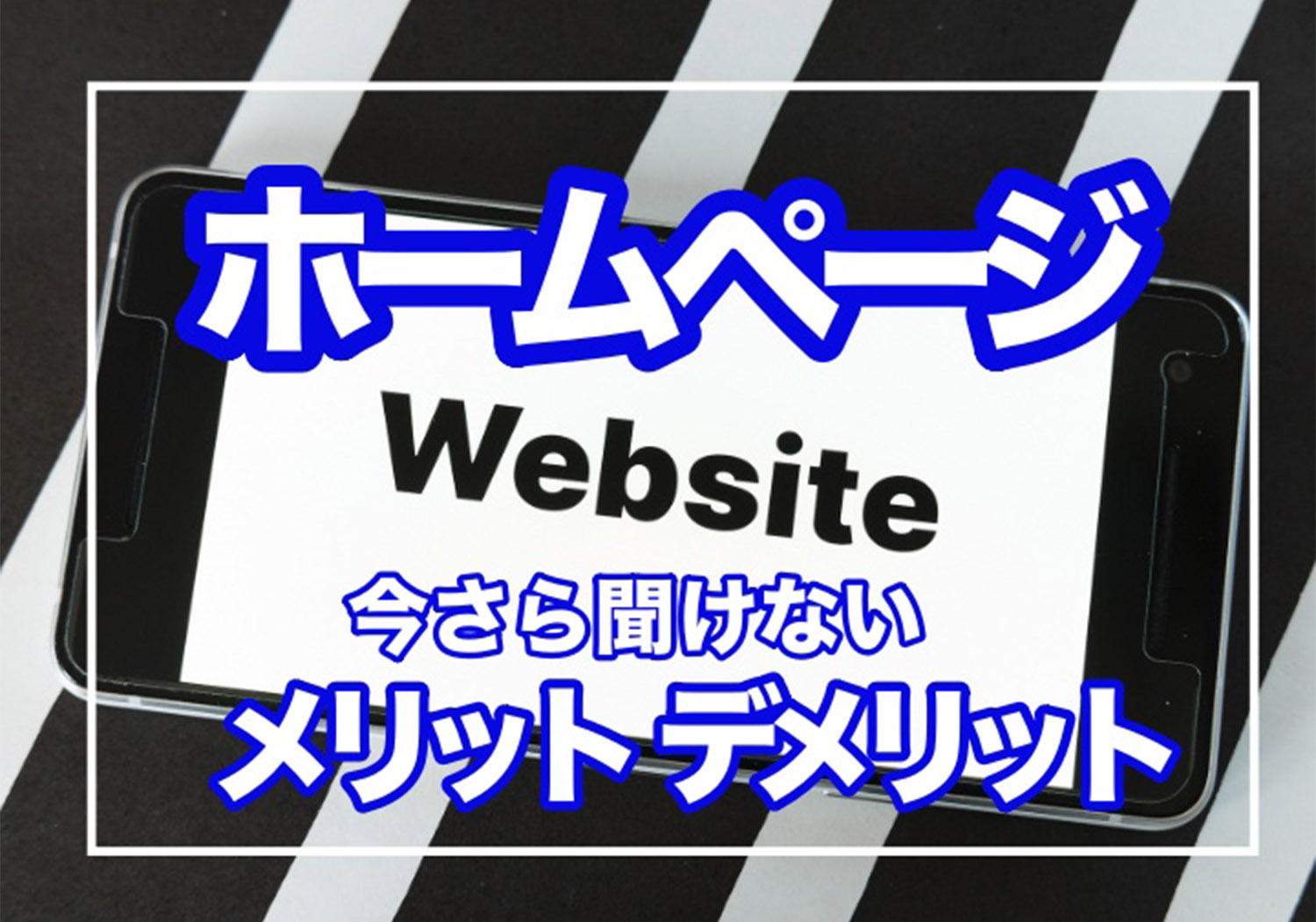
コメント