
こんにちは、クセノツヨイ映像制作会社「トビガスマル」代表の廣瀬です。
最近、「Web CMを作りたい」というご相談が増えています。
でもお話を聞いてみると、意外と多くの方がこう言うんです。
「テレビCMとはどう違うの?」
「Web CMって、どんな効果があるの?」
そして、
「うちみたいな会社でも意味ありますか?」
結論から言えば、あります。
むしろ今の時代、Web CMを活用できるかどうかが、ブランドの“体温”をどう伝えるかの分かれ道です。
かつてはテレビが主戦場でしたが、
今やスマホ・SNS・YouTubeなど、企業が“自分のチャンネル”を持てる時代。
その中で“動く広告=Web CM”は、
ターゲットに直接語りかけるもっともパワフルなコミュニケーション手段になりました。
この記事では、
を、トビガスマルの制作現場で培った経験から、わかりやすく解説します。
読後には、あなたの頭の中で、「自社ならどんなWeb CMを作るべきか」が明確になります。
さあ、次の一歩を“動く広告”でデザインしていきましょう。
目次
なぜ今、Web CMが企業活動に欠かせないのか
テレビCMからWeb CMへ──広告の主戦場が変わった
かつては「映像広告=テレビCM」という時代でした。
しかし今や、ユーザーの視聴環境はスマホ・SNS・YouTube・配信アプリなどに大きく移行しています。
企業の発信もテレビ中心から、“Webを主戦場にした動画広告”へ。
中でも、ブランドやサービスを短尺で訴求するWeb CM(ウェブシーエム)は、
企業の顔として欠かせない存在になりつつあります。
しかもWeb CMは、放送枠に縛られず自由に展開できるのが特徴。
SNS・YouTube・オウンドメディアなど、企業自身が“発信の場”を持てるようになった今、
動画広告の主役は確実にWebにシフトしています。
“誰にでも届く”から“誰に届けるか”へ
テレビCMの最大の特徴は「マス配信」ですが、
Web CMの最大の武器は、“ターゲットを絞って届けられる”ことです。
年齢・地域・興味関心などを細かく設定して広告を出せるため、
少ない予算でも「伝えたい相手にだけ」映像を届けることができます。
これが、特に中小企業や地域ブランドにとって大きなチャンスです。
また、Web CMは反応をすぐに数値で確認できるため、
「見てもらえた」「最後まで視聴された」「クリックされた」など、成果を可視化できます。
視聴者の行動動線に“動画”が入り込んでいる
現代のユーザーは、何かを調べるとき、まず動画を探す傾向があります。
商品レビュー・採用企業・イベント情報——すべて動画で“確認”される時代です。
つまり、Web CMは広告ではなく「企業の入口」になっているのです。
動画を通じて企業を知り、信頼し、行動につなげる。
それが今の消費者行動の自然な流れです。
だからこそ、Web CMは「見せる広告」ではなく、“信頼を築く接点”として活用されるようになっています。
Web CMの3つの強み:スピード・自由度・データ
1つ目はスピード。
Web CMは放送局の審査やスケジュールに縛られず、短期間で公開・修正が可能です。
2つ目は自由度。
ストーリー・尺・フォーマットを自由に設計できるため、
企業の個性やブランドトーンをそのまま表現できます。
3つ目はデータ活用。
クリック率や視聴完了率などをリアルタイムで測定し、
次の動画改善に活かせる点がテレビにはない強みです。
これら3つの特性を活かせば、Web CMは小さく始めて大きく育てる広告戦略になります。
Web CMは“企業の声”を最短で届ける手段
今の時代、企業が「伝えたいことを動画で語る」のは特別なことではありません。
むしろ、それが当たり前になりつつあります。
Web CMは、テレビCMのような知名度戦略ではなく、
“ピンポイントで信頼を積み上げる広告”です。
目的を明確にし、短く強いメッセージを込める。
その積み重ねが、企業ブランドを静かに、しかし確実に成長させていきます。
Web CMで押さえるべき5つの目的とKPI
Web CMの効果を最大化するために大切なのは、「なぜ作るのか」を明確にすること。
目的が決まれば、訴求内容も演出トーンもKPI(成果指標)も自然に定まります。
ここでは、企業がWeb CMを制作するときに押さえておきたい5つの目的とKPI設定を紹介します。
① ブランド認知を広げる(Awareness)
もっとも一般的な目的が、企業やサービスの存在を知ってもらうことです。
いわば「顔を覚えてもらう」ためのWeb CM。
KPIは「インプレッション数」「視聴完了率」「ブランド検索数」。
とくに認知目的の場合は、短尺(6〜15秒)で印象的なコピーを打ち出すのが効果的です。
企業ロゴよりも“人の表情”や“ストーリー性”を優先して、感情に訴える構成にしましょう。
② 問い合わせや資料請求を促す(Lead)
サービス説明型のWeb CMでは、見た人をアクションへ導く設計が重要です。
ここでのKPIは「クリック率(CTR)」「サイト訪問数」「問い合わせ件数」。
Web CMの最後に、明確なCTA(Call to Action)を設置することが必須です。
「今すぐチェック」「無料で相談」など、シンプルで行動を促す一言が成否を分けます。
③ 商品・サービスの理解を深める(Education)
商品の特徴や使い方を説明するWeb CMは、理解促進型の映像です。
とくにBtoBやテクノロジー領域では、複雑なサービスをわかりやすく見せることが信頼につながります。
KPIは「平均視聴時間」「離脱率」「理解度アンケート」など。
ここでは“情報の整理”と“テンポの設計”が重要になります。
ナレーションや図解を交えながら、難しい内容を“感覚でわかる”構成に仕上げましょう。
④ 顧客ロイヤリティを高める(Engagement)
Web CMは、新規獲得だけでなく、既存顧客へのフォローにも効果的です。
たとえば利用者インタビューや企業の裏側を見せる動画は、ファンを育てる施策になります。
KPIは「コメント数」「SNSシェア」「再生回数のリピート率」。
“人間味のある映像”が共感を呼び、企業ブランドへの愛着を育てます。
⑤ 採用・企業ブランディングを強化する(HR Branding)
最近では、採用活動や社内ブランディングのためにWeb CMを使う企業が増えています。
社員や現場の姿を映すことで、企業文化や価値観をダイレクトに伝えられます。
KPIは「採用応募数」「エントリー率」「SNSでの反響」。
とくに若年層に向けた採用ブランディングでは、“自然体の映像”が最も効果的です。
目的とKPIを“セット”で考える
Web CMは、目的を決めてから制作すれば効果が10倍変わります。
目的とKPIがセットになっていれば、社内報告も明確で、改善もスムーズ。
「見てもらう」だけで終わらせず、「目的を達成する動画」にする。
それが、Web CMの真の価値です。
制作前に知っておくべき構成要素と尺の設計
Web CMの成功は、撮影や編集よりも“設計の段階”で決まります。
尺・構成・テンポ・メッセージの順番を誤ると、どんなに綺麗な映像でも「なんとなく見たけど覚えていない」動画になってしまいます。
ここでは、Web CMを制作する前に必ず押さえておきたい構成の基本要素と尺の考え方を紹介します。
① 冒頭3秒で“見る理由”をつくる
Web CMでは、最初の3秒が命です。
YouTubeやSNSではスキップやスクロールが一瞬で行われるため、
冒頭で「自分ごと化」させられなければ視聴維持は望めません。
たとえば…
- 質問型:「あなたの会社、採用動画に本気ですか?」
- 驚き型:「たった15秒で信頼をつくる方法があります。」
- 共感型:「忙しいのに、“伝わらない”ってつらいですよね。」
「最初の3秒で見る理由を与える」——これがWeb CMの鉄則です。
② 構成は“起承転結”ではなく“問題→解決→行動”
テレビCMではストーリー性が重視されますが、Web CMはより論理的な設計が求められます。
視聴者は時間を奪われたくないため、「見る価値のある情報」を早く知りたいのです。
理想的な構成は以下の3ステップ:
- 問題提起:「○○でお困りではありませんか?」
- 解決提案:「私たちが提供する○○がその課題を解決します」
- 行動喚起:「今すぐサイトへ」「資料をダウンロード」
このシンプルな構成が、Web CMで最も反応を生む黄金パターンです。
③ 尺(長さ)は“目的別”に最適化する
Web CMの最適な尺は、目的によって異なります。
万能な長さは存在しません。
- 6秒〜15秒:認知拡大・SNS広告向け。短くて強い印象を。
- 30秒:ブランド・サービス紹介。メッセージの芯を1つに絞る。
- 60秒以上:ストーリーテリング型。理念や採用向けに最適。
重要なのは、「尺を短くすること」ではなく、「1メッセージ1動画」にすること。
伝えたいことを削るのではなく、目的ごとに動画を分ける発想が成功の鍵です。
④ 画面設計:音なしでも伝わる構成を意識
SNSでの再生は多くが“ミュート状態”。
だからこそ、「音なしでも伝わる映像設計」が必須です。
ポイントは3つ:
- テロップで要点を常に補足する
- 画面上の動きを意図的に設計(視線誘導)
- 印象的なビジュアルで感情を補完
Web CMは、映像だけでなく「言葉を読む動画」でもあります。
だからこそ、視覚的な構成力がブランドの印象を左右します。
⑤ 終盤5秒で“次のアクション”をデザイン
Web CMは「終わり方」が命です。
ラスト5秒に行動喚起(CTA)を入れなければ、視聴者はそのまま離脱します。
効果的な締め方は以下のようなものです:
- 「詳しくは検索」→ ブランド検索を誘導
- 「今すぐ資料請求」→ 明確なCTAでリード獲得
- 「フォローして続きを見る」→ SNSの継続接点を設計
締めの一言は、“動画のゴール”を明確にする役割を持っています。
終わり方を設計できるかどうかで、動画のROI(投資対効果)は劇的に変わります。
構成と尺は“伝え方の戦略”
Web CMの設計は、デザインではなく戦略です。
構成と尺を計画的に決めることで、視聴者の集中力を最大限に活かせます。
つまり、動画制作は「どんな映像を撮るか」ではなく、
「どんな順番で伝えるか」が勝負。
この考え方が、反応率の高いWeb CMを生む土台になります。
Web CMの撮影・編集で抑える3つのポイント
Web CMは、映像の長さが短いほど一瞬の印象で勝負になります。
だからこそ、撮影と編集での「設計力」と「判断力」が成果を左右します。
ここでは、トビガスマルが現場で実践している3つの撮影・編集ポイントをご紹介します。
① “目的に合った構図”を選ぶ
Web CMの撮影では、構図=伝わり方です。
同じ被写体でも、カメラの高さ・角度・距離で印象がまったく変わります。
たとえば…
- ブランド訴求 → センター構図で安定感と信頼感を演出
- 採用・社風訴求 → 三分割構図で自然さと親近感を演出
- 現場・商品紹介 → 斜め構図で臨場感と動きを出す
被写体を撮る位置や背景の整理だけで、動画の“温度”は大きく変わります。
カメラを置く前に、まず「どんな印象を伝えたいか」を決める。
それがプロの現場で最初に行う“構図の設計”です。
② 音がなくても伝わる“画作り”を意識
SNSやYouTube広告の多くは音声OFFで再生されるため、
映像だけでメッセージを伝える工夫が必要です。
効果的な方法は次の3つ:
- 文字(テロップ)で要点を補足
┗ 文字数は多すぎず、「一行一意」でテンポよく。 - 動き(モーション)で注目を誘導
┗ カメラワークやアニメーションで視線の流れを制御。 - 色と構成で印象を固定
┗ ブランドカラーや背景のトーンで記憶に残す。
Web CMでは、「聞かなくても伝わる」設計が大前提。
それができて初めて、音付きでも“二度おいしい映像”になります。
③ テンポとリズムで“見る気持ち”を切らせない
編集段階で最も大事なのがテンポ設計。
テンポが遅いと離脱され、速すぎると情報が入ってこない。
理想は、「リズム感は軽快に、テンポは安定的に」。
視聴者が無意識に“心地よい流れ”を感じる編集がベストです。
そのためのテクニックとして、トビガスマルでは…
- カット間に“0.3秒の余白”を入れて呼吸感を作る
- BGMとセリフをぶつけずにリズムを調整する
- シーン転換時に“視線方向”を揃えて流れを維持する
テンポを整えることで、最後まで見てもらえる動画に変わります。
撮影と編集は“演出”ではなく“設計”
撮影と編集は、見栄えを作る作業ではありません。
それは、伝わり方をデザインする設計プロセスです。
構図・音・テンポ——。
これらを目的に合わせて設計することで、Web CMは「流される動画」から
“記憶に残る動画”へと進化します。
映像を美しく撮るのではなく、心地よく伝わるように組み立てる。
それが、トビガスマルが大切にしている“設計としての映像制作”です。
予算別:小規模から大規模までのWeb CM制作モデル
Web CMを作ろうと思ったときに、最初に気になるのはやはり「予算感」です。
とはいえ、金額の差は単なる「クオリティの差」ではなく、“目的と手段の違い”です。
ここでは、トビガスマルが実際の現場で提案している3つの制作モデルを紹介します。
① 小規模モデル(10万〜30万円):
社内完結・スピード重視型
社内広報・SNS発信用など、「とにかく早く出したい」ときに最適なモデル。
スマホや社内機材を活用して、撮影から編集までを内製するケースです。
この価格帯では、構成とテンポ設計がすべて。
「映像を綺麗にする」よりも、「メッセージを的確に届ける」ことを優先します。
💡ポイント:
- SNS向けの6〜15秒動画に最適
- テンプレート+明確なCTAでスピード感
- 制作時間は最短1〜2日で完了
このモデルの成功例は、「スピード×回数」。
数を重ねることでブランド認知を積み上げることができます。
② 中規模モデル(50万〜150万円):
プロ撮影・ブランディング強化型
最も多いのがこのモデル。
プロのカメラマン・ライター・編集スタッフが入り、“伝わる品質”を確保します。
ブランドムービー・サービス紹介・採用動画など、企業の「顔」となる映像を作るのに適しています。
💡ポイント:
- 撮影1日〜2日/編集期間約2〜3週間
- BGM・ナレーション・グラフィック演出を追加
- 撮影構成を目的別に最適化(例:ストーリー型・インタビュー型)
この価格帯では、「質×設計」の両立が可能。
映像が“見られて終わる”ではなく、“印象に残る”レベルに到達します。
③ 大規模モデル(200万〜500万円以上):
ブランドキャンペーン・広告展開型
企業全体のブランディングや全国キャンペーンに使うWeb CMは、設計と演出の総合力が問われます。
コンセプト設計・シナリオ開発・キャスティング・スタジオ撮影など、
「一つの映像をブランドの象徴にする」ことが目的です。
💡ポイント:
- 放送CMと同等の品質でオンライン展開
- 複数バージョン・SNS広告・イベント上映にも対応
- 撮影〜編集まで1〜2か月のプロジェクト規模
このモデルでは、映像単体ではなく“体験”をデザインします。
「動画を見る」ではなく「世界観を感じる」。
それが大規模Web CMの目的です。
予算ではなく“目的”から逆算する
Web CM制作は、予算で方向を決めるのではなく、目的から逆算して考えるのが鉄則です。
「なぜ作るのか」「誰に届けたいのか」「どんな行動を促したいのか」。
この3点が明確であれば、“今の自社に最適な規模感”が見えてきます。
映像の価値は、金額ではなく成果で測る時代。
予算の大小にかかわらず、設計されたWeb CMには確実に「伝わる力」が宿ります。
測定と最適化:効果を出すための運用術
Web CMの真価は、公開したあとに現れます。
「作って終わり」ではなく、「データを見て改善する」こと。
これこそが、Web CMがテレビCMと決定的に違う部分です。
映像は生き物。
配信後のデータを活かせば、1本の動画から何倍もの成果を引き出すことができます。
① 効果測定の基本指標を押さえる
Web CMの効果を見極めるには、まず4つのKPIを確認します。
- ① インプレッション数:動画が表示された回数。まずは認知の目安。
- ② 視聴完了率:最後まで再生された割合。内容の“引きつけ力”を測る。
- ③ CTR(クリック率):動画からサイトやLPへの誘導率。行動促進の指標。
- ④ CVR(コンバージョン率):最終成果(問い合わせ・応募など)の達成率。
これらを定期的にチェックし、「どの段階で離脱しているか」を把握することが重要です。
数字を見るだけでなく、視聴体験を観察することが最も効果的な改善につながります。
② ABテストで“仮説”を検証する
Web CMは、1本作って終わりではありません。
むしろ、2本目からが本番です。
タイトルや冒頭3秒、テロップの色、ナレーションの有無など、
細かな違いを複数パターンでテストし、反応の高い構成を検証します。
たとえば:
- パターンA:商品特徴を先に伝える構成
- パターンB:悩み→解決のストーリー構成
結果を比較し、CTRや視聴完了率が高い方を残す。
これを繰り返すことで、“最適化された映像”が生まれます。
トビガスマルでは、AI解析ツールを併用して視線・感情の動きをチェック。
人の心の動きを数値化して改善するのが、現代の動画運用です。
③ 広告配信の設計を見直す
どんなに良いWeb CMでも、配信設計がズレていれば成果は出ません。
広告媒体ごとに「向き・フォーマット・時間帯」が違うため、
目的に合わせて出し分けるのがポイントです。
- Instagram/TikTok:縦型・短尺で感情重視
- YouTube広告:横型・15〜30秒で情報と印象の両立
- Webサイト埋め込み:ブランド動画・採用動画など信頼重視
媒体別にトーンを調整することで、“同じ動画でも成果が3倍変わる”ことがあります。
④ 継続運用で“動画資産”を育てる
Web CMの最大の特徴は、資産化できる広告であることです。
1本作って終わりではなく、定期的に改善・再利用していくことで、
企業にとっての「映像資産」が積み上がっていきます。
再編集・リサイズ・SNS再展開などを行えば、
新規制作の数分の一のコストで新しい動画が生まれます。
つまり、Web CMのゴールは「完成」ではなく、“成長”です。
運用の中で進化し続ける動画こそ、最も費用対効果の高い映像になります。
Web CMは“運用で勝つ”時代
Web CMの成功は、最初の映像の出来ではなく、改善のスピードで決まります。
「作って、見て、直す」このサイクルを回せる企業が、
“動画の競争力”を手にします。
1本の動画をリリースしたら終わりではなく、
そこから「次の一手」を生み出すのが、Web CM時代の正しい勝ち方です。
まとめ|Web CMは“伝える”ではなく“動かす”広告である
Web CMの役割は、単に情報を届けることではありません。
視聴者の心を動かし、行動を生み出すこと。
それが、テレビCMにはないWeb CMの真価です。
「ブランドを知ってもらう」から、「好きになってもらう」へ。
「見てもらう」から、「動いてもらう」へ。
その変化を設計できる企業こそ、これからの時代に強く残ります。
Web CMは、映像を“つくる”仕事ではなく、“人の行動をデザインする仕事”です。
誰に・何を・どう伝えるのか。
その意図を明確にすることで、動画は一気に「戦略的メディア」へと進化します。
Web CMは“企業の声”を最短距離で届けるツール
いまや、Web CMは大企業だけのものではありません。
中小企業、自治体、学校、個人ブランド——。
誰もが「映像で語れる時代」です。
だからこそ重要なのは、“何を言うか”より“なぜ言うか”。
目的と熱意を持って作られた映像は、予算や技術を超えて人の心を動かします。
映像は、企業が社会に投げかける「声」です。
その声が誠実であればあるほど、信頼は積み重なっていきます。
“小さく始めて、大きく育てる”が正解
最初から完璧を目指す必要はありません。
小さく始め、配信し、データを見て改善する。
その繰り返しが、確実にブランドの厚みをつくります。
Web CMは“走りながら育てる広告”。
1本目で成功しなくても、方向性を掴めば次は必ず伸びます。
継続する企業ほど、確実に「映像力」が上がっていくのです。
最後に:映像は“想い”を社会に届ける手段
私たちトビガスマルは、いつもこう考えています。
動画は、会社の想いを社会に届けるための“翻訳”だと。
企業がどんな想いで動いているのか。
どんな人が、どんな情熱で仕事をしているのか。
そのリアルを伝える手段こそが、Web CMなのです。
だから、あなたの会社の想いもぜひ映像にしてください。
“伝わる動画”は、必ず人を動かします。
映像でブランドを育てる時代。今が、その第一歩を踏み出すときです。

2025.05.10
VSEOとは?YouTubeにおけるSEOの基礎 まずは基本となる「VSEO」とは何かを押さえておきましょう。VSEOとは「Video Search Engine Optimization(動画検索エンジン最適化)」の略で、簡単に言えば「YouTubeなどで動画を検索結果の上位に表示...
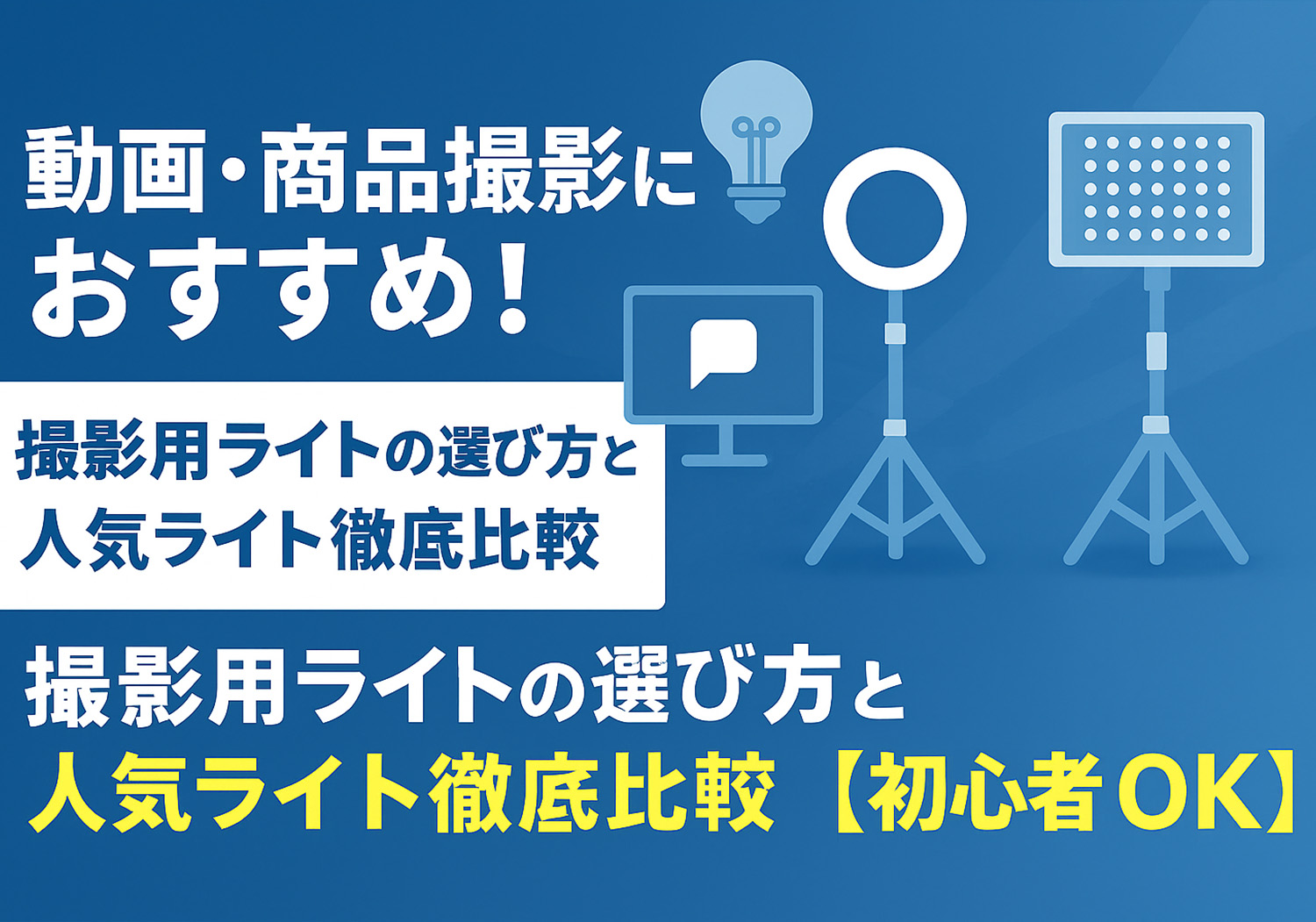
2025.05.11
実は、照明ひとつで動画や商品の見え方は劇的に変わります。暗くて地味だった映像も、適切なライトを使うだけでプロっぽい仕上がりに。 今回は、これから動画撮影やネットショップ用の商品撮影を始めたい方に向けて、撮影用ライトの基礎知識と選び方、そして2025年現在人気の機種まで、最新情報を交えて徹底...



コメント