
こんにちわ、合同会社トビガスマル代表の廣瀬です。
いま、世界中のクリエイターや知識発信者たちの間で注目されているプラットフォーム——それがSubstack(サブスタック)です。
「メルマガ」「ブログ」「コミュニティ」。これらをすべて一体化したようなSubstackは、文章で伝えたい人が、自分の言葉でファンとつながれる場所。
広告収益に縛られない“読者主導”のメディアとして、日本でもじわじわと浸透してきています。
この記事では、Substackの基本機能や始め方から、実際の活用事例、そして今後の可能性までを丁寧に解説していきます。
「自分のメディアを持ちたい」「ファンと直接つながりたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
Substackとは?基本機能と特徴
Substack(サブスタック)は、クリエイターが読者に直接コンテンツを届けるためのニュースレタープラットフォームです。
メール配信をベースにしながらも、ブログ・課金・コミュニティ機能まで備えており、 「SNSに頼らない発信」「広告に依存しない収益化」を実現する手段として注目を集めています。
Substackの主要機能:ニュースレター配信、課金システム、コミュニティ機能
Substackには、以下のような機能が備わっています:
- ニュースレター配信: メールで直接読者に記事を届ける(無料/有料どちらも可)
- 記事アーカイブ: Webサイトとしても機能し、過去記事は誰でも閲覧可能
- 有料購読モデル: 月額・年額課金で収益化でき、手数料は基本10%
- Substack Chat: 読者同士&クリエイターとのコミュニケーションツール
- ポッドキャスト&動画機能: 音声や映像もアップロードできる
つまり、“書く”だけでなく、“つながる・稼ぐ”までワンストップで実現できるのが最大の魅力です。
Substackの料金体系とプラン:無料プランと有料プランの違い
Substack自体の利用は基本無料です。誰でもアカウントを作成し、すぐに記事を書き始めることができます。
有料課金を導入した場合のみ、売上の10%がSubstackの手数料として差し引かれます。その他に、決済代行手数料(Stripe経由)として約3〜5%が必要です。
つまり、
- 読者からお金を取らなければ完全無料で運営可能
- 収益化したときだけ手数料が発生する“成果報酬型”
このシンプルで明快なモデルも、クリエイターにとって始めやすい理由の一つです。
Substackの始め方:アカウント作成から最初の記事公開までのステップ
Substackは、英語中心のUIではあるものの、直感的な操作で簡単に始められます。
基本的な流れ:
- アカウント作成: メールアドレスまたはGoogleアカウントで登録
- プロフィール設定: サブタイトル、ロゴ、テーマカラーなどを入力
- 配信方法の選択: 無料配信/有料課金のどちらかを選択
- 記事作成: 見出し・本文・画像などを挿入(エディターはシンプルで使いやすい)
- 公開: 「今すぐ公開」「メールで配信」「スケジュール配信」から選択可
1本目の記事を出すまで、最短10分〜30分あればスタート可能です。
カスタムドメインの設定(任意)
- SubstackのSettings → Domainへ進み、Add custom domainをクリック。
- 表示されたCNAMEをドメイン管理側のDNSへ登録。
- Substack側で認証→反映($50/媒体の一回払い)。
Tips:先にSubstack側でドメイン追加を完了→その後DNSにCNAMEを設定するとトラブルが少ないです。
Substackの料金と手数料(いくらかかる?)
- 基本料金:アカウント作成・配信は無料(有料購読をONにしたときのみ手数料が発生)。
- プラットフォーム手数料:売上の10%(Substack)。
- 決済手数料:Stripeの2.9%+$0.30/取引(国・決済手段で変動)。
- カスタムドメイン:一度だけ$50/媒体(任意)。
| 例 | 月間売上 | Substack 10% | Stripe(概算) | 手取り目安 |
|---|---|---|---|---|
| 100名×¥500 | ¥50,000 | ¥5,000 | 約¥2,000 | 約¥43,000 |
※Stripe手数料は通貨/決済手段で変動。概算のため実数はダッシュボードで確認を。
Substackで成功するための戦略
Substackは「書けば読まれる」ほど甘くはありません。 でも、読者を意識した発信・継続的な工夫・ファンとの関係構築を積み重ねれば、着実に成果につなげることができます。
ここでは、Substackを単なる“発信の場”ではなく、読者との信頼関係を育てる場として活用するための戦略を3つに絞ってご紹介します。
読者を惹きつけるコンテンツ作成術
Substackで最も重要なのは、「どんな記事を書くか」ではなく「誰の、どんな悩みに応えるか」です。
基本のポイント:
- タイトル: 疑問・メリット・感情を揺さぶる要素を入れる
- 冒頭文: 結論→背景→読者のベネフィット、の順で構成
- 配信頻度: 週1〜2回を目安に「忘れられない発信者」になる
さらに、体験談・失敗談・裏話など、個人的な視点を盛り込むことで、 情報だけでなく「この人だから読みたい」と思わせる力が強まります。
効果的な集客方法:SNS活用、クロスプロモーション、SEO対策
Substack単体では読者が増えにくいため、外部チャネルからの流入設計がカギになります。
主な集客手法:
- X(旧Twitter)やInstagram: 投稿→Substack記事にリンク→プロフィール固定など
- クロスプロモーション: 他のSubstackクリエイターと紹介し合う
- SEO対策: Webサイト化された記事をGoogleにインデックスさせる
とくにSNSからの流入は即効性が高く、「この人の考え方をもっと読みたい」という文脈でSubstackを紹介すると読者が増えやすいです。
コミュニティの構築:読者との交流、フィードバックの収集、コラボレーション
Substackの強みは、単なる「発信」ではなく、読者と“関係を育てられる”設計があること。
活用すべき機能:
- コメント欄: 質問や感想を受け取り、双方向のやりとりを生む
- Substack Chat: 雑談的なやりとりで距離感を縮める
- 有料読者限定コンテンツ: 熱量の高い読者を中心に“コアなファン”を育てる
また、他のクリエイターとのコラボ記事やインタビューなども、新たな読者との接点づくりに効果的です。
Substack内で伸ばす:発見・交流・紹介の機能
- Notes:短文タイムライン。引用/タグ付け/再投稿で露出拡大。
- Chat:購読者限定のグループ会話。濃い関係づくりに。
- Recommendations:他媒体の推薦で新規読者の流入を増やす。
- Referral:紹介プログラムで読者が読者を連れてくる。
※Notesは短文投稿、Chatは購読者向けの会話。紹介/推薦は成長施策の中核です。
配信形式:文章だけじゃない(音声・動画・ライブ)
- ポッドキャスト:記事と同じ媒体で配信・有料限定も可能。
- 動画投稿:「Video post」機能で直接アップ/収録(機能は動画ポスト時に有効)。
- ライブ:段階的に提供拡大中(先行提供→順次解放の方針)。
- 公式アプリ:iOS/Androidで視聴・交流・通知に強い。
Substackの活用事例
ここでは、実際にSubstackを活用して成果を上げている3つの注目事例をご紹介します。
それぞれのジャンル・発信スタイルを参考に、自分なりの活かし方のヒントを見つけてみてください。
TechSodaの事例:技術系ニュースレターの配信とコミュニティ運営
TechSodaは、国内外のスタートアップやAI技術、Web3関連の最新ニュースを毎週配信するSubstack。 技術に明るい読者層をターゲットに、“要約+個人の視点”という独自スタイルで差別化しています。
注目ポイント:
- 週1〜2回の配信で読者を“習慣化”
- XやThreadsとの連携で拡散力を確保
- 有料購読者限定でオンラインサロン的な交流も展開
情報提供 × コミュニティ構築の成功例として、技術分野のSubstack活用をリードしています。
文武両道(Bunburyoudou)の事例:教育系コンテンツの配信と読者との対話
文武両道(Bunburyoudou)は、教育・学習・探究に関する考察や実践記を発信している教育者によるSubstackです。
特徴は、“思考の過程”をシェアする文章スタイル。 コメント欄では読者との意見交換が活発に行われ、教育現場にいる読者との交流コミュニティが自然発生的に形成されています。
注目ポイント:
- 日常と教育をつなぐ視点がユニーク
- 読者参加型コンテンツが共感を呼ぶ
- 一部記事を有料化し、価値に対する対価を可視化
読者との“対話型メディア”としてSubstackを活用している好例です。
Michele De Lucchiの事例:デザインに関する洞察と美的探求
世界的な建築家・デザイナーであるMichele De Lucchi氏は、自身の哲学・スケッチ・建築論をSubstackで発信。 日常的なデザイン観察や作品の裏話などを交えながら、“思想と美意識”を可視化しています。
注目ポイント:
- 手書きスケッチや詩的な表現で世界観を確立
- 短文でも強い印象を残すクリエイティブ構成
- 英語圏外の読者からも支持を集め、国際的な交流が生まれている
ブランディングと思想発信を融合した、アート的Substackの事例として注目されています。
Substackの今後の展望と可能性
Substackは、ニュースレター配信ツールの枠を超え、クリエイターが“自分のメディア”を築けるプラットフォームへと進化し続けています。
ここでは、Substackの今後の進化と、これからのクリエイター経済における役割を考察していきます。
Substackの進化:新機能の追加とプラットフォームの改善
Substackは2024年〜2025年にかけて、下記のような機能強化を行っています:
- Substack Chat: 記事だけでなく、読者とのリアルタイムな会話機能を追加
- 動画・ポッドキャスト対応: 音声や映像による配信スタイルが可能に
- 複数著者運営: チームでのメディア発行もスムーズに
加えて、Substack Discoverという“新しいクリエイターに出会える仕組み”も進化中。 プラットフォーム内での発見性が高まり、読者獲得のハードルが徐々に下がってきています。
クリエイターエコノミーの未来:Substackが果たす役割
かつては「メディア=マスコミ」の時代でしたが、今は「個人がメディアになる時代」です。
その中でSubstackは、
- 広告収入に頼らずに読者から直接収益を得られる
- アルゴリズムに振り回されず、価値ある発信をコツコツ届けられる
- プラットフォーム外への脱出口(メール)を自分で持てる
という点で、「クリエイターの自由と継続性」を守る基盤になりつつあります。
特に、信頼や世界観を大切にする発信者にとって、Substackは“小さく始めて長く続けられるメディア”の形を提示してくれます。
効果測定:ダッシュボードとGA4の使い分け
- Substack内の指標:オープン率/クリック率/購読者増減/流入元(ダッシュボード)。
- GA4連携:Web上のページビュー・サインアップ・有料購読イベントを計測。
- 読み解き方:メール内の開封/クリックはSubstack側、Webの回遊はGA4側で見るのが最短。
まとめ:Substackであなたの創造性を開花させよう
Substackは、単なるメルマガ配信ツールではありません。 それはあなたの言葉で、価値あるつながりを育てるための“土壌”です。
誰かの評価を気にせず、自分のスタイルで書き、自分の声を信じて届ける。 そんな時代だからこそ、読者とまっすぐ向き合える場としてのSubstackは、非常に大きな可能性を秘めています。
はじめは数人の読者でも大丈夫。その中の誰かに届けば、それはすでに意味があるということ。 続けるうちにファンが生まれ、共感が生まれ、いつのまにか“メディア”になっている。Substackは、そんなクリエイターの背中をそっと押してくれる存在です。

トビガスマルでは、動画やWeb制作だけでなく、「文章によるブランディング」「Substackを活用した情報発信」についてのご相談も承っています。
「書くことに興味がある」「自分のメディアを育てたい」という方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
Substackが、あなたの創造性を羽ばたかせるきっかけになるかもしれません。
よくある質問(Substack)
Q. 料金は?無料で始められる?
A. はい。無料で開始可能。有料購読をONにした場合のみ10%(Substack)+Stripe手数料が発生します。
Q. カスタムドメインは使える?
A. 使えます。設定画面で追加し、DNSにCNAMEを登録。$50/媒体の一回払いが必要です。
Q. NotesとChatの違いは?
A. Notes=短文タイムライン、Chat=購読者限定の会話。役割が異なります。
Q. 文章以外も配信できる?
A. ポッドキャストや動画ポストに対応。ライブ機能は段階的に拡大中です。

2025.08.01
実際に私は - 参加者20名(M1‑M10, F1‑F10)が提出した 告白カード(最終 2 名指名)を回収。 - 両想いペアを確定し、結果レポート(成立/片想い/マッチ無し)を表示・エクスポート。 ──たったこれだけの指示文を入力しただけで、マッチングロジック...

2025.06.22
本記事では、学割付きパッケージを提供する代表的な 3 校 アドバンスクールオンライン・たのまな・デジハリ ONLINE を 価格・講座内容・サポート体制の3視点で徹底比較。 「買うならどこが自分に合う?」「動画講座の質は?」「質問サポートの違いは?」 ──そんな疑問を、早見表...


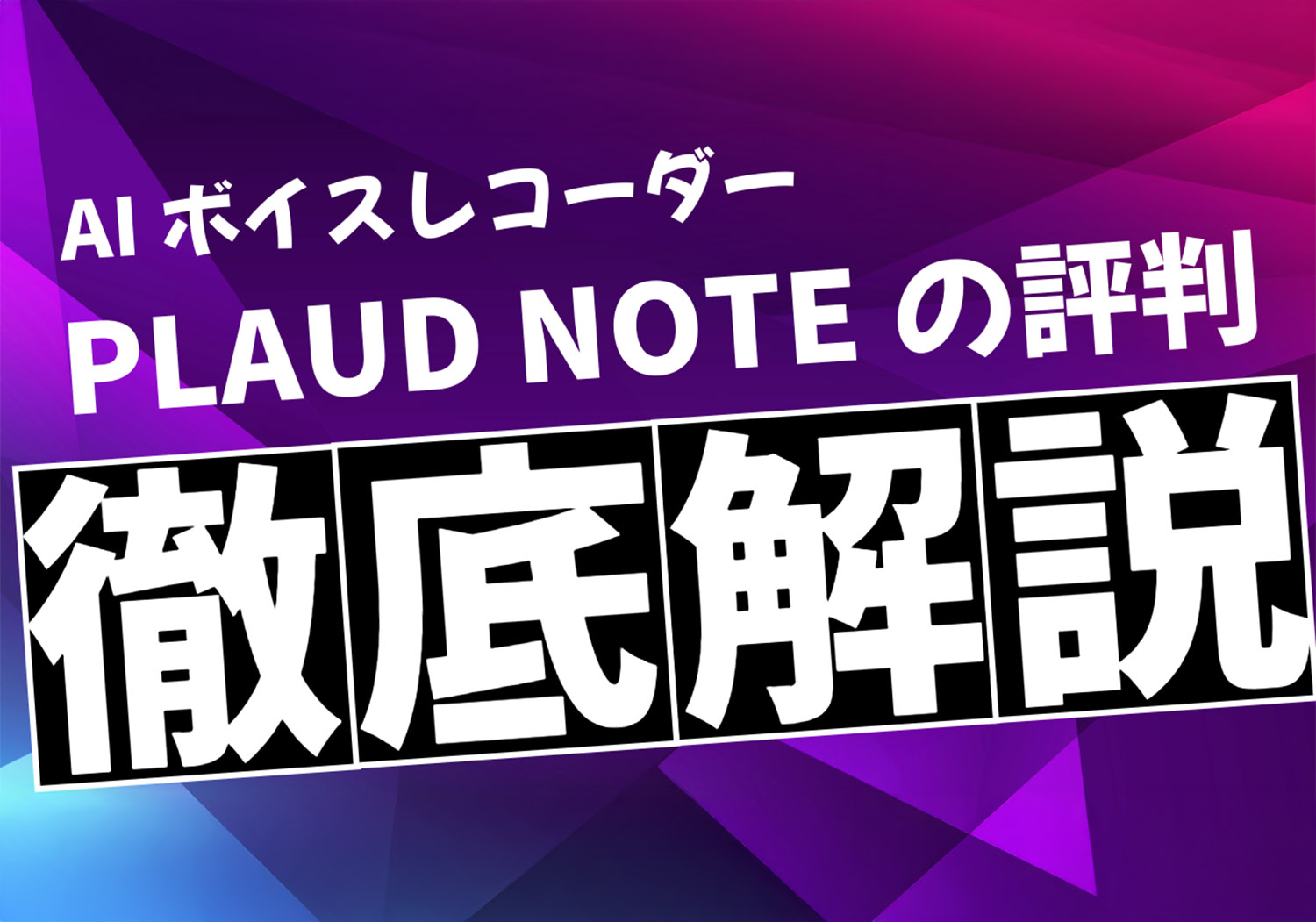
コメント